本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
地図ラボサイトと検索技術について(第1回) 2009年5月27日「事例から見るデジタルコンテンツ活用の可能性」より(全2回)
クロスメディア研究会の5月定例勉強会は、「事例から見るデジタルコンテンツ活用の可能性」として検索技術を活用したコンテンツ活用をテーマに開催。前半は、ヤフー株式会社 R&D統括本部フロントエンド開発本部 陸口満氏より、同社で運用している地図ラボサイト「LatLongLab」および地図・位置情報の動向についてお話を伺った。


写真下・奥がヤフー 陸口氏
我々は、「位置情報はライフスタイルを変える」と信じて、地図や路線情報をはじめ、地域系のサービスとしてグルメや地域情報等、いろいろと取り組んでいる。
位置情報がライフスタイルを変えると思う理由としては、1つは技術や環境の整備がだんだん整ってきている。2つ目に、環境が整備されることによって、地図に関する新たな取り組みがいろいろ行われている。3つ目として、地図はそもそも情報整理の優れたプラットフォームである。このあたりを理由として、うまくすればライフスタイルを変えていけるようなプラットフォームになれるのではないかと思っている。
地図デジタル化の歴史
その前に地図・位置情報について、簡単に歴史をまとめてみる。1995年前後、地図は紙からデジタル化への流れがあった。この頃はPCアプリケーションの最盛期で、紙で見る地図からPCで見られるようになったことで、印刷して持ち運びできるようになったり、簡単な検索が使えるようになったりすることで、紙で地図帳として持っていたものが、もう少し利便性が高まってきたというのが、この時代であった。
この後、いわゆるWeb前夜になるが、1997年前後に地図のサイト、Web上で地図が見られるようなサイトが登場する。MapionやMapfan等が、こういう形でサービスをリリースしている。Yahoo!地図情報は若干遅れて、1998年公開となった。
今の一般的な地図サイトはマウスでスクロールできたりするが、当時はまだ紙の置き換え版のような形で、ページのもう少し右のほうが見たいという場合はクリックしてもう一度ページ自体を読み込まなければいけないとか、まだまだ利便性は低かった。しかし、基本的に無料で見られるということが、ユーザーにとっては価値があったという時代である。
2004年以降になると、地図がスクロールできるようになったり航空写真が見られるようになったりなってきた。Yahoo!ではリアルタイムメンテナンスという、地図を毎日更新する仕組みを取り入れたり、Google Street View など、かなり価値のあるコンテンツも出てきている。
通信環境の整備や技術的な発展等、さまざまな要因があると思うが、どんどん地図の使い勝手が良くなってきて、所在地や目的地の地図を見るだけでなく、何かを調べたりすることが徐々に充実してきた。
最新の動向
地図の最近動向を3つくらいに挙げると、まず1つ目はAR系(拡張現実)がある。GoogleのAndroid端末ではGPSで緯度経度を取るのはもちろん、電子コンパスで端末がどちらの方向を向いているか、上を向いているとか左を向いているとか、そういったものを端末自体で把握できるようになっている(図1)。
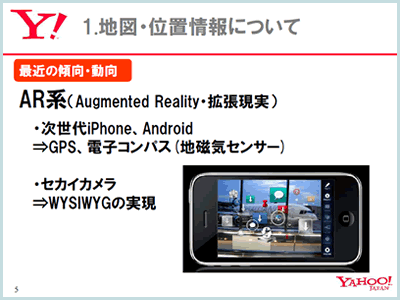
▲図1
これをうまく利用したと思うのは、「Sekai Camera(セカイカメラ) 」というアプリケーションである。これはWYSIWYGを実現しており、例えばiPhone等で自分の周囲を映像として撮っていくと、そのリアルな映像の上にエアタグという、ユーザーやCP(コンテンツプロバイダ)が付けたタグ情報が表示される。
例えば、何か新しいおもしろそうなものがある、建物があると思ってiPhone等で映していると、カメラを通してその名称が表れたり、それをクリックするとその名称の由来が取れたり、そういったものが実現しつつある。
2つ目の動向は、ここ数年よく聞かれるようになったライフログという言葉である。人の行い(life)を記録(log)することを指すが、技術やいろいろな環境が整うことによって、徐々に充実してきている。GPSやWi-Fiで緯度経度を取る仕組みもそのひとつである。
「今あなたはどこにいるか」、「どこで何をしているか」というようなものを、ユーザーがそこにポストするというか、落としていくことができるようになる。もしかすると自動的に端末を通じて「何をしていたか」というところまでが記録できるようになるのではないかと思っている(図2)。
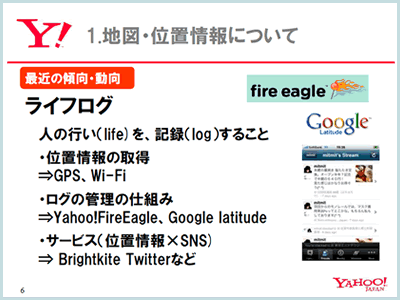
▲図2
一方で、取得した緯度経度情報や、そこで何をしたかというログの管理の仕組みというところも、米Yahoo!ではFireEagleという仕組みがあったり、Googleでもlatitudeという仕組みがあったりして、緯度経度のログの管理の仕組みも徐々に充実してきている。
さらに、サービスのほうも少しずつ出てきている。位置情報とSNSを組合わせた形で、Twitter のほかBrightkite というサービスがある。Brightkiteのように今どこにいて、何をしていて、写真を落としたり、そこに対して他のユーザーがコメントを落としていったりするようなことができるサービスが、結構盛り上がってきている。
私もBrightkiteをやっているので、(本日講演に来る前に)「この近くに来てご飯を食べている」というようなコメントを書いて投稿してきたが、それに対して会社の人からコメントが幾つか入っている。
この話は、基本的にはモバイルで「今ここにいる」という情報を取得するのがポイントになってくるが、PCに搭載するブラウザに対しても位置情報を取得する仕組みが徐々に生まれてきている。
次世代のFirefox、既存のFirefoxでも位置情報取得アドオンの「Geode」を組み込んだりGoogleのツールバーを入れたりすることで、今PCがどこにいるかという情報を、Wi-FiやGeo IPのような形で取得している。最近では、こういったことが少し傾向としてはあるのではないかというふうに考えている(図3)。
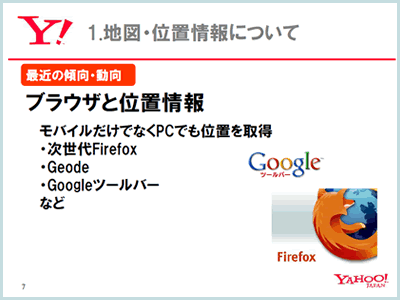
▲図3
こういった傾向がなぜあるのかということで、3つ挙げてみた。1つはWeb上に流通する情報は、正確に測ったわけではないが、8割くらいは位置情報が含まれていると言われている。先ほど、Yahoo!の地域系サービスという話をしたが、グルメとか、さまざまな店舗情報はもちろん持っている。病院情報も、もちろん持っている。
ユーザーが投稿するようなブログも、位置情報を持っているものがある。不動産もある。あとは、あまり位置情報と関係なさそうに思えるニュース等でも、どこで事件が起きたというようなものを含めて考えると、実は緯度経度を持っているのではないか。天気ももちろんそうである。
オークションというのは一見関係なさそうに見えるが、イベント系のチケットを売っていたりすると、イベントの開催場所という緯度経度の情報を持っていたり、新幹線のチケット等も、東京発新大阪というのを福岡の人に提示してもあまり刺さらないといった感じで考えていくと、実は緯度経度を持っていると考えられる。
Yahoo!JapanのWebで行うメイン検索のクエリの中にも、よく六本木とか杉並とか、そういったキーワードがあるが、大体25%~40%の検索ワードが緯度経度に関係していそうだというログの集計が出ているともいわれている。こういった緯度経度をユーザーが探しているというところで、いろいろとチャンスがあるのではないかと感じている。
一方でビジネスとしての位置情報と考えていくと、いろいろと取り組みは行っているが、成功している位置連動広告モデルというものは、まだないのではないか。オークションのように、場所に対して新幹線のチケットを提示するとか、ここに住んでいる人なのでここのイベントを紹介するといった仕組みは、実はまだまだできていない。
Yahoo!地図でも、ユーザーが見ている地図に対して広告を出してはいるが、それが本当にその地図を見ているユーザーにとって心に残るものかどうかというのも、まだ測り切れていないし、効果のほうもまだこれからと考えている。
あとは、前述のGPSのような形で今いる場所に対して適した広告を表示するような仕組みも、まだこれからということで、完全な勝ちモデルや勝ち組のようなものはないという状況である。
最後に、プライバシーの課題について触れる。これはログの取得とかログの管理の部分に当たると思う。先ほど自分のログというか、Brightkiteを紹介したが、私の所属しているチームのメンバーでも、女性など、そういうものを外に晒したくないという人はかなりいる。その位置情報をどう安全に安心して使ってもらえるかという管理の仕方は、今後の課題であろう。
一方で、ビジネスに絡んでくると思うが、それを外部に落とすことで、ユーザーに利便性の高いものをこちらが提供できるようになってくるということが、もう1つの課題だと考えている。
(続く)
