本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
似て非なる大阪と東京の商店街とフリーペーパー
掲載日: 2010年11月17日
三回目の西部支社だよりである。前回は水都大阪を代表する道頓堀のネオンについてお話したが、あれから約二月、源八橋から見える大川両岸の木々は紅葉の真っ盛り。赤黄に彩られた水面を眺めていると都心であることを忘れるほどの静寂さである。【西部支社だより(3)】
大阪はかつての「水の都」を取りもどそうと数年前から川清掃に力を入れているのだが、川清掃の前に人心の清掃から始めなくてはいけない、情けないニュースが話題になっている。
さて、堀川同様大阪の中心街には大きな商店街、それもアーケード商店街が多いのに驚かされる。商店街アーケードの最初は北九州市小倉北区の「魚町銀天街」といわれているように全般に西日本に多いが、とくに関西圏は多いと聞く。たとえば東京と大阪の高級商店街を比べると違いがよくわかる。東京の高級ショッピング街といえば「銀座」である。そのシンボルは銀座4丁目の交差点、和光の時計台、三越、日産といったイメージが誰でも浮かぶ。アーケード商店街のイメージなど微塵もない。それに対して大阪の高級ショッピング街は「心斎橋」である。そのシンボルはウィリアム・メレル・ヴォーリズ設計の大丸心斎橋店付近である。ただ大丸前の大通り「御堂筋」なのかといえば、ちょっと違う。銀座のような賑わいは1本東に入ったアーケード街「心斎橋筋商店街」である。


心斎橋筋商店街側大丸 御堂筋側大丸
東京にも有名なアーケード商店街はある。浅草新仲見世商店街、武蔵小山商店街パルム、蒲田西口商店街、JAGAT本社にも近い、中野サンモール商店街、十条銀座商店街、ハッピーロード大山などなど。しかしいずれも大阪の規模には及ばないことと立地場所がまったく違うことである。JAGAT西部支社に近い、天神橋筋商店街は長さが約3キロ近くもあり、日本一とも言われている。これらの商店街には古い店も多く、創業100年も珍しくないという。そういえば昔ながらの喫茶店が多いのも錯覚ではないように思う。
一方、大阪には「地下商店街」が多いのも大きな特徴である。東京は地形、地質、地震のせいかどうかは分からないが、八重洲地下街以外自慢できる地下街はない。
地下街の報告は次回に譲ることにして話を商店街に戻すと、これら商店街情報あるいは地域情報の発信を担っているのがフリーペーパーであろう。大阪でどれぐらいのフリーペーパー・フリーマガジンがでているのかははっきりした統計はないようだ。日本生活情報紙協会が調査したところでは、71誌(紙)、約300万部といわれている。東京では、344誌(紙)、約1430万部と発表されている。単純に人口を比較すると大阪府は東京都の約70%(1300万に対し883万人)であるが、フリーペーパーでは東京の21%でしかない。人口の割にはフリーペーパーの種類も部数も少ないような気がする。そこで少し統計が古いが、昼間人口の違いを見ると、大阪市は東京23区の約32%(東京1128万人に対して大阪358万人)でしかないことが分かる(2005年国勢調査)。常住人口との差をみると、東京が約300万人、大阪は約100万人で昼間と夜間人口差の対比は3対1である。この差が生活密着とはちょっとコンセプトの違う「職場(オフィス)、OL、学生」を対象としたフリーペーパーが東京では多いことが設置場所や配布形式などから容易に想像がつく。大阪ではその規模が小さいことが発行の種類、部数の差になっているのだろうか。もちろん、全国ブランドで有名なフリーペーパー(リクルート、サンケイリビング)や百貨店、JR・私鉄会社、ガス・電力会社などの大企業による広報誌、PR誌型のフリーペーパーは東京と同じように発行されている。
一方、これだけ商店街が多い大阪で商店街と連動したフリーペーパー・マガジンはどうなのだろうか。大きな商店街ではいろいろなフリーペーパー・マガジンを散見するがなかなか維持・継続では苦労しているようだ。このあたりはもっとウオッチしていきたいと思う。従来の商店街の良さを残しながらも、未来の商業施設として発展させるには、IT化、メディア化、安心・安全といったことを推進する必要があろう。印刷会社としての社会的役割がありそうな気がする。
大阪市内を中心にした昼間人口を狙った女性向けフリーペーパーは大阪でも人気があるようだ。「オンリーワンの自分に誇りを持ち、毎日を自分らしく素敵に楽しむ女性を応援する」をコンセプトに15万部を発行する『Pretty』(大新社)、20代後半~30代のOLを対称にした『PLUS Lumino』も同じ15万を発行。比較的金銭的にも時間的にも余裕のある購買意欲の高い読者ターゲットに対し、クオリティの高い誌面と読み応えのあるコンテンツを提供することを方針としている。
割引・特典で訴求するクーポン型マガジンである「HOT PEPPER」(リクルート)などと一線を画するには、商品の魅力と価値を伝える情報で勝負をすることが重要だとシティライフの副編集の尾浴芳久氏は話す。
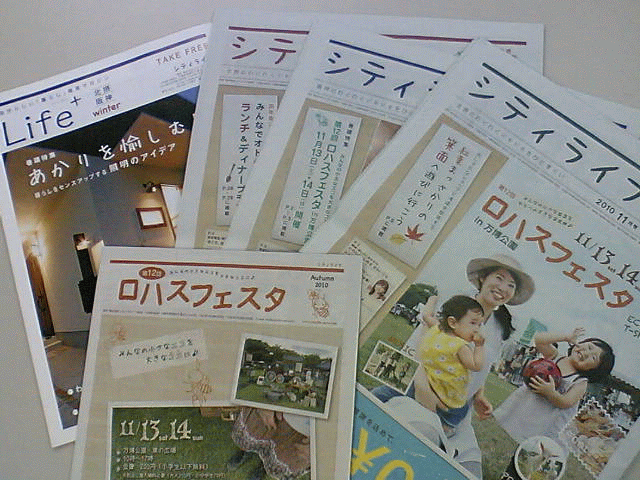
シティライフ((株)シティライフNEW)は郊外住宅密着型の典型的なフリーペーパーで、24年前に高槻市、茨木市の北摂東地区を皮切りに吹田市、箕面市、池田市、豊中市の北摂西地区、宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市東灘区の阪神地区をエリアに合計60万部を発行し、90%を戸別ポスティングしている。ショッピングセンターやスーパーにも置いているが、戸別配布にこだわっているのは、地域の一人ひとりとの結びつきがなければ存在価値はないと考えているからだ。ネット化にも意欲的で、地域のポータルサイトになるために住民読者のブログ発信基地を目指している。ただ基本メディアを印刷と位置づけ印刷を中心にメディアを連携したいと考えている。印刷メディアとしてのシティライフは「新しい出会い場」であり、Webサイトやイベントを支える「ブランドメディア」であるという。ブランドとは「信頼」であり、信頼のためにはそれぞれのエリアに肌理の細かい取材、情報発信が必要で、それを実現するのが「編集者の人間力」であると考えている。この力はネットでも活かさされるという。かつて編集者は誌面の黒子であったが、どういう人が、どのようにして、情報を発信しているのか、読者一人ひとりとコミュニケーションをすることで、編集を通じてもっと深いメディアとしてのブランドを獲得できるという。同氏はいままでの携帯電話をスマートフォンタイプに替え、今Twitterでつぶやき続け、印刷メディアでも積極的に署名記事にして登場しているという。地域密着のフリーペーパーを作るには、作り手自身が地域密着でなければ「ブランド」作りはできないということだ。ネットで発信すれば何とかなるというのは幻想で、多様なメディアとコンテンツがあってこそできることがあり、地域密着だからこそできることがある、というのがシティライフの企業理念である。
とはいっても広告モデルの上に成り立っているのが現実で、広告減は継続を厳しくすることは明白である。これまでの「ブランド」と「コンテンツ」を活かしながら地域のコミュニケーションツールとしていかに深く入り込むかが大事であるという。新事業としてメディアの公共性を活かしたロハスフェスタを大阪万博公園で4年前からスタート。年間に6万人を動員するまでになった。これを東京にも広げようと練馬・光が丘公園で今年初めて開催された。自分らしい生き方をキーワードにコンサートやロハスカフェ、セミナー、交流会など多彩な展開をしている。
東京にも有名なアーケード商店街はある。浅草新仲見世商店街、武蔵小山商店街パルム、蒲田西口商店街、JAGAT本社にも近い、中野サンモール商店街、十条銀座商店街、ハッピーロード大山などなど。しかしいずれも大阪の規模には及ばないことと立地場所がまったく違うことである。JAGAT西部支社に近い、天神橋筋商店街は長さが約3キロ近くもあり、日本一とも言われている。これらの商店街には古い店も多く、創業100年も珍しくないという。そういえば昔ながらの喫茶店が多いのも錯覚ではないように思う。
一方、大阪には「地下商店街」が多いのも大きな特徴である。東京は地形、地質、地震のせいかどうかは分からないが、八重洲地下街以外自慢できる地下街はない。
地下街の報告は次回に譲ることにして話を商店街に戻すと、これら商店街情報あるいは地域情報の発信を担っているのがフリーペーパーであろう。大阪でどれぐらいのフリーペーパー・フリーマガジンがでているのかははっきりした統計はないようだ。日本生活情報紙協会が調査したところでは、71誌(紙)、約300万部といわれている。東京では、344誌(紙)、約1430万部と発表されている。単純に人口を比較すると大阪府は東京都の約70%(1300万に対し883万人)であるが、フリーペーパーでは東京の21%でしかない。人口の割にはフリーペーパーの種類も部数も少ないような気がする。そこで少し統計が古いが、昼間人口の違いを見ると、大阪市は東京23区の約32%(東京1128万人に対して大阪358万人)でしかないことが分かる(2005年国勢調査)。常住人口との差をみると、東京が約300万人、大阪は約100万人で昼間と夜間人口差の対比は3対1である。この差が生活密着とはちょっとコンセプトの違う「職場(オフィス)、OL、学生」を対象としたフリーペーパーが東京では多いことが設置場所や配布形式などから容易に想像がつく。大阪ではその規模が小さいことが発行の種類、部数の差になっているのだろうか。もちろん、全国ブランドで有名なフリーペーパー(リクルート、サンケイリビング)や百貨店、JR・私鉄会社、ガス・電力会社などの大企業による広報誌、PR誌型のフリーペーパーは東京と同じように発行されている。
一方、これだけ商店街が多い大阪で商店街と連動したフリーペーパー・マガジンはどうなのだろうか。大きな商店街ではいろいろなフリーペーパー・マガジンを散見するがなかなか維持・継続では苦労しているようだ。このあたりはもっとウオッチしていきたいと思う。従来の商店街の良さを残しながらも、未来の商業施設として発展させるには、IT化、メディア化、安心・安全といったことを推進する必要があろう。印刷会社としての社会的役割がありそうな気がする。
大阪市内を中心にした昼間人口を狙った女性向けフリーペーパーは大阪でも人気があるようだ。「オンリーワンの自分に誇りを持ち、毎日を自分らしく素敵に楽しむ女性を応援する」をコンセプトに15万部を発行する『Pretty』(大新社)、20代後半~30代のOLを対称にした『PLUS Lumino』も同じ15万を発行。比較的金銭的にも時間的にも余裕のある購買意欲の高い読者ターゲットに対し、クオリティの高い誌面と読み応えのあるコンテンツを提供することを方針としている。
割引・特典で訴求するクーポン型マガジンである「HOT PEPPER」(リクルート)などと一線を画するには、商品の魅力と価値を伝える情報で勝負をすることが重要だとシティライフの副編集の尾浴芳久氏は話す。
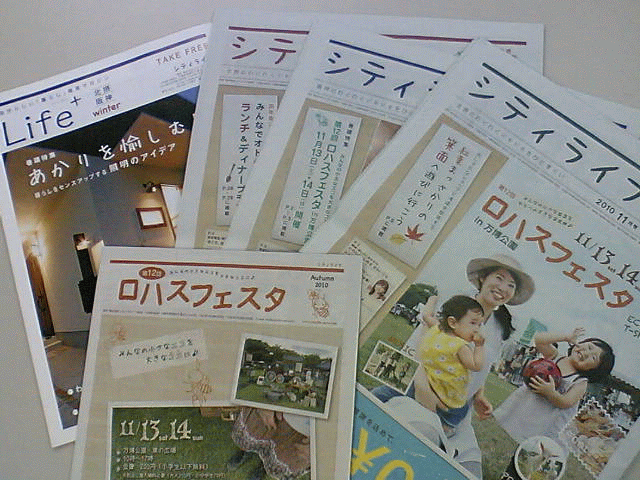
シティライフ((株)シティライフNEW)は郊外住宅密着型の典型的なフリーペーパーで、24年前に高槻市、茨木市の北摂東地区を皮切りに吹田市、箕面市、池田市、豊中市の北摂西地区、宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市東灘区の阪神地区をエリアに合計60万部を発行し、90%を戸別ポスティングしている。ショッピングセンターやスーパーにも置いているが、戸別配布にこだわっているのは、地域の一人ひとりとの結びつきがなければ存在価値はないと考えているからだ。ネット化にも意欲的で、地域のポータルサイトになるために住民読者のブログ発信基地を目指している。ただ基本メディアを印刷と位置づけ印刷を中心にメディアを連携したいと考えている。印刷メディアとしてのシティライフは「新しい出会い場」であり、Webサイトやイベントを支える「ブランドメディア」であるという。ブランドとは「信頼」であり、信頼のためにはそれぞれのエリアに肌理の細かい取材、情報発信が必要で、それを実現するのが「編集者の人間力」であると考えている。この力はネットでも活かさされるという。かつて編集者は誌面の黒子であったが、どういう人が、どのようにして、情報を発信しているのか、読者一人ひとりとコミュニケーションをすることで、編集を通じてもっと深いメディアとしてのブランドを獲得できるという。同氏はいままでの携帯電話をスマートフォンタイプに替え、今Twitterでつぶやき続け、印刷メディアでも積極的に署名記事にして登場しているという。地域密着のフリーペーパーを作るには、作り手自身が地域密着でなければ「ブランド」作りはできないということだ。ネットで発信すれば何とかなるというのは幻想で、多様なメディアとコンテンツがあってこそできることがあり、地域密着だからこそできることがある、というのがシティライフの企業理念である。
とはいっても広告モデルの上に成り立っているのが現実で、広告減は継続を厳しくすることは明白である。これまでの「ブランド」と「コンテンツ」を活かしながら地域のコミュニケーションツールとしていかに深く入り込むかが大事であるという。新事業としてメディアの公共性を活かしたロハスフェスタを大阪万博公園で4年前からスタート。年間に6万人を動員するまでになった。これを東京にも広げようと練馬・光が丘公園で今年初めて開催された。自分らしい生き方をキーワードにコンサートやロハスカフェ、セミナー、交流会など多彩な展開をしている。
(西部支社:杉山慶廣)
(C) Japan Association of Graphic Arts Technology
