本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
組織力を生み、紡ぐために 「経営シンポジウム2010」開催報告
課題解決の具体的な方法はそれぞれの企業ごとに異なるが、そのすべての原動力となるのは、最終的な基盤としての「人材」にたどり着くと思われる。人が動いてこその組織である。「人を活かす組織、人が活きる組織を作る」、その道筋を示すことが結果的には、収益向上への最短距離ではないだろうか。
2010年11月19日(金)、内幸町ホール(東京・千代田区)にて2年振りとなる「経営シンポジウム2010」を開催し、前回よりも多い約80名の方にご参加いただいた。
過去には、「企業風土改革」「人材マネジメント」「サービス経営」「働きがいのある会社」をテーマにしたが、今回は「やる気を引き出す「組織力」」をテーマに印刷会社の経営戦略を検討していった。
● 基調講演「組織力―― 宿し、紡ぎ、磨き、繋ぐ」 
東京大学大学院経済学研究科の高橋伸夫教授の専門は、経営学、経営組織論、意思決定論、統計調査論である。
最初から「組織で仕事をする」わけではない。仕事を共にすることで、だんだんと組織らしくなってくる。経営やマネジメントの本質とは、一人ひとりではできないような大きな仕事をみんなでこなす。あるいは、一人ひとりでは突破できないような難関をみんなでなんとか切り抜ける。それが多分、普通に考えたところの「組織力」である。
このチーム、この組織、あるいはこの会社なら、このくらいの大きさの仕事ならこなせる。あるいは、このくらいの難関だったら何とか切り抜けられるというイメージである。そのイメージと感覚を、経営者や中間管理職といった組織のリーダーも、個々のメンバーも、共有しなければいけない。
必要なのは「仕事ができる人」ではなく、「仕事を任せられる人」である。仕事ができる人は、よそから持ってくることができるが、仕事を任せられる人は中で育ていくしかない。それには時間がかかるのである。仕事を任せられる人をいかに作るかというのが、実は重要であり、実務経験を積ませるのは大人の責任である。
一番シンプルでまともな評価は、「また君と一緒に仕事がしたい」である。例えば、一度仕事を一緒にしたことがあって、「もう二度とあんなやつと組みたくない」という評価なのか、まだ一度も仕事を組んだことはないが「あの部長の下で働けるなら手弁当でもいい」と思うことがあるとか、そういう評価が本当の評価である。
若者に必要なのは、自分が成長しているという手応え、仕事の達成感である。仕事のおもしろさに目覚めた人間だけが、本当の意味で一生懸命働くからである。彼らが会社の未来である。若者に仕事のおもしろさを教えてやってほしい。皆さんと一緒に働くことの楽しさを教えてやってほしい。
●ディスカッション「やる気を引き出す組織のあり方」
高橋教授をモデレータに、スピーカーに株式会社ウエマツの福田浩志社長と株式会社ディグの杉井康之社長を迎え、組織力アップとリーダーシップ、モチベーション維持について両社の取り組みを伺った。二人の経営者は他業界しかも大手企業(メリルリンチ、東京電力)の出身で、2003年より印刷会社の経営に携わっている。はじめは大手の社内モチベーションシステムと印刷会社の実態の相違に戸惑うこともあったようだ。
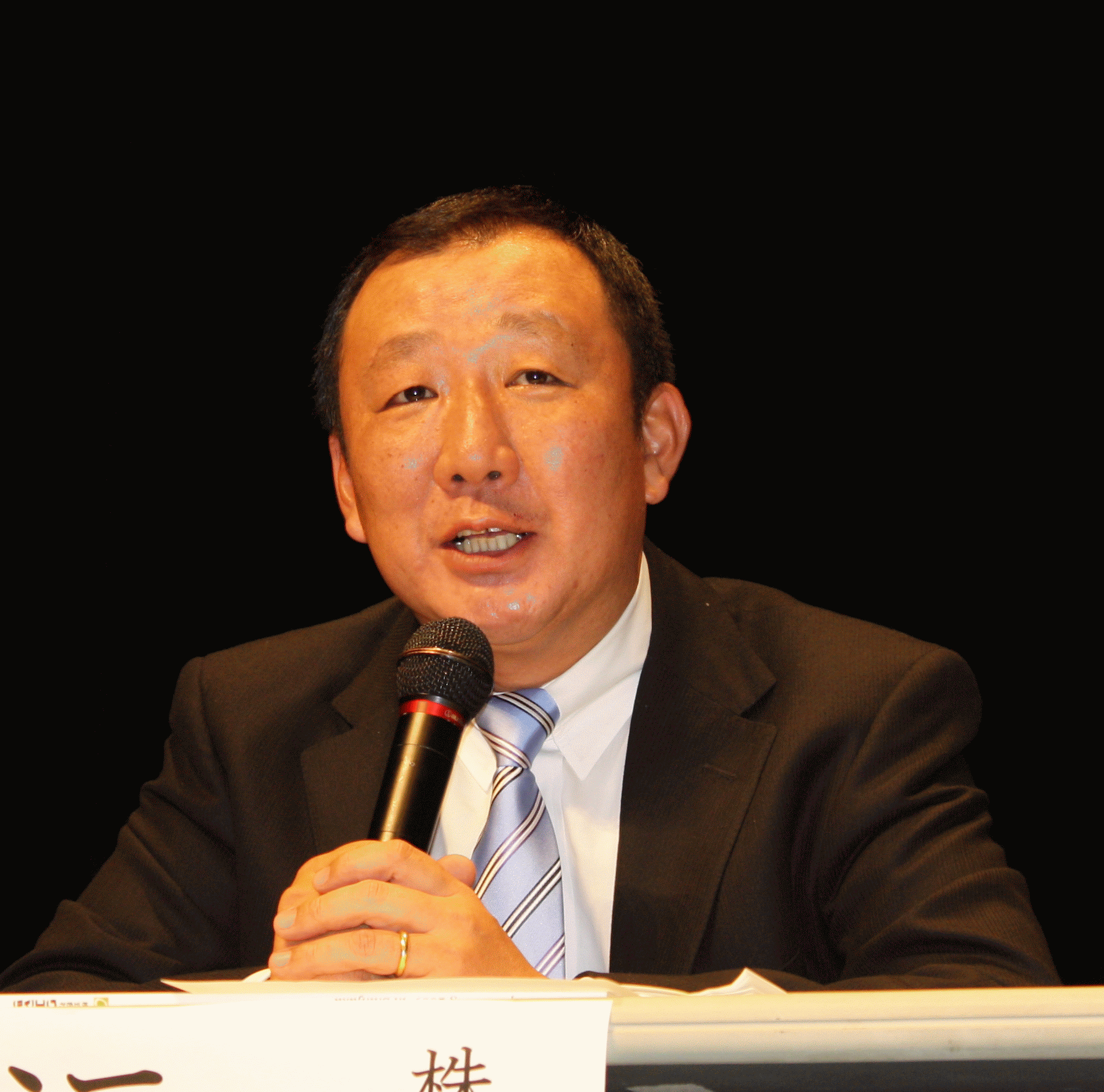 ウエマツの福田社長は、自社の独自のポジション――印刷受託製造会社に特化したビジネスモデルを推進し、日本最大の印刷ファンドリー会社を目指している。その上で自社の組織力アップの事例として、「5つの行動指針」「リーダーシップ研修」など具体的な取り組みについて説明があった。
ウエマツの福田社長は、自社の独自のポジション――印刷受託製造会社に特化したビジネスモデルを推進し、日本最大の印刷ファンドリー会社を目指している。その上で自社の組織力アップの事例として、「5つの行動指針」「リーダーシップ研修」など具体的な取り組みについて説明があった。
まずは、「5つの行動指針」(顧客重視=品質重視、相互の尊敬、チームワーク、変革への挑戦、学習する組織)を社内で浸透させることで、社員の意識を高めることからはじめた。
「リーダーシップ研修」は、社長から参加者に招待状を送るもので、毎年1回、泊まりがけで開催する。この研修は、一定の勤務年数を迎えたときに受けるものでも、社員全員が参加できるものでもない。ましてや社員旅行でもない。日頃の仕事に対する努力やリーダーシップを会社に認められた人が、そのリーダーシップスキルをさらに磨くために参加できるもの。それだけに各自の自信にもつながり、研修への意欲も高まるという。
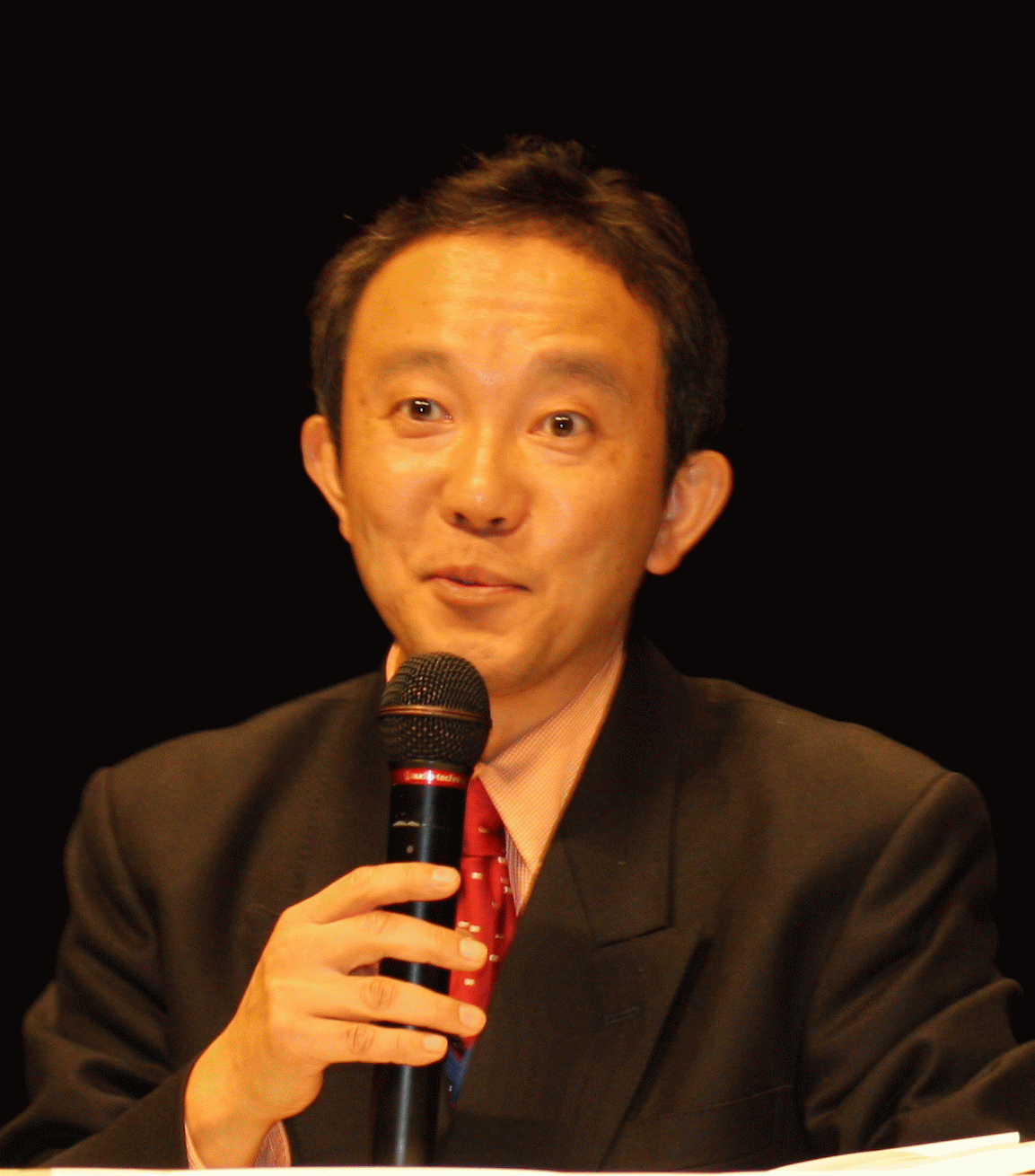 ディグの杉井社長は、ITを社内に浸透させ、かつ環境問題に力をいれ、「環境のディグ」というブランドの確立を目指している。杉井社長自ら社内のシステム化を推進して、ITによる業務改革に取り組んでいる。初めのころは、タイムカードからパソコンによる出勤簿に切り替えるだけでも戸惑いがあったようだが、社内の事情を熟知した上で作られたシステムであることが理解させてきた。
ディグの杉井社長は、ITを社内に浸透させ、かつ環境問題に力をいれ、「環境のディグ」というブランドの確立を目指している。杉井社長自ら社内のシステム化を推進して、ITによる業務改革に取り組んでいる。初めのころは、タイムカードからパソコンによる出勤簿に切り替えるだけでも戸惑いがあったようだが、社内の事情を熟知した上で作られたシステムであることが理解させてきた。
「仕事を任せられる人」ということでは、新設のソリューション事業部の責任者に、長年パート職員として働いていた女性を正職員にして部長に抜擢した。年功序列でもなければ、成果主義でもない、仕事の内容をよくわかっている、つまり「仕事を任せられる人」として登用した。さらに、インターンシップ制の導入で、優秀な新卒者の戦略的な採用の道筋もできている。
