本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
たくさんの出来事と大きな潮流
掲載日: 2010年12月30日
「われわれはたまたま、輝き渡る新星に幻惑されがちであるが、むしろ大きな潮流の行方をこそ静かに虚心に見守るべきである」(故・馬渡力氏:元JAGAT副会長)今年は、電子書籍で明け、電子書籍で暮れた感じの1年であった。『電子出版の構図』の著者・植村八潮氏の言葉を借りれば、"電子書籍を題材にした電子書籍「本」のブームであり、電子書籍「セミナー・講演会」ブームであった"というのが実態であろう。年末にきて東京では三省堂書店(神田神保町店)の「エスプレッソ・ブック・マシーン」のサービスが開始(12月15日)された。一方、大阪では書店大手のジュンク堂書店と丸善が12月22日に売り場面積日本最大とのふれ込みで「MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店」(写真)がオープンさせた。ベストセラーや芥川賞といった本自体の話題とは違い、本を巡る産業界そのものが1年を通じでニュースになったのは珍しいといえよう。出版界のみならず、書店、流通、新聞、印刷、作家、コンビニ、通信会社、広告代理店、そして読者も含めてこれだけ関心が高くなったことは過去にはないだろう。この事象自体をもって「電子書籍元年」とするのかどうかは、2011年が2年目としてのステップを踏めるかどうかである。どちらにしても印刷メディアを取り巻くビジネス環境の厳しさは変わりがない。
「MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店」は丸善とジュンク堂が共同ブランドで出す店で、東京、広島に次いで3店目とのこと。「ない本はないと言われる、電子書籍より楽しい本屋にしたい」というのがコンセプト。しかし単に大書店というだけでは、楽しいスタイルは提供できないであろう。電子書籍の登場や携帯配信、あるいは同じ本であってもアマゾンのようなネット販売など新たな本の環境が従来とは違う読書スタイル、制作スタイルを生み、新たな本の可能性を掘り起こすことができるとすれば、それこそが本質的なpublishingの時代、つまり英語のpublic と語源を共有するpublishingが誕生する。わが国の狭義としての出版のスタイルとは違った広がりを持つビジネスができるのではないだろうか。新たなスタイルと従来のスタイルが互いに切磋琢磨しながら、ハイブリッドで読者サービスの向上や便利さが充実すれば歓迎されるであろう。ただ、着地点はその通りであっても、そのプロセスで起こる大きな構造の変化に対応せねばならない。生き残るには環境変化に応じて進化しなければならない。
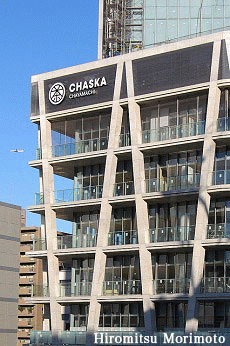
先日、業界とはまったく関係のないセミナーで、産業構造の変革の好事例として「出版・印刷業」が講演の俎上に登った。思いもよらない展開に苦笑しつつも事例は明快であった。
出版産業(関連業種を含め)は、『印刷技術』によってすべてが構築された産業であること。
本の制作・流通・販売すべてが印刷という技法、時間、加工・形状に規定されているということである。業界人にとってそんなこと当たり前すぎる話であるが、講師は印刷技術を出版産業から抜いてしまうとどういうことになるか。情報の記録・伝達、つまりコミュニケーションの大革命を想定しなければならないことを解説。改めて印刷メディアの果たしてきた大きさを感じた。
さて、もう一つの話題、東京の三省堂神田神保町店(写真)の店内に置かれた印刷・製本機(Espresso Book Machine・本文印刷はXerox 4115でモノクロ刷り、表紙はEPSONのインクジェットプリンタでカラー印刷)で始ったブックオンデマンドサービス。当面は「絶版本」や「著作権フリー本」が中心となるようだが、今後どのような存在になるのだろうか。一時の話題として終息するのか。新たなビジネスとして波紋を広げていくのか、具体的な形はまだ見えない。しかし、書店の店頭で読者の目前で10分足らずで本ができという事実、そして「本」というモノが流通するのでなく、「データ」が流通するという事実。この事実は電子書籍とも従来の本とも違うということだけは頭の隅において置く必要があろう。

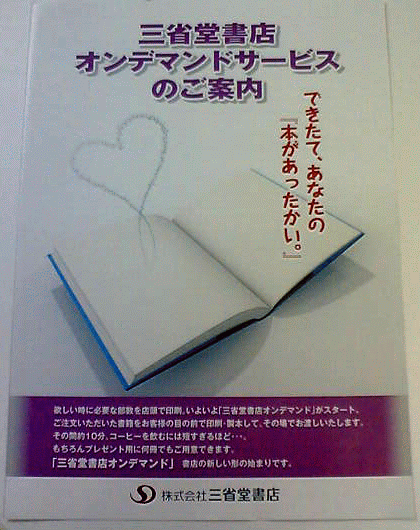
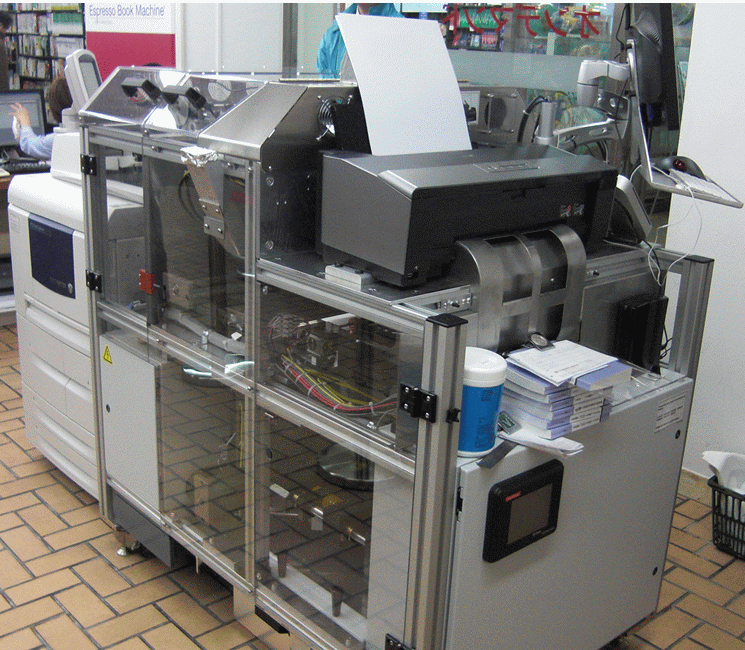
三省堂神田神保町店 Espresso Book Machine
いずれにしてもメディアの歴史的な転換期の中で印刷の仕事に携われる誇りと怖さを真摯に受け止めたい。
以前JAGATの副会長をされた故馬渡力氏は57年前の1953年にまとめた海外印刷技術動向の報告書の一部で、「萌芽としての無圧印刷」と題し、印刷の根本理論を改革するものに「無圧印刷」があることに触れておかねばならないと今日のデジタル印刷の予測をしている。インキジェット方式などの研究はかなり古くからあったことは聞いていたが、57年前の報告の中で注目していることに驚愕した。
『一つの大きな潮流というものは、とうとうとして不断にその目指す方向に流れている。われわれはたまたま、輝き渡る新星に幻惑されがちであるが、むしろ大きな潮流の行方をこそ静かに虚心に見守るべきである』という冒頭の言葉を改めて噛みしめたい。(西部支社:杉山慶廣)
(C) Japan Association of Graphic Arts Technology
