本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
森裕司のInDesign未来塾 -8-
掲載日: 2011年04月30日
InDesignが扱うカラーについて考える
アプリケーションのカラー設定はBridgeから統一する
今回は、InDesignのカラーについてのあれこれを考察してみたい。まずは「カラー設定」。アプリケーションごとに「カラー設定」ダイアログから設定が出来るが、使用するAdobeアプリケーションのカラー設定はすべて同じにしておかないと、色の見え方が違ってしまうので統一する必要がある。しかし、アプリケーションごとに設定していては手間も掛かるし、設定を間違うことも考えられる。
そこでAdobe Bridgeから設定することをお薦めしたい。「Suiteのカラー設定」ダイアログによって、InDesignのみならず、PhotoshopやIllustratorのカラー設定も一気に同じ設定に同期することが出来る。仕事内容によってカラー設定を変更する場合でも、Bridgeから行えば間違いがないというわけだ。
なお、本来であれば印刷会社の印刷機に合わせたプロファイルを指定するのがベストだが、プロファイルを配布している印刷会社は少ない。そのため、一般的なコート紙への印刷であれば、「Japan Color 2001 Coated」がCMYKのプロファイルとして推奨されている。個人的には自社のプロファイルをユーザーに配布する印刷会社が、もっともっと出てきて欲しいなと感じている。
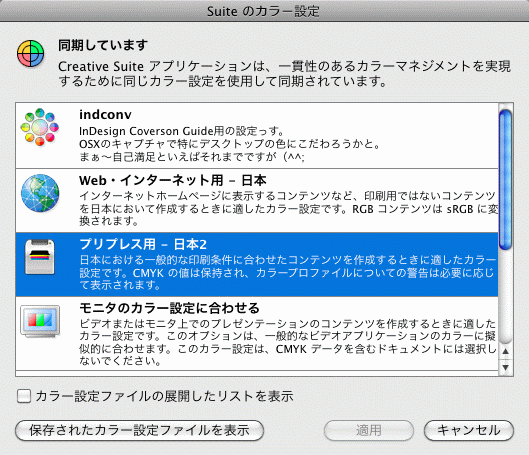
特色に強いInDesign
特色の扱いもなかなか難しい問題のひとつではないだろうか。CMYKにプラスして特色を使用するケースもあるが、特に多いのが2色刷りで特色を使用するケースだろう。その場合、任意の特色2色、あるいは墨と特色を使用してデータを制作する。しかし、特色を使用してデータ制作するのではなく、その多くはCMYKのうちの任意の2版で作業をして、印刷時に指定した特色で刷ってもらうというケースが多いのではないだろうか。これは、Illustratorでは特色の掛け合わせが出来ないためだ。オーバープリントや乗算の機能を駆使すれば特色を使用して作業することも可能だが、リスクもあるためあまりお薦め出来ない。
そこで、特色の仕事にはInDesignを使用して欲しい。実はInDesignでは特色の掛け合わせカラーが使用出来るのだ。これを混合インキと呼ぶ。例えば、DIC○○を30%、DIC□□を60%といった形で特色を掛け合わせた混合インキが作成出来る。仕上がりイメージに近いカラーでプリント出来るだけでなく、そのまま特色版として出力も可能だ。
また、複数の掛け合わせカラーを一括して作成する「混合インキグループ」という機能も用意されている。掛け合わせたい複数のカラー(特色を1色以上含んでいる必要あり)を指定し、何%単位で掛け合わせるかを指定すれば、一気に複数の混合インキが作成される。更には、クライアントから特色を変更して欲しいといった要望があった場合でも、混合インキとして使用したベースの特色を変更すれば、その特色を使用した混合インキすべてが一気に変更されるので、修正にも素早く対応出来る。ぜひ使って欲しい機能のひとつだ。筆者は、ペラものを制作する場合でも、特色を使用する仕事にはInDesignを使用するようにしている。
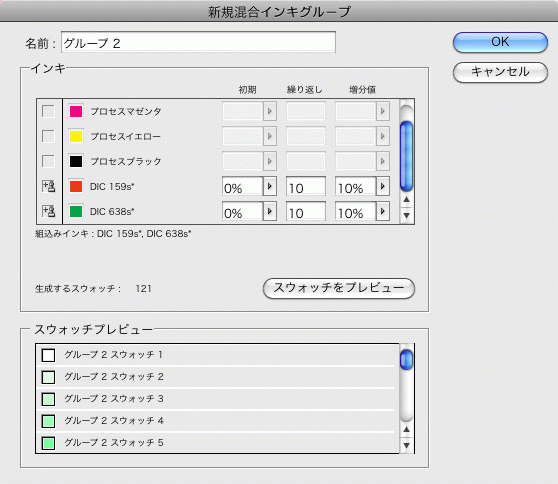
これからはRGBワークフロー?
印刷物制作を目的とした場合、カラーモードはCMYKで作業していることと思う。CMYKのインキで刷るので当たり前だったわけだが、今後は徐々にRGBベースのワークフローに切り替わっていくと思われる。理由は色々あるが、ウェブやデジタルカメラを始め、今後必須とも言うべき電子書籍がRGBベースで運用されていることが大きな理由として挙げられる。例えば、EPUBやAdobe Digital Publishing Suiteなど、InDesignで印刷用に制作したデータ(CMYK)をデジタルデバイス向けに書き出すと、自動的にRGBに変換されて書き出される。
しかし、皆さんご存じのようにCMYKよりもRGBの方が色域が広いため、最終ターゲットがRGBならば、最初からRGBで運用した方が素材本来の色を損なうことなく運用出来るのでベストなはずだ。色のことを考えれば、CMYKからわざわざRGBに戻す必要はない。であれば、最初からRGBで作業する方がメリットが大きいのではないだろうか。
「RGBで運用すると、CMYKで出力した場合に色の問題が出るのでは?」と思われる方もいると思うが、実はRGBで画像を運用しても、きちんとしたワークフローを組むことで現在では問題ない状況になっている。例えば、毎日コミュニケーションズの『+DESIGNING』誌は数年前からRGBワークフローで制作されている。InDesignドキュメントにはRGB画像を配置して制作を行い、PDF/X-4を書き出す。書き出したPDFをAcrobat用のプラグインであるColorgenius ACで、各画像に対してCMYKへの補正パラメーターをレシピファイルとして付加するのだ。元画像には最終段階まで手を加えず、どのようにCMYKに変換するのかを確認しているというわけだ。そうすることで、出来るだけ手間の掛かる色校正をなくし、印刷までのスケジュール短縮にも成功している。また、デジタルマガジンなどに展開する場合でも、RGBのまま作業出来るため、画像本来のカラーを生かせるわけだ。
画像をRGBで運用すれば、RGBとCMYKの2つの画像を使い分ける必要もなく、Photoshopでの補正やファイルサイズを減らすといった意味でもメリットがある。富士ゼロックスからもAdobe PDF Print Engine 2.5が搭載されたプリンターが発売され、今後ますますPDFの運用も広がっていくはずだ。自社のワークフローを効率化するためにも、ぜひRGBワークフローに取り組んでいただきたいと思う。
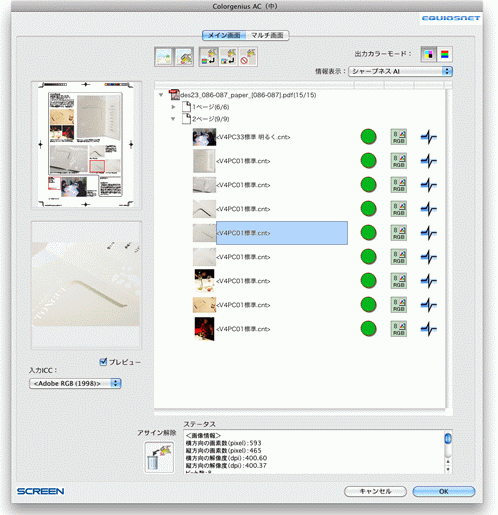
(2011年3月号 プリバリ印より)
(C) Japan Association of Graphic Arts Technology
