本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
DTPエキスパートのための注目キーワード -9-
試験のキーワードをワンポイント解説 第9回 光源と色の見え方(LED光源)
印刷物の評価では、標準光源が重要であることは言うまでもない。その光源の特徴を示すものに分光特性がある。今回は、その光源の特徴を示す分光特性の考え方と、最近、話題になるLED光源について取り上げる。
■分光特性とは?
光源には、いろいろな色がある。その光源から放射されている光を波長ごとに測定(分光)し、その光のエネルギーの割合を表したものを分光分布(分光特性)という。分光特性図は次ページの問題文の中にもあるように横軸に波長域(nm)、縦軸にその波長域の比エネルギーの値をとり、その中に表される曲線の分布(エネルギーの分布)によってどんな波長域の色を持っているのか、ピークの形状にどのようになっているのかなどが表される。全波長域に大きな偏りがなくエネルギーの分布があるものが太陽光であり、その光源の演色性が高いものとなる。
分光特性によって照明の色彩特性が決まり、その色彩特性には色温度と演色性がある(図1参照)。照明光の分光特性としては、エネルギーの過不足がなく、分光エネルギー分布がフラットなものが望ましい。照明光の分光特性が異なると、同じ印刷物でも色の見えが変わってしまう。印刷物の評価で使う標準光は、D50があり、その色温度は5000Kであり、高演色性の昼光用の蛍光ランプがよく用いられる。
■LED光源ってどんな光源?
LED(Light:光る、Emitting:出す、Diode:ダイオード)は、発光ダイオードのことで、発光原理はエレクトロルミネセンス効果(順方向の電圧をかけ、LED内を電子と正孔が移動し電流が流れ、移動の途中で電子と正孔がぶつかると結合し、その際の電子と正孔のエネルギー差が光のエネルギーに変換される原理)を利用している。
LEDの寿命は白熱電球に比べてかなり長いが、省エネの点から見ると、発光効率は白熱電球より優っているが蛍光灯までには至っていない。 発光の色は用いる材料によって異なり、使用するダイオードの材料を変えることにより赤外線領域から可視光域、紫外線領域で発光するものまでの様々な色のLEDを作ることができる。Ga(ガリウム)、N(窒素)、 In(インジウム)、Al(アルミニウム)、P(リン)など、半導体を構成する化合物によって、放出される光の波長が異なる(図2参照)。擬似白色LEDは現在の白色LEDの主流であり、一般に青黄色系擬似白色LEDと呼ばれている。視感度の高い波長である黄色に蛍光体と青色とを組み合わせることによって、視覚上明るい白色LEDを実現している。この他に光の三原色である赤色、緑色、青色のLEDをミックスして白色を得る方法がある。RGBの各LEDの光量を調節することで任意の色が得られるため、大型映像表示装置やカラー電光掲示板の発光素子として使用されるが照明用には適さない。照明として用いる場合、蛍光体方式はある程度幅のあるスペクトルであるのに対して3色LED方式は赤、緑、青の鋭い3つのピークであり、黄及びシアンのスペクトルは大きく欠落しているためである。3色LED方式の白色発光では光自体は白く見えても自然光(太陽光)の白色光とはほど遠いため、それで照らされた物の色合いは太陽光とは演色性が異なってくる。
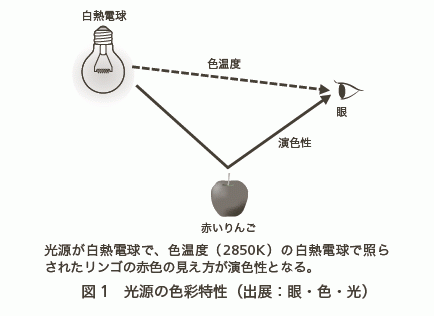
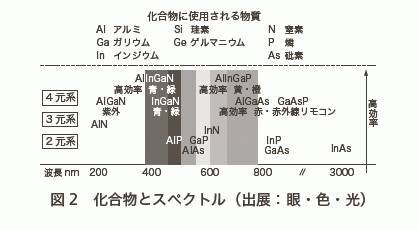
例題 光源とLED光源 C4(23期1-24)
次の文の[ ]の中の正しいものを選びなさい。
・分光特性Aは[1: ①LED ②白熱灯 ③昼光色蛍光灯 ④太陽光]であり、人にとって基準となる自然な見え方をする。
・分光特性Bは[2 : ①LED ②白熱灯 ③昼光色蛍光灯 ④太陽光]であり、長波長成分が少ないので、[3: ①赤がくすむ ②青がくすむ ③緑がくすむ ④色はほとんどわからない]。
・分光特性Cは[4 : ①LED ②白熱灯 ③昼光色蛍光灯 ④太陽光]であり、短波長成分が少ないので、[5: ①赤がくすむ ②青がくすむ ③緑がくすむ ④色はほとんどわからない]。
・分光特性Dは[6: ①LED ②白熱灯 ③昼光色蛍光灯 ④太陽光]であり、ほぼ一定の波長のエネルギーしか出ていない。
【分光特性】
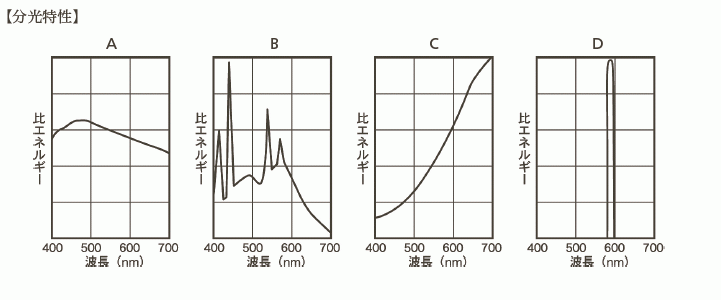
解答 1④ 2③ 3① 4② 5② 6①
問題文中の図では、Aは波長域の分布がなだらかで広範囲に分布している太陽光、Bは3波長にピークを持たせて演色性を高めて昼光色に近づけた蛍光灯、Cは長波長域が主に分布しているので白熱電球、Dは600nmのみにピークを持つ黄色に発色するLEDと推測される。
