本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
最近思うこと
最近、私は「製本講習」の講師として、公共図書館や社会教育施設に呼ばれる機会が増えてきました。多くの参加者から「先生」と呼ばれますが、一営業職なので、気恥ずかしい限りです。
私の勤め先である「タナカ」の主な事業内容は、①図書館用品の製造・販売、②新聞・雑誌の合冊製本、図書修理であります。主要な顧客は、公共図書館、学校、そして、地方自治体です。
今から10年以上前のこと。ある図書館の方から、「うちの図書館の職員に、簡単な本の修理方法を話して欲しい」という依頼を受けました。それを発端に近隣の図書館に口コミで広がり、講師の依頼が増えていきました。なかには司書の方だけでなく、図書館で活動しているボランティアさんを対象に講義をすることもあります。
最近は更にテーマが広がってきました。図書館や社会教育施設が、一般市民を対象に開催する「生涯学習講座…和綴本を作ってみよう」「小学生のための手づくり絵本教室」といった会場でも講師を務めるようになったのです。
最近、私が強く感じることは「なんと本好きの人が多いのか」ということです。
本の修理講座や手作り絵本講座に参加してくださる方々は増える一方です。参加者の方々からお聞きする本に対する思いは十人十色ですが、どなたの思いも深いのです。何より製本が進み始めると、明るい表情でイキイキと楽しんでおられます。講師役の私も楽しくなって、講義が終わる頃には心も軽く、にこやかになっています。
それにひきかえ……。
私たち印刷・製本業界は暗い話題が多く、業界人が集まると、まるで習慣のように悪い話ばかり交わしています。不況という重い空気にすっかり飲み込まれてしまったのでしょうか。
紙・インキからできた印刷物、また、その印刷物を裁ち・折り・綴じてできた本は、業界人から見れば「製品」ですが、手に取る人の立場に立てば「文化」です。いま、私たちは取引先とのやり取りにとらわれすぎて、本を手にとって読む人々のことを忘れていないでしょうか。
私たちは文化の一翼を担っているという誇りを持っているか、今こそ問い直さねばなりません。その誇りを過去のものにしないためにも、新しい技術の習得や勉強を怠ってはなりません。そして、社会の変化を見逃さず、新しい製品を生み出していかなければならないと思います。
さて、読者である業界の皆様に提案があります。
【業界を挙げて「社会見学」の誘致をしよう】
昨今は子どもだけでなく大人の間でも「社会見学」がブームです。バラエティ番組でも社会見学を切り口に、様々な工業製品ができ上がっていく様を追跡する企画も増えました。
印刷・製本業界では大手さんを中心に社会見学を受け入れておられますが、中小の会社もそれぞれの体力に応じたやり方で「社会見学」を受け入れ、技術をもっと知ってもらえる機会を作りませんか。
また、印刷機器や技術の見本市や展示会も、最終日は一般公開日にするなどしていただければ、私たちの業界を応援してくださる人も増えると思います。
小学校の社会見学で訪れた工場ではワクワクしたものでした。自動車、食品、電機等々、ものづくりの現場は、子どもながら驚きに包まれていました。私たち印刷・製本業界も、伝え方さえ間違わなければ、とても魅力ある分野だと思います。
当店の場合、小さな作業場のため、1クラス全部を受け入れる訳にもいかず、現在は講座という形で出向いてお話をさせていただいております。時間も割かれて面倒ですが、彼らの輝く目を見ていると、未来の担い手になってくれるのではないか、という期待をもっています。
【改めて奥付を大切にするキャンペーン】
活版からオフセットへと進化し、今ではオフセット印刷もプロセス抜きで刷版ができる時代となりました。私たち印刷、製本会社は、顧客からすれば、巨大なコピー機や自動製本機のような存在として認識されてしまっているかもしれません。入稿されたデータを指示された通り、そのまま作って納品する…という味気ない仕事が増えています。
しかし、実際には長年にわたって培ってきた技術とノウハウが生かされ、多くの人々が働いています。私たちが自信をもって作った製品に名前を残していきませんか。改めて冊子や本の奥付に「印刷○○・製本××」と名を入れることについて、お客様からの理解と協力を得ていきませんか。責任と誇りを明快に示し、この分野で働く人々のモチベーションを高めたいのです。
小学校二年生の息子がいます。彼が一年生のときの宿題に「自分の夢を書いてみましょう」というのがありました。彼は「こわれている本をなおすしごとをしたい」と書いていました。正直うれしいです。子どものことですから彼が大人になる頃には気持ちも変わっているかもしれません。でも先輩方が築いてくださった伝統は我々が少しでも発展させて後世に伝えていきたいものです。
田中稔(たなか・みのる)
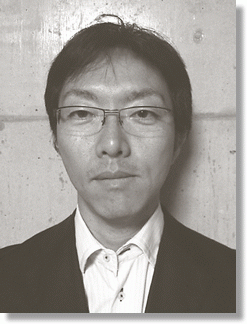
1972年岐阜市生まれ。朝日大学経営学部卒業。1995年よりタナカに勤務
会社概要
タナカ
〒501-2575
岐阜市太郎丸中島319-1
℡058-229-2627/Fax058-229-1416
1976年創業
業務内容 図書館用品の製造と販売
諸製本(逐次刊行物合冊製本・図書修理)
(JAGATinfo 2011.6月号より)
