本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
電子書籍アプリは制作した後がたいへん、売上げUPには施策が必須
コンテンツの質やクオリティはもちろんだが、数あるアプリの中で自社アプリのダウンロード数を増やすためには、広告やキャンペーンなどさまざまな施策が欠かせない。
JAGATクロスメディア研究会では、2011年9月2日(金)に「電子書籍アワード受賞社に聞くアプリ制作の実際[Xover Night #2] 」を開催しました。お話いただいたのは、ムームー 代表の森川さんと白石さん。
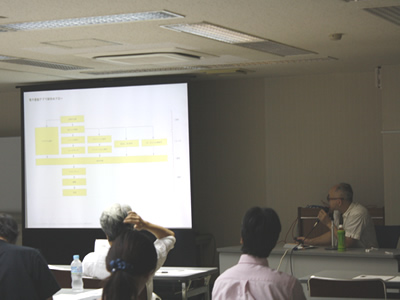
お話いただいたムームー 森川さん
今回は、「ヌカカの結婚」ほか3部作としてリリースした同社のiPhoneアプリを例に、電子書籍アプリをどのようにして販売していくかというお話をしていただきました。
42万分の1で勝負するのにランキング入りは必須!
iPhoneアプリは42万本以上もあり、ダウンロード数は150億を超える(2011年7月時点)という激戦地区。そのなかでアプリを販売するというのはハンパなく大変で、たとえば売り上げトップ10のランキングに入るためには有料版で1日5,000DL(ダウンロード)は必要なんだとか(電子書籍ジャンルでは1,300~1,500DLくらい)。
で、どうやってランキングに入るかというと、期間限定で値段を下げてみたり広告を打ってみたり、いろいろな施策を打ってDL数を稼ぐという仕組み。なかにはダウンロード数をお金で買ってしまう会社もあるようです。ランキングに入ることが売上げに大変影響するため、ここはどこも必死で取り組む部分のよう。

iPhoneアプリランキング(電子書籍)。ランキングに入ると飛躍的にDLが増える。
実際のアプリ売り上げ推移を見せてもらうと、売り上げトップ10に入る、iTunesStoreお気に入りに入る、115円に値下げキャンペーン、電子書籍大賞受賞、などトピックが発生するごとに売り上げが伸びているのがわかります。また「ヌカカの結婚」は3部作のため、シリーズの別タイトルが売れると連動してほかの2作も売上げが伸びたそうです。
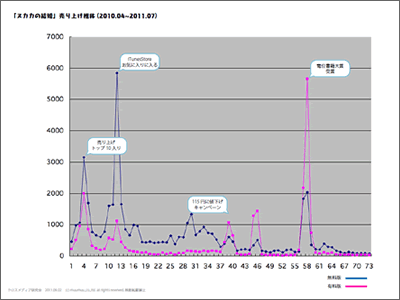
「ヌカカの結婚」ダウンロード数推移
開発はスピーディ、でも登録・審査に時間がかかることも
実務を担当されている白石さんからは、実際にApp Store へ登録するときに大変な点や気をつける点などについて紹介いただきました。まずアプリ販売をおこなうデベロッパーとして登録する必要がありますが、同社では1ヶ月弱かかったそうです。その後のアプリ提出後の審査でも1週間程度かかるほか、アプリを修正する都度再審査が必要で(また1週間くらいかかる)、制作以外で意外と時間がかかります。またAppleから差し戻されても詳細な理由は教えてもらえない場合もあるため、慣れるまではかなり手間がかかる作業ということです。
開発自体は、ひとつのアプリを2人で2・3ヶ月くらいで仕上げるくらいのペースで作業していくそうです。それくらいでないとコスト的にもスピード的にも間に合わないのだとか。
ほかにはApp Storeでは価格設定がマトリクス式になっており自由に価格設定ができなかったり、ドルベースなので為替レートの変動によってアプリの価格がある日突然115円から85円に変わったり(!)なんてこともあるなど、実際にやってみて戸惑ったことや大変に感じたことなどをお話いただきました。

白石さん。最新情報の入手手段として開発者ブログをチェックするとよいとのこと。
今回お話いただいて感じたことは、「電子書籍アプリを売るのって大変なんだなー」ということ。アプリを制作してストアに並べるのがスタート地点で、それをいかに売っていくかに根性を入れて取り組まないと電子書籍で収益をあげることは難しい、と。
研究会でも今後はいかに電子書籍ビジネスで収益をあげるかについて、取り組まれているところからお話をお伺いしたいと考えています。
(JAGATクロスメディア研究会 中狭)
関連セミナー
事例から探る電子書籍のビジネスチャンスと収益化【電子書籍ビジネス事例研究(1)】
2011年10月28日(金) 14:00-16:20(受付開始:13:30より)
出版社が低コストで参加しやすい制作システムを提供するブックパブ、新たな顧客層を開拓したハーレクイン、フリーペーパーに新たな価値を生み出した「ANA Virtual Airport」の事例を取り上げる。
