本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
千年級の作品が醸し出す オーラをプリントする
月刊『プリバリ印』2011年11月号の特集では、アートを広め、感覚を共有し、情緒を記録し、想いを伝える―― デジタルの時代にも決して輝きを失わない"印刷のアルス(技芸)"を紹介します。
コロタイプは版面にゼラチンを用いる平版印刷法で、連続階調による滑らかで深みのある表現が得られます。京都の便利堂は、単色だけだったコロタイプの多色刷り技術を開発し、数多くの国宝級絵画の複製を手掛けてきました。
プリバリインタビューでは、印刷のアルスを追究する、便利堂コロタイプ工房長の山本修さんに、コロタイプ技術の習得やそのエッセンスについて伺いました。

(インタビューより)
―― 入社してからは、どのようなかたちで仕事を覚えていかれたのでしょうか。
山本氏 現場をご覧いただければお分かりになると思うのですが、半世紀も前の機械をずっと使っていますし、製版でも手作業の部分が多いですから、高速の印刷機を回す一般の印刷会社さんの雰囲気とはまったく違うと思います。家内制手工業的な現場ですから、そこにいるのは職人さんばかりですよね。
私が入社した頃、コロタイプの現場ではしばらく新規採用をしていませんでしたので、先輩といっても私より20歳以上も年上の40代の方ばかりで、もう親子の関係ですよね。そういうなかで、朝早く来て機械の油を差してインキを練る。印刷助手といっても、要は丁稚仕事ですね。
コロタイプのインキは非常に硬いのです。粘度が非常に高く流動性がまったくないインキをヘラでひたすら練って、それでヘラを使うことを覚える。印刷機にインキ壺はありませんから、機械を動かしながら自分でインキを入れていきますが、ヘラが使えなければインキの充填もできないのです。
とにかく「油を差して手回しで動かして構造を覚えろ」、「職人を見て覚えろ」の繰り返しです。自動給紙ではなくて手差しですから、助手が紙を1枚ずつ手差しします。和紙をたくさん使いますから、紙の質、紙の癖を覚える。機械の下準備をしながら、紙を覚え、インキを覚え、ヘラを覚えていく。職人さんの仕事が終われば後片付けですが、ローラーの洗浄にしても、自動洗浄機などありませんから、手とウエスでザーッと洗う。そうやって、すべての手仕事を、一から十まで身体で覚えていくわけです。
仕事のやり方は職人さんによってそれぞれ違います。どんな仕事でもそうでしょうが、基本はありますが、みんな自分のかたちを持っておられるでしょ。コロタイプの職人さんでも、3人に尋ねると3人が違うことを答えます。まったく違うことをしているわけではないのですが、アプローチの仕方がそれぞれに違うのです。そういうなかで、自分に合うやり方を見つけて、自分のスタイルをつくっていくことが重要だと思います。
***
本誌では、山本さんに修行時代のお話やコロタイプの魅力など6ページにわたるインタビューを掲載しています。是非チェックください!
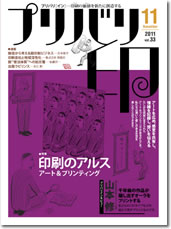
『プリバリ印』2011年11月号
特集: 印刷のアルス
アート&プリンティング
▼最新の情報はこちらからチェック▼
印刷物をつくる人・つかう人の虎の巻 『プリバリ印』
