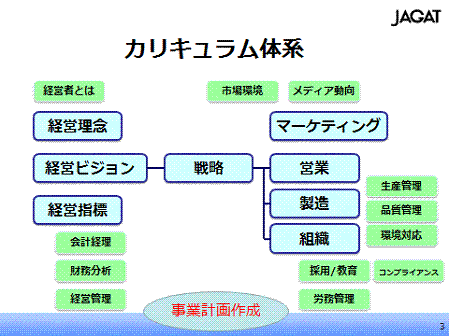本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
たしかな事業継承に向けて
厳しい現実を受け止めつつも自ら未来を切り開いていく後継者の育成は、自社のみならず業界の発展のためにも大きな意味を持つ。
統計数字の上では印刷業界は成熟期から衰退期を迎え、2020年の市場規模はさらに縮小するという予測数字もある。いままでと同じことを同じようにしていたのでは衰退は避けられない。厳しい環境下で勝ち残るためには「変化・変革」が不可欠である。変革を遂げた姿とは、一言で表すとメディア環境の変化に対応し新たな事業分野に挑戦するとともに、生産性向上を果たすということであろうか。言葉で表すのは簡単だが、実行・実現するのは容易いことではない。そこで求められるのが経営者のリーダーシップと“決断”である。市場での競争のみならず、自己の既成概念との戦いやときには、ついてこない社員との葛藤もあるだろう。厳しい現実を受け止めつつも自ら未来を切り開いていく後継者の育成は、自社のみならず業界の発展のためにも大きな意味を持つ。
JAGATが主催している「印刷後継者・経営幹部ゼミナール 」は今年、第30期を迎えるにあたり、急激な時代の変化に合わせカリキュラムの大幅改定を行った。一番のポイントとして、理論と(経営)実践と演習を3つの柱として設定した。
現役経営者が語る経営実践
実践とは現役経営者をお招きし、自らの体験と経営哲学を語っていただくことで、必ずしもセオリーどおりにはいかない現実にどのように“決断”し、どう対処したか、まさに“生”の声を聞く。「和の心を重んじた日本式M&A」を展開しているアサプリホールディングスの松岡社長からは、会社経営で最も重視しているという経営理念の共有とそれを軸とした経営管理の実践をお話しいただく。
大東印刷工業株の佐竹社長には、徹底した見える化(数値化)による経営管理をテーマにお話しいただく。具体的な数値を示さない限り、いくらコスト意識を持てと訴えても会社は変わらない。「社員全員に個人事業主意識を!」という佐竹氏の経営哲学と取組みを伺う。
シー・レップの北田社長は、家業の製本業の3代目にあたる。環境変化に強い危機意識を持ち、1990年の起業から今に至るまで、業態変革にチャレンジし続けている。「業態変革のための経営戦略の立案と実践」をテーマに受注産業としてのマーケティング視点を基軸に、いかに競合優位性を築くのか?また独自の社内制度や組織づくりなどのマネジメントの実践例をうかがう。
マルワの鳥原社長は、小学校、中学校教諭として8年間勤務したという経歴を持つ。設備重視から人材重視へ、自らの教育現場の経験を生かしたユニークな社員教育は他社からも大きな評価を得ている。企業が如何にやりがいを社員に提供できるか、また社員がいかに「主体的」に行動できるか、「絆」をキーワードに社員が主体的に動く仕組み作りについて伺う。
自社の事業計画書の策定
経済構造全体が成熟化するなかで事業計画の重要性が増している。成長期のような対前年比何%増という売上計画を漠然と立てているようでは経営をしているとはいえない。適切な事業計画を作成する事が事業の維持・発展に必須条件となりつつある。
演習として弊誌に「印刷業の事業計画」を連載中の印刷業界に特化したコンサルティング会社の(株)GIMSのバックアップのもとで、自社の事業計画書の策定に取り組む。
事業計画作成の必要性と意義、加えて作成に必要な経営環境の分析について講義で学ぶととともに、「経営課題」「経営戦略」「計画立案」について実習を進めてゆく。
以下のような策定プロセスを経る
①会社の5年後、10年後を考える(自社の事業ドメイン)
②あるべき姿になるための事業計画とは何か
③事業計画作成の前提条件(経営環境分析)
④事業計画の構成要素と作成プロセス
⑤事業計画作成後にすべき内容(モニタリング⇒課題の抽出により継続的革新へ)
体系的にセオリーを学ぶ
カリキュラムの全体像は下図のようになっている。営業戦略、財務分析、マーケティング、デジタルメディア・クロスメディアへの展開から労務管理に至るまで網羅されている。
これからの印刷会社経営に必須と思われるメニューをラインアップしたので、是非、ご活用いただき事業継承をたしかなものとしていただきたい。
(教育コンサルティング部 花房 賢)