本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
日本ではあまり知られていない大型枚葉印刷機の概要
欧州において大型枚葉印刷機(VLF)で印刷されているものは日本ではオフ輪で行われていることが多い。そのため日本ではVLFを導入している会社の数も少ない。
枚葉大判印刷機の具体的なサイズはどういうものか。VLF(Very Large Format)で印刷される用紙には5サイズから9サイズまであり、その間に7種類ある(図1)。(1)5サイズは890×1,260でA倍判、(2)6サイズは1,020×1,420で菊倍判に相当する。(3)7サイズは1,120×1,620で四六倍判、(4)7Bサイズは1,200×1,620であり若干天地が伸びた四六倍判寸延び判である。同じ四六判の寸延びサイズだが天地がもう少し延びて(5)7B plusサイズが1,260×1,620である。(6)サイズ8は1,300×1,620でありA四倍判、(7)9サイズは1,510×2,050で菊四倍判になる。
VLFが脚光を浴びつつあるのは、世界的にも生産性を高めるために大規模で自動化された工場内の集約化という傾向がありトータルのバリューチェーンを整備して単価を下げることにより受注水準をある生産体制に持っていく狙いがあるからだ。VLFは2人のオペレータが操作することにより生産性向上が期待できる。コストも条件によるが、ページ数が増えることによって単価が低くなる。VLFは必ずしも大部数だけではなく2万5千部以下のロットでも単価競争ができるということがシュミレーションされている。
欧州でVLFが導入される背景の1つの要因として、ベルリンの壁崩壊後、東欧の国々が安い金利で最新の機械を導入して安い人件費で印刷物を製作しているところにある。欧州は陸続きなので大型トラックでいつでも持っていける。この影響で西欧の多くの印刷会社が潰れてきた。そうした流れの中で生き残りの考え方の一つとして、VLFを導入してより集中化した生産体制をとり単価を下げて対抗している。ドイツでは最近、大型機の導入が非常に進んできた。日本でも数は少ないが厚紙、商印又は出版分野でVLFに特化した仕事をしている印刷会社もある。
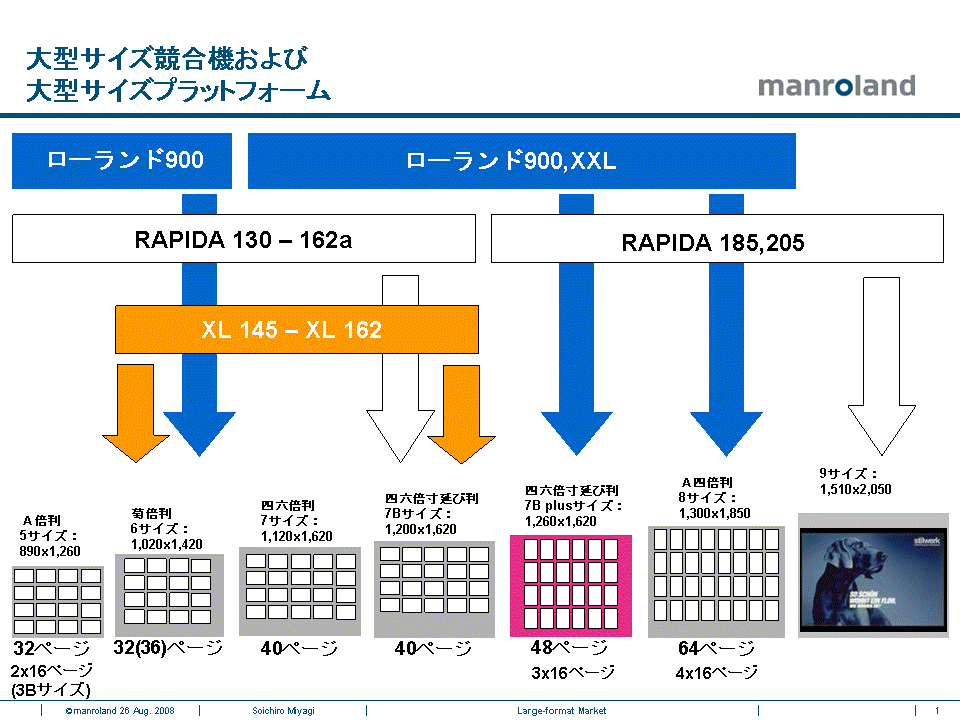
(図1) クリックすると拡大されます。
