『本文用明朝体のリョービ「本明朝-Book」誕生』
「明朝体」と呼ばれる書体は、印刷100年余の間に多種多様な明朝体が数多く存在している。明朝体の歴史は長く、明治初期の活版時代から写植時代を経て現代のデジタル時代にいたるまで、同じ明朝体であってもそのデザイン・コンセプトや形姿は微妙に変化している。それは、文字処理システムの変遷に影響を受けていることは否めない。
以前本誌で述べたように明治から昭和の初期まで、活字書体の主流といわれた「築地明朝」「秀英明朝」が一世を風靡していた。その後大正時代(1920年頃)に創業した、活字母型業者の「イワタ明朝」が台頭し活字書体の主流となった。続いてモトヤや日活などが活字母型販売に進出し、「モトヤ明朝」や「日活明朝」などが活版印刷に寄与してきた。そのため市場では母型メーカー名を書体につけて代名詞として呼んでいた。
一方写植の世界では、写植メーカーの創始者の名前をつけて「石井明朝」と呼ばれ、他の写植メーカーの追従を許さなかった。写植の両雄と呼ばれたモリサワは、自社の写植書体を整備したのは写研より後で、当初は活字母型メーカーと提携し活字書体を文字盤化していた。後発の写植メーカーであるリョービでも、初期にはモトヤや日活と提携し、写植用に活字書体を文字盤化していた。
日本の代表的な本文用書体としての明朝体は、その使われ方が広範囲に設定されてきた傾向がある。つまり大サイズの見出しから小サイズまで、共用できるという利便性があることや、また縦組みや横組みにも対応できるという便利な存在であった。
●本文用書体は明朝体が万能か?
これからの日本の本文用書体には、何が求められるのであろうか。昔から本文用書体は「明朝体」と相場がきまっていたが、本当に明朝体であれば本文用書体としてベストな書体であろうか。そこで「Book」(本文用という意味)を付けた新しい「明朝体」を取り上げて紹介する。
今まで意識的に「本文用」とうたった明朝体はなかった。明朝体といえば本文用という意識があるからだ。またしばしば「良い書体とはどのような書体のことか」を論じられることがあるが、良い書体とは「あらゆる要素を満たしていて、よく使われている書体」といえるであろう。
したがって見慣れた書体は、読者の目に馴染んで抵抗感が少ないというわけだ。一般的に明朝体は縦組み(縦書き)に適しているといわれ、横組みには不向きな書体といわれている。例をいえば、明朝体の特徴である横線の終筆部のウロコという要素は、横組み(横書き)における目の視線の流れを妨げていることになる。つまり可読性を損ねるという視覚的理由があるわけだ。
しかし前述した理由により大多数の日本人は見慣れた、そして読み慣れた明朝体に抵抗感はなく、好感をもっている(そうでない明朝体もあるが)。つまり日本の印刷書体としての明朝体の位置づけが、本文用書体の代表として尊重され、あるいは偏重されているともいえるほどである。
明治の末期から昭和の初期へかけて、多くの活字書体の明朝体が存在していたが、昭和初期に写植機が実用化され、写植機用明朝体が生まれる土壌ができてきた。戦後の1947年頃には写植機の開発者である写研の石井茂吉が苦心を重ね、最初の「細明朝体」を文字盤化した。これが「石井細明朝」と呼ばれ、印刷用本文書体として最も多く用いられた写植書体で、写植書体の代名詞になったほどである。
後年になり、リョービの「本明朝」という名の明朝体が、リョービ製写植機の文字盤に搭載され印刷物に使われるようになったが、出発は欧文活字販売の「晃文堂」に始まる(つづく)。
※参照:リョービイマジクス資料「本明朝Book」より
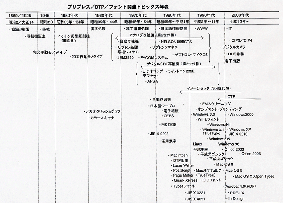
【参考】プリプレス/DTP/フォント関連トピックス年表
(拡大する場合は画像をクリックしてください)
■DTP玉手箱■
2005/02/19 00:00:00
