図は、経済産業省発表の「印刷統計」による品目別生産に関する推移である。トレンドを見るために6ヶ月移動平均で見ている。このデータは、印刷工程のみの金額を集計したものでプリプレスや後加工は含まない。また、外注費や用紙代を含んでいない金額だから印刷工程の加工高ということになる。また、データを採取する調査対象は100名以上の事業所だから、かなり規模の大きな印刷会社の数字である。
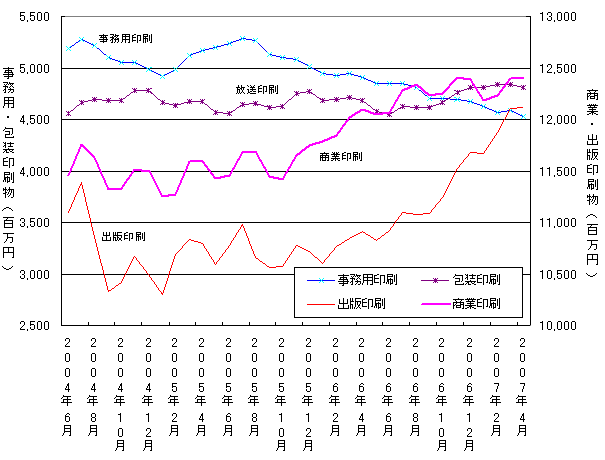
図:主要印刷物印刷加工高推移
過去3年間のトレンドを見ると、2005年度は全体としてほぼ横ばい(0.8%増)であったものが、2006年度は分野による差はあるが全体としてはかなり増加している。具体的な数字で見ると3.8%増であった。
品目別に見ると、2005年末あたりから4品目それぞれに異なる動きが見られる。事務用印刷は、2005年上期には増加したが下期以降減少に転じている。ここでの事務用印刷はいわゆるBF印刷が主体と思われ、2005年に個人情報保護関連の需要増で拡大した。しかし、それはこの分野の長期低落を変えるような変化ではないから、特需が終わった段階で再び従来の長期低迷に戻ったということである。
2006年に入ってから増加に転じたのが商業印刷と出版印刷である。2005年度、商業印刷は対前年比2.4%増であったが、2006年度は5.0%と大幅に伸びた。景気全般は2003年から回復してそれなりの水準を維持してきているが、大手企業を中心に企業収益が過去最高を記録するなどの状況が定着し、2006年度は商業宣伝印刷物作成にも以前より余裕が出来たためと思われる。
最も大きな変化は出版印刷物に見られる。図で見るように2006年夏から上昇をはじめ、急速に増加している。2006年度の出版印刷の加工高前年比は実に8.3%増であった。2006年の書籍・雑誌販売額は△2.0%で、2年連続の前年割れになった。書籍販売金額は 1.4%増だったが、雑誌販売金額が△4.4と過去最大のマイナスとなったからである。そのような中での規模の大きな印刷会社の出版印刷加工高大幅増は、フリーペーパーの大幅な増加によるものと見られる。大手印刷業の2006年度決算でみると、フリーペーパーは商業印刷物ではなく出版印刷物として分類しており、図の「印刷統計」でも出版印刷に分類されて集計されているとみて間違いないだろう。
日本生活情報紙協会(JAFN A)の調査によれば、2005年におけるフリーペーパーの年間総発行部数は95.5億部で、2003年の64.3億部からわずか2年で31.2億部も増えている。この部数増加にともなう紙の使用量増加は、同期間に増加した印刷情報用紙の出荷販売量増加分にほぼ匹敵すると推計される。有代雑誌のための紙の使用量と対比すると、雑誌が2年間で15%増加した量に匹敵する。フリーペーパー需要増大の恩恵は、中規模以上企業に限定されるのだろうが、その印刷物需要全体への貢献度は非常に大きい。
ちなみに、2005年におけるフリーペーパーの広告費は4082億円と推計されている。これは、テレビ、新聞、折込に次いで第4位を占める大きさである(「情報メディア白書2007」:電通総研編集、ダイアモンド社発行)。
(2007年7月3日)
2007/07/04 00:00:00
