クロスコミュニケーションユニット プラニングディレクター
亀井典明(かめい・のりあき)
エンゲージメントによる媒体評価の事例
ここに、前回紹介したJean-Louis Laborieのコンセプトを実践した事例を紹介しよう。2007年7月、『VOGUE』や『GQ』を発行するコンデナスト・パブリケーションズ・ジャパンとADKが、雑誌のエンゲージメントパワーを評価する方法を共同で開発し、分析結果とともに公開した。
このプロジェクトの特徴は、第1にエンゲージメントを次の2つの効果の掛け算と規定したことである。すなわち、(1)雑誌自身のブランド価値が、広告掲載された文字どおりのブランドに乗り移ってその価値を高める効果=『価値移転効果』(Value Transfer Effect)、(2)その結果、読者の購買など多様な行動を引き起こす効果=『起動効果』(Audience Activation Effect)がそれである。すなわち、Engagement Index=【移転効果】×【起動効果】である。
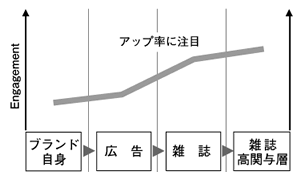
図2
その計測法はシンプルである。ブランドが現在持っているエンゲージ力をベンチマークとし、それが広告になった時、雑誌に掲載された時にどれだけ伸びたかを計測し、インデックス化したのである。 ところで「価値移転」の価値とは何を意味するのか。それが第2の特徴である。同プロジェクトは、ブランドと雑誌が提供するさまざまな心理的なベネフィットを、コロンビア大学Bernd H. Schmittの5つの経験価値に分類して計量した。
| ACT: | [行動] 一歩踏み出す気持ち。調べる、人に伝える、買う、習慣を変えること。 |
| SENSE: | [感覚] 五感に響く感じ。色、デザイン、質感、切り口やコンセプトのユニークさ。 |
| FEEL: | [心地] 高揚、(逆に)安静。刺激的、思わず没頭、メジャーの安心感、高品質の安心感。 |
| THINK: | [知性] 頭で理解。知的欲求をそそる、好奇心を満足、先進性、機能性。 |
| RELATE: | [帰属] アイコン・象徴への向き合い。モノ・所有者へのあこがれ、あかし、帰属意識。 |
では、どうやってブランドと雑誌が提供価値を規定するのか。それが第3の特徴である。まず対象ブランドと雑誌について、5つの経験価値のそれぞれに付随した4問ずつ、計20問を問う調査を行う。次にACTを「結果」に置き、SENSE、FEEL、THINK、RELATEを「影響要因」に置いて、因果関係を特定する。つまり、4つの経験価値のうち、どれが、消費者の「行動」を引き起こす最も直接的な要因になっているのかを特定するのだ。これをブランドのコアバリューとする。そして間接要因も同時に探り出すのだ。これにはパス解析という統計手法を用いる。
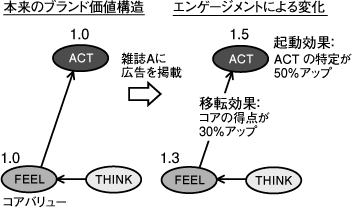
図3
図3は分析結果の例である。左側はあるブランドの価値構造を示したものである。このブランドは、THINK(知性に訴える経験)が、FEEL(信頼の安心感)を生み、それが直接の原因となって消費者のACT(口コミや購買)につながっていることを表している。一方右方は、このブランドを雑誌に掲載したらどのようなエンゲージ効果を受けるのかを示している。価値構造を変えずに、コアバリュー、行動のいずれもが増幅したことが、数値によって示されている。
では、実際にエンゲージメントの視点で、雑誌の重要度を評価した例をご覧いただこう。この分析を通じて、次の2つの発見があった。それにも注目してほしい。
- ブランドと雑誌の経験価値構造が似ている場合とそうでない場合では、エンゲージメント効果に違いがある
- 媒体への関与度が高い人たちの間では、それが一層顕著に現れる
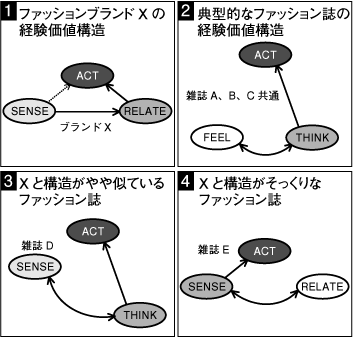
図4
図4-1は、ある高級ファッションブランドXの経験価値構造を、4-2はファッション誌A、B、Cに共通の価値構造を、4-3はブランドとやや構造が似ている雑誌Dの、4-4はそっくりな雑誌Eの、それぞれの価値構造を示している。いずれもACTを結果指標とし、ほかの経験価値を原因指標とする因果関係図である。
ブランドXの経験価値の因果関係図(4-1)によると、消費者はXのセンスに注目し、ブランドや所有者コミュニティーへのRELATE(あこがれ)を持つ。その「あこがれ」が、購買やブランド探求のモチベーション(コアバリュー)となっているのだ。一方ファッション誌A、B、Cの読者は、それらに掲載されている記事や広告のTHINK(知的側面)に刺激されてACTする。D誌はこれにSENSE(センスの良さ)が加わる。そしてE誌は、SENSEとRELATEがACTにつながっているという点で、ブランドXとそっくりな経験価値構造を持っている。
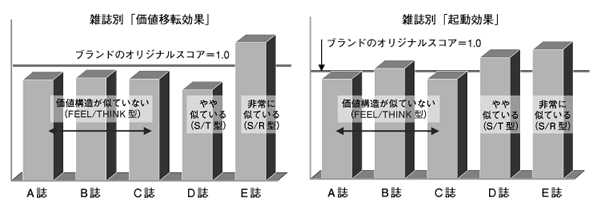
図5
ではブランドXは、それぞれの雑誌に掲載することによって、どのようなエンゲージメントを受けるのであろうか。図5で「価値移転効果」(RELATEスコアの現状に対する伸び率)と「起動効果」(ACTスコアの伸び率)に分けて見てみよう。この図の縦軸はインデックスを表す。すなわちブランドが本来持つスコアを1.0とした場合、各雑誌がどのくらいそれを伸ばしたのかを示しているのだ。この結果から、ブランドと雑誌の経験価値構造が似ている場合とそうでない場合とでは、エンゲージメント効果に違いが出ることが分かる。経験価値構造が異なるA、B、C誌は、移転効果、起動効果ともに、現状に対して顕著な伸びがない。D誌は構造がやや似ている分、起動効果において伸びが見られる。一方そっくりなE誌では、両効果において明らかに有意な影響を与えていることが分かる。
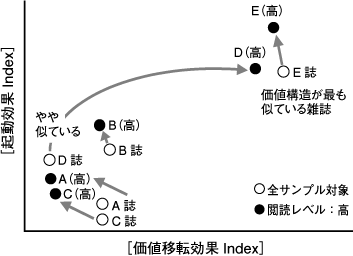
図6
次に図6をご覧いただきたい。これは横軸に移転効果を、縦軸に起動効果を取り、各誌のスコアをプロットしたものである。白丸のシンボルは読者全体のスコアである。そして黒丸のシンボルは高閲読者に限定したスコアである。この図から、媒体への関与度が高い人たちの間では、それが一層顕著に現れる様子が見て取れる。例えばE誌は「移転」「起動」ともに高い効果を発揮しているが、閲読頻度が高い人の間では起動効果が一層顕著である。D誌はユニークである。一般読者層においては必ずしも目立った存在ではない。しかし、高閲読者の間では、ドラマティックに効果が上がるのだ。事実、ブランドXの年間雑誌出稿金額の1位と2位が、E誌、D誌だという。メディアプラン担当者は、一般的なデータや感覚的な基準で、雑誌の本質的な効果を見抜いているのであろう。エンゲージメントスタディはそれを数値化し、証明するというサポートにもつながるのだ。
・第1回 エンゲージメントの意味を考える
(『プリンターズサークル』2008年7月号より)
2008/08/16 00:00:00
