去る1月28日に行ったJAGATとMIS懇談会との共催セミナー「利益を管理する会社が生き残る」における壮光舎印刷株式会社竹内社長のお話の一つの要点は、利益を管理するためにはまず部門別あるいは工程別の予算をきちっと作ること、ということである。予算に基づく標準値によって事前原価をきちっと把握することができるし、予算を作ることは自社のコスト構造を明確にすることであり、そのデータ自体から得られるさまざまな情報を経営判断に有効に活用できるからである。
印刷業界でも、やっとどんぶり勘定ではやっていけないと意識され始めた。いまのような価格の下落が無かった時代には、売上や仕事量を見ておけば利益も予想できた。しかしいまは、価格競争の問題だけでなくプリプレスの技術も大きく変化したので、どこでどれだけ利益が出ているのかを直接把握しておかないと判断を大きく誤ることになる。
図1は、いまのような値崩れが起きる前に、ある印刷会社で商品分類ごとに月間の売上高と粗利益率を調べた結果である。今から見ればかなり高い粗利益率水準にある。その高低は別にして、例えば新年度の営業方針を考えるとき、売上高だけで見ればBFの仕事を減らすという方針はまず出てこないだろう。しかし、粗利益率というデータを合わせて見たときには、個別に利益状況を調べて価格交渉の可能性あるいは取捨選択を検討することになるだろう。新聞は営業段階ですでに大きな粗利益率のマイナスになっているから、どう見ても会社全体として利益が出ていない仕事である。
いまは、各社で図1のBFや新聞のような状況にある商品もかなりあるのではないだろうか?
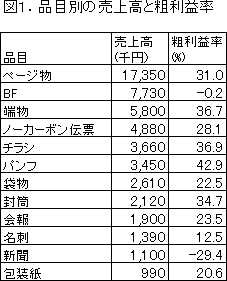
図2は同じ会社の二人の営業マンの実績である。売上だけで見れば両者にそれほど差は無いが粗利益率を見ると大変な開きがある。これが現実である。Bさんは自らの給料を稼がないばかりか、他の営業マンが出した利益をも食いつぶしているわけだから、少なくとも数字だけから言えば、Bさんはいない方が良いということは誰が見ても明らかである。
図2で、工程別の粗利益率に注目すると、2人の組版の粗利益率がいずれもかなり大幅なマイナスになっている。この会社の組版の生産性はかなり問題であることがわかる。製本も組版ほどではないが同様である。
図1、2と同じことを得意先別に行ってみれば、従来とはかなり違った得意先の見え方になるはずである。最近の情勢のなかで見れば、少なくとも数字だけから見ればもう手を引いたほうが良いといった得意先も見つかるのではないだろうか。当然、時系列的な変化も見る方が良い。壮光舎印刷の場合には5ヵ年での変化を一覧表にして見ている。
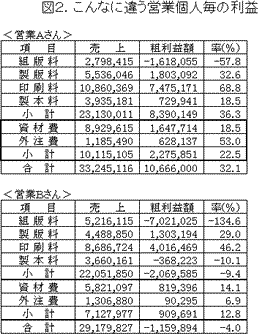
上記の図1,2のデータは、部門別予算を作り、そのデータに基づいて作った社内仕切価格と売上高とを対比させることによって得られた情報である。社内仕切価格は予算を元にしなくても作ることができるが、やはり予算と標準作業時間を元にして出した社内仕切価格を使うことがお勧めである。それはより明確な根拠を持った数字として使えるということと、部門別予算を作ることで自社のコスト構造や生産性の実態等さまざまな経営実態を明らかにすることができるし、改善のためのシミュレーションにも使えるからである。
図3は部門別予算表の一つのモデルである。部門別の直接経費(図の最上行「固定費(直接)」)を計算して、その後管理部門や工務部門といった間接部門の経費を、利益を出すべき部門に配賦、さらに会社全体が出すべき利益も割り振って部門別の売上、加工高、利益(会社全体でいう営業利益相当)の予算表としてまとめたものである。その下には、各部門の予算を元に計算した生産性(一人当り、時間当り等)等の目標値を計算してある。 この表からだけでもいろいろなことが見える。
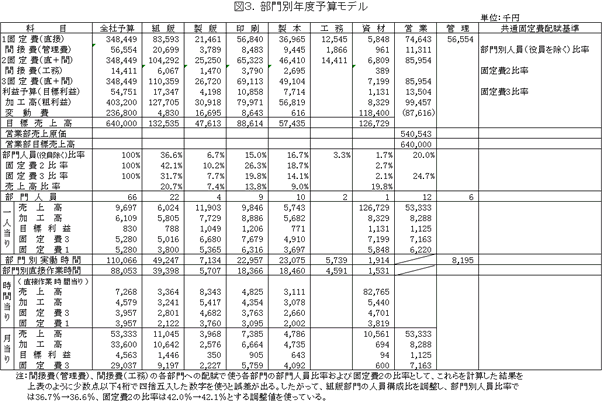
固定費が大きい部門はどこかがわかるし、その細部の内容は「固定費(直接)」を出した元資料から知ることが出来る。図3では各部門に求められる価値的労働生産性に大きな差があることが明確にわかる。例えば、一人当り加工高は最大の印刷(8887千円/人・年)と最低の製本の5680千円/人・年とで5割以上の差がある。会社全体としての一人当り加工高目標といったものだけでは管理的には不充分であることがはっきりわかる。
毎年、同様の予算資料を作っておけば、各部門のコストおよび価値的生産性目標がどのように変化してきたかがわかる。図3の時間当り売上高(一人一時間当り売上高)、あるいは加工高を維持ないしは上げていくことが現場管理職の基本的な任務である。いつも設備と人が足りないとぶつぶつ言っている現場の管理者に、そのような数字を見せて説明してやれば、むやみに人と設備を入れることが結局自分の首を締めることぐらいは理解できるはずである。もし、それが理解できないとすれば、その人は管理職には向かないということである。
ごく普通に事務処理に使っているエクセルのようなソフトでもさまざまなシミュレーションが簡単にできる。直接固定費のデータを含めて図3の各種データを使って、どのようにすれば利益がどのように変化していくかを推測することができるはずである。
設備投資をしたときにコストがどのようになり、設備導入をした部門の価値的生産性はどの程度まで上げなければならないのか、そしてそれは可能なレベルなのかどうか、あるいは内製化によるコスト構造の変化や利益への影響等のシミュレーション程度は可能である。
図3の時間当り売上高または加工高は、製造各部門が出すべき利益を含めた形で設定する社内仕切価格の元になる数字である。この数字に各作業毎の標準作業時間を掛け合わせれば、それが作業単位の社内仕切価格になる。営業部門が出すべき粗利益率は「営業」欄の加工高(99457千円)を営業部目標売上高(640057千円)で割った15.5%である。資材部門が出すべき粗利益率は6.6%(8329千円×100/126729千円)と設定できる。
これだけ価格が下がったいま、社内仕切価格のようなものを作ってみても意味がない、といったことを耳にすることも増えた。それは、とにかく仕事を取らなければ先がないということなのだろうが、実際に赤字の仕事をとればそれが首を締めることは言うまでもない。にもかかわらず、先のようなことを言っていられるのは、現実にはかなり利幅のある仕事もまだあるからとしか言い様がない。
しかし、この1,2年で今の受注競争が緩和するといったことは誰も考えないだろう。3年、5年という期間で考えるのならば、いろいろな仕事を混ぜこぜにしてみればそこそこ利益が出ているという状況を放置することは出来ないはずである。利益の出方を、1品別、得意先、部門別等のように細かく見て利益が出ていない部門であればコストダウンの具体策を検討して実行するか縮小する、あるいは利益の出ない仕事については、手を引くことを含めて具体的な対応策を決めて一つづつ実行していくしかない。
いずれにしても、上記で説明したような部門別予算作りから始めることをお勧めする。
来る2月27日(木)、28日(金)の2日間、「利益管理導入の実際」セミナーを、装いを新たに開催する。今回のセミナーからは、予算作り、仕切価格作りの演習をエクセルソフトを使って行う。そして、そこで使うソフトを参加企業に無料で進呈する。このソフトは、各部門別の直接経費から図3で示したような部門別予算表の作成、および、そこで出されたデータと別途設定した標準時間のデータとから作業単位の仕切価格を設定するプロセスを処理するものである。
頭で理解しても実際に予算表を作り仕切価格を設定していく作業はかなりの時間がかかるものである。今回のセミナーで無料提供するソフトは、そのような業務処理負担を軽減し、より多くの印刷関連企業に利益管理システムを実際に構築、運用していただくために、非常に有効であると考えている。
2003/02/12 00:00:00
