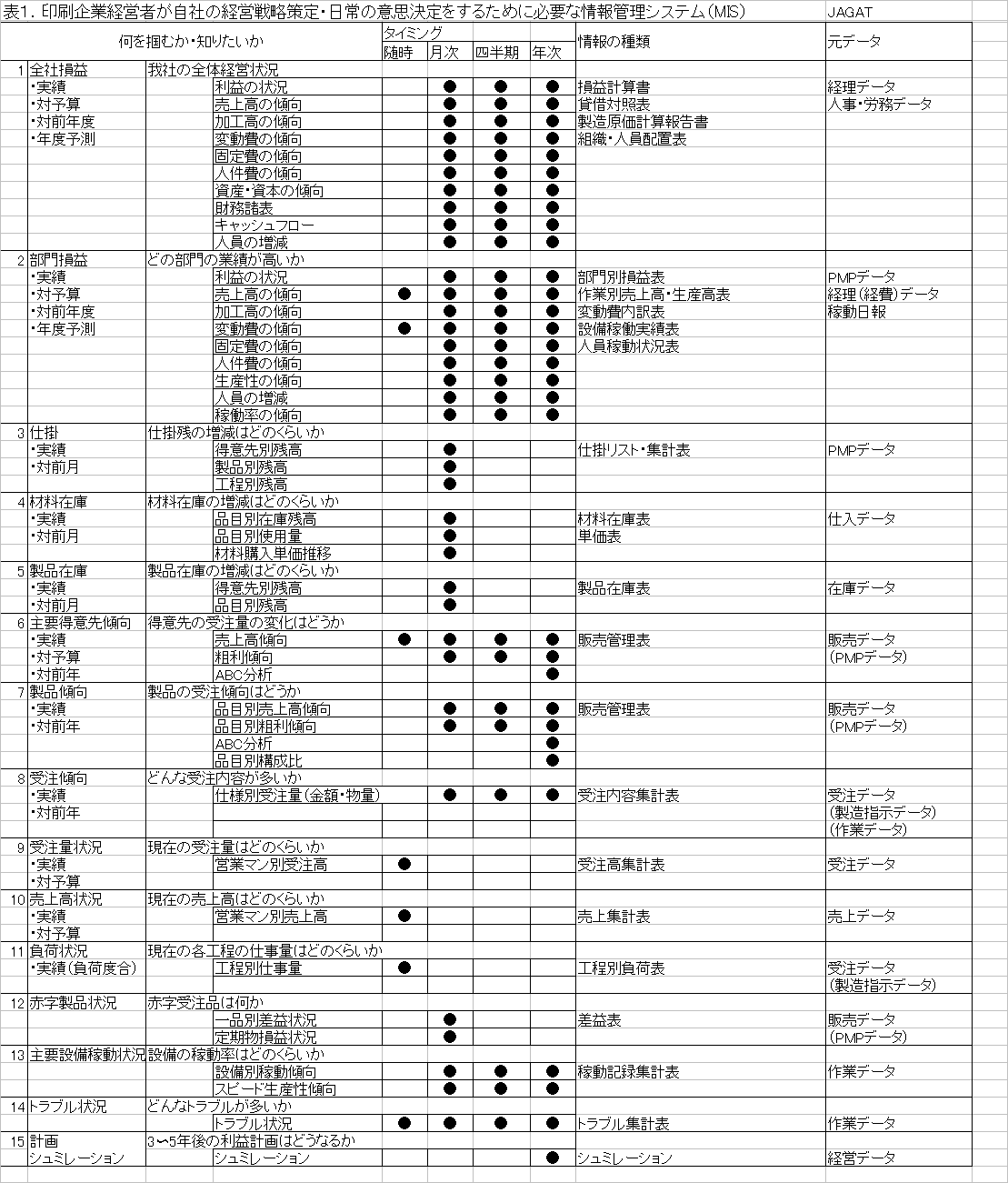経営管理層が必要とするMISの出力情報(要登録)
一般的に、印刷会社の情報管理システム(MIS)は日常業務の処理を正確に効率良く行うことが主眼に構築されている。反面、経営トップとして意思決定に必要な情報がタイムリーに提供されているかはに関しては必ずしも充分でない場合が多い。
印刷市場、印刷産業の経営環境が大きく変化した現在、印刷会社の経営はどんぶり勘定から脱して緻密な管理が非常に重要になってきた。生産量を見ていさえすれば利益の状況も推測できるといった状況はもはや存在しない。技術変化、価格低下のなかで、問題点を木目細かく把握し、日々の改善に繋げていかなければ利益率はどんどん落ちるばかりである。これからの経営管理・管理情報システムは,日常業務をうまくこなすだけではなく、経営者、管理者が必要な情報を必要なときにいつでも得られるようなものでなければならない。
経営管理層が必要な情報といってもその内容は多岐にわたる。表1は、日々の状況把握で必要なものから、経営者、管理者の意思決定に必要な情報を、必要なタイミングに分けて整理したものである。
日々・随時必要な情報
1.受注量・売上高状況
営業マン,グループ別に現時点での受注・売上状況を把握する情報で,目標達成度,未達成度などから,未達成の大きい担当者に営業日常行動へアドバイスなどをする。2.主要得意先売上高状況
主要得意先の発注状況を把握する情報で,特に対前月,対前年度との対比で得意先の発注意向,自社に対する問題点の有無の判断材料とする。判断によっては同行または単独訪問により得意先の本意をつかむ行動が必要になる。3.生産部門の実績
生産・製造部門の売上高または生産高の情報で,目標達成度合から部門利益状況を判断する。4.負荷状況
各工程の1〜2週間先までの仕事量を把握する情報で,受注金額の裏付け資料として売上高の見通しや外注発注のガイドラインに利用する。月次・年次単位で必要な情報
1.全社損益
当社の当月および累計業績の状況を判断する情報で,経理部門から得られる経営実績の基本となる。利益実績は売上高,加工高,変動費(材料費,外注費など),固定費(人件費,経費)のどの要素かの判断に利用する。各経費の売上高比率や要素の前年度比較をしながら傾向を探る。2.部門損益
期間の全社利益実績に対する部門の貢献度を判断する情報で,全社業績を営業,製造,その他部門別に業績を見ることで具体的問題点の摘出と改善策を立てる資料である。部門損益は部門ごと,特に営業以外の部門に部門売り上げまたは生産高を計上させる必要がある。JAGATが管理システムに推奨している「社内仕切価格」を取り込んだものである。全体と同様に部門の利益の増減要素を的確につかむ。特に生産性(1人当たり)の傾向と増減要素をつかむことが必要で,適正人員の把握がより可能になる。3.仕掛かり
営業部門売上・損益資料を補完する情報。特にページ物のように入稿から完成納品まで期間の掛かる製品を多く取り扱う企業では重要である。仕掛かり残の増減原因をつかむことで不良なコスト発生を防ぐことや,時には請求漏れを発見できる。4.材料在庫
主要材料の用紙,インキ,刷版の月間使用量,在庫量,購入単価の変動を把握する情報。売上比率,対前月・対前年増減により購入量の適正の判断や今後の傾向を把握する。5.製品在庫
帳票類,包装製品など製品在庫扱いとなる在庫残高を把握する情報。月間払い出し量,在庫残高増減により不良在庫の判断に利用する。とかく営業担当者が得意先製品在庫残高を忘れており,不良品となってしまう場合がある。6.主要得意先傾向
主要得意先の売上高,粗利傾向の情報。市場要因,製品要因,価格要因,競業要因などを分析し,得意先満足度を上げ,売り上げ拡大の検討に利用する。1年に1回はABC分析をし得意先のランク付けと個別の戦略を考える。7.製品傾向
主要製品の売上高,粗利,構成比傾向の情報。市場要因,製品要因,価格要因,競業要因などを分析し,製品ごとの販売,生産システムの改善施策に利用する。1年に1回はABC分析をし製品のランク付けと個別の戦略を考える。8.受注傾向
受注内容の情報。受注品を生産仕様要素別に層別集計し内容分析する。例えば製品別のサイズ,色数,プレプレス手段,版数,号機,ロット,通し数,色数通し数,製本形態,配送形態など生産様式別に集計し,各工程の設備・人員の整合性を判断する。9.赤字製品状況・定期物利益状況
赤字発生製品や定期物製品の損益状況を把握する情報。大きな赤字を生じた製品に対して,一品別差益管理・原価管理集計分析から得意先,営業担当者,生産システムなどの赤字要因を抽出し,改善策を講じる。比較的定期物,リピート物は管理を怠ると知らない間に利益が下がっていることがある。10.主要設備稼動状況
売上高・生産高の主要設備の物的生産性,稼動状況を把握するための情報。物的,価値的生産性の違いが起きている場合の要因を探る。価格,製品仕様の変化,製品と生産システムのアンバランスによる内製化,外注依存割合の変化などを調べる。稼動率では時間的効率,スピード生産性が目標に合致しているかを判断する。11.トラブル状況
トラブルの発生状況を知る情報。当月発生したトラブルを現象の層別集計し,原因の究明,対策,再発防止策などを全社的に構築する。12.計画シミュレーション
あらゆる状況から自社の短期・中期の戦略的計画を立案するが,最終的には定性的施策を利益計画の数値に置き換え,満足する利益になるかをシミュレーションする。 これらの情報をすべて必要とするかは別ではあるが,この辺が主に経営者が把握したい情報である。以上、印刷企業の経営者、管理者が捉えてさまざまな改善に生かしていくために必要な情報はどのようなものかについて紹介したが、表1の内容を使って、貴社の管理情報システムで得られる情報およびそのような情報を活かした改善がなされているかをチェックしてみてはいかがだろうか。
表1
印刷企業経営者が自社の経営戦略策定・日常の意思決定をするために
必要な情報管理システム(MIS)
(JAGAT info 2003年2月号より)
2003/04/23 00:00:00