2018年8月26日(日)に実施する第50期DTPエキスパート認証試験の新出題項目を、下記の通り発表します。 続きを読む
「DTPエキスパート」カテゴリーアーカイブ
第50期DTPエキスパート対策講座―模擬試験とポイント解説―
第50期DTPエキスパート認証試験に向けて、模擬試験と問題ポイント解説による対策講座を開催します。
それぞれのDTPエキスパート~第50期DTPエキスパート認証試験申請受付開始
本日より記念すべき50回目となるDTPエキスパート認証試験の申請受付を開始した。これまで様々な業種、職種の方がそれぞれの目的をもって受験してきたが、共通するのは印刷・DTPのことをきちんと学び理解したいという思いであった。 続きを読む
DTPエキスパートのススメ
DTPエキスパート試験は、次回の試験日2018年8月26日で記念すべき50回目を迎える。 続きを読む
第49期DTPエキスパート認証試験結果総評
2018年3月18日(日)に実施しました第49期DTPエキスパート認証試験総評を掲載いたします。
続きを読む
DTPエキスパート結果通知発送
第49期DTPエキスパート認証試験の結果通知を発送いたしました。
本試験合格者の方につきましては、同封の案内に従い、資格者登録情報のご確認をお願いいたします。
尚、2018年4月に実施しましたDTPエキスパート更新試験・再取得試験につきまして、合格者の方に新しい認証証を発送いたしました。
エキスパート優待案内 2018年7月
エキスパート有資格者の皆様に提供させていただく各種優待制度のご案内です。
エキスパート受験予定者向け資格者ご本人優待や、現役エキスパート推薦による受験予定者に向けたご優待をご紹介しています。
- 優待の申込は期間限定です。各ご優待の申込期限を必ずご確認のうえ、お申込ください。
- 今後も優待制度のご案内はメールでお送りしてまいります。ぜひ基本台帳にメールアドレスをご登録ください。
エキスパート優待制度
1.有資格者ご本人ご優待
ダブルライセンス取得推進優待
受験予定者入手必須の模擬試験問題を無料にて進呈いたします。
この機会に是非DTPエキスパート/クロスメディアエキスパート 2種の資格取得をご検討ください。2.第50期DTPエキスパート/第26期クロスメディアエキスパート受験予定者ご優待
メディアビジネスの牽引役となるべきより多くの人材に対し、本試験を受験しやすい環境を提供するため、現役エキスパートの方のご紹介により受験予定の方の 受験準備にご利用いただける優待特典をご案内いたします。
優待特典
模擬試験問題を無料送付
優待対象者
第50期DTPエキスパート/第26期クロスメディアエキスパート認証試験を受験予定で、今後印刷メディア設計およびコミュニケーション戦略の企画提案展開等に臨む可能性のある方。
- 優待制度の趣旨に鑑み、受験を予定していない方のご利用はお断りいたします。
- お申込みには、ご紹介者となるエキスパート有資格者のエキスパートIDおよびお名前が必要となります。
申込方法
申込期間 2018年7月9日~2018年8月9日
エキスパートWeb基本台帳より優待制度申込書をダウンロードのうえ、お申込みください。
エキスパートWeb基本台帳 ログイン
ログインには、エキスパートIDおよびパスワードが必要です。
パスワードがお手元にない場合は、ログイン画面の「パスワード照会フォーム」より取得してください。- ご住所など登録情報に変更はございませんか?エキスパートWeb基本台帳でご登録情報をご確認ください。
- 基本台帳はメンテナンスのため6月下旬より一時的にアクセスできなくなることがございますのでご注意ください。7月6日より再オープンいたします。
ご注意
第50期DTPエキスパート認証試験/第26期クロスメディアエキスパート認証試験の受験は、別途申請が必要です。
受験申請は、下記より行って下さい。
第50期DTPエキスパート認証試験 受験申請
第26クロスメディアエキスパート認証試験 受験申請対策セミナー優待価格受講
試験対策セミナーをお得な優待価格でご受講いただけます。
※有資格者ご本人がもう一方の資格の取得のためにセミナー受講される場合も優待価格で受講いただけます。【有資格者ID】欄に、既に取得している資格のエキスパートIDをご記入ください。
お申込み方法等詳しくは、各対策セミナー案内ページよりご覧ください。【東京-大阪ライブ 6/22,7/6開催】課題解決のための『クロスメディアエキスパート総合対策講座』
・東京会場 一般価格21,600円(税込)
⇒ JAGAT会員およびDTPエキスパート有資格者紹介価格 14,040円(税込)
・大阪会場 一般価格18,360円(税込)
⇒ JAGAT会員およびDTPエキスパート有資格者紹介価格 11,880円(税込)
※1日のみの受講も可能です。詳しくは、ご案内ページをご覧ください。【7/7 東京開催】第50期DTPエキスパート対策講座―模擬試験とポイント解説―
一般価格16,200円(税込)
⇒ JAGAT会員およびDTPエキスパート有資格者紹介価格 9,720円(税込)【7/19 大阪開催】DTPエキスパート試験対策講座(大阪開催)
一般価格9,720円(税込)
⇒ JAGAT会員・大印工組合員・DTPエキスパート有資格者紹介価格 7.560円(税込)
DTPエキスパート企業別累計合格者数
DTPエキスパート認証試験は、各企業の人材育成に活用いただいてまいりました。
節目となる50回を迎え、過去の累計合格者数上位100社を掲載いたします。
※本集計は、JAGAT資格制度事務局が把握する資格保有時登録内容に基づき行っています。
| 企業名(敬称略) | 累計合格者数*(名) |
|---|---|
| 大日本印刷(株) | 784 |
| 凸版印刷(株) | 727 |
| (株)DNPコミュニケーションデザイン | 395 |
| (株)DNPメディア・アート | 338 |
| (株)トッパングラフィックコミュニケーションズ | 307 |
| 日経印刷(株) | 184 |
| サンメッセ(株) | 174 |
| キヤノンマーケティングジャパン(株) | 169 |
| 富士ゼロックス(株) | 159 |
| 共同印刷(株) | 134 |
| (株)小森コーポレーション | 121 |
| (株)モトヤ | 112 |
| NTT印刷(株) | 110 |
| 水上印刷(株) | 109 |
| (株)第一印刷所 | 97 |
| 三浦印刷(株) | 92 |
| (株)研文社 | 89 |
| (株)Too | 86 |
| 高桑美術印刷(株) | 86 |
| (株)モリサワ | 81 |
| (株)加藤文明社印刷所 | 80 |
| 瞬報社写真印刷(株) | 80 |
| セキ(株) | 78 |
| (株)帆風 | 78 |
| (株)金羊社 | 74 |
| (株)平河工業社 | 74 |
| (株)DNPテクノパック | 72 |
| (株)サンニチ印刷 | 69 |
| (株)光陽メディア | 69 |
| 大日本法令印刷(株) | 69 |
| (株)アスカネット | 68 |
| (株)プレスメディア | 68 |
| リコージャパン(株) | 66 |
| 大村印刷(株) | 65 |
| (株)DNPデータテクノ | 64 |
| (株)グラフィック | 62 |
| コニカミノルタジャパン(株) | 62 |
| ジャパンプリント(株) | 59 |
| NISSHA(株) | 59 |
| 富士ゼロックス東京(株) | 59 |
| (株)太洋社 | 59 |
| あかつき印刷(株) | 56 |
| 竹田印刷(株) | 56 |
| 壮光舎印刷(株) | 55 |
| 福島印刷(株) | 53 |
| 凸版メディア(株) | 51 |
| (株)リーブルテック | 49 |
| (株)沖データ | 49 |
| (株)大鹿印刷所 | 49 |
| NECマネジメントパートナー(株) | 48 |
| 朝日印刷(株) | 47 |
| (株)ウィザップ | 46 |
| 広研印刷(株) | 46 |
| (株)阿部紙工 | 45 |
| (株)あかがね | 41 |
| トッパン・フォームズ(株) | 41 |
| (株)青葉堂印刷 | 40 |
| キヤノン(株) | 39 |
| 図書印刷(株) | 38 |
| (株)山田写真製版所 | 35 |
| 第一資料印刷(株) | 35 |
| 萩原印刷(株) | 35 |
| (株)フジプラス | 35 |
| 富山スガキ(株) | 35 |
| (株)ユーメディア | 34 |
| (株)廣済堂 | 34 |
| ダイヤミック(株) | 34 |
| 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株) | 34 |
| (株)朝日印刷 | 33 |
| (株)日進堂印刷所 | 33 |
| たつみ印刷(株) | 33 |
| 三美印刷(株) | 33 |
| (株)ムサシ | 32 |
| 光村印刷(株) | 32 |
| 十一房印刷工業(株) | 32 |
| 新村印刷(株) | 32 |
| 豊国印刷(株) | 32 |
| (株)木元省美堂 | 31 |
| (株)メディアテクノロジージャパン | 30 |
| (株)精興社 | 30 |
| (株)遊文舎 | 30 |
| JTB印刷(株) | 30 |
| エプソン販売(株) | 29 |
| (株)ムレコミュニケーションズ | 28 |
| (株)小森マシナリー | 27 |
| 西巻印刷(株) | 27 |
| 富士ゼロックス北陸(株) | 27 |
| 中日高速オフセット印刷(株) | 26 |
| (株)NPCコーポレーション | 25 |
| (株)メディアグラフィックス | 25 |
| (株)須田製版 | 25 |
| 斯文堂(株) | 25 |
| 瞬報社オフリン印刷(株) | 25 |
| 富士ゼロックス長野(株) | 25 |
| (株)DNP四国 | 24 |
| (株)コームラ | 24 |
| キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株) | 24 |
| (株)松井ピ・テ・オ・印刷 | 23 |
| (株)博報堂プロダクツ | 23 |
| 富士ゼロックス愛知(株) | 23 |
*第1期〜48期の累計合格者数(現時点の資格保有者数ではありません)
※(2018/6/1) ~49期までの累計合格者数に更新しました。
DTPエキスパート認証試験が25年目を迎え、第50期試験を実施
JAGATは、DTPエキスパート認証試験が25年目を迎え、8月26日に第50期試験を実施することを発表した。
続きを読む
ハードからソフト・人材へ[DTPエキスパート認証制度]
いよいよDTPが主流となる
DTP が主流となり始めたアメリカでの動きを受けて、1994(平成6)年2 月開催のPAGE94ではDTPを真正面から捉えようと「JAGAT DTP Conference」を開催した。同時期にスタートしたのが「DTP エキスパート認証制度」である。DTPの進化は速く、電算写植やトータルスキャナーのようなプリプレスシステムは1997(平成9)年頃を境に衰退の一途をたどった。
このように変化の速い技術と常に歩調を合わせ、情報のアップデートができる制度にするため、有効期限を2 年とし、更新試験によって資格が維持されるものとした。名称もポピュラーなものは避け、新しい技術知識をもち顧客・デザイナーを含めた印刷現場をリードできる「専門家」という意味を込めて「DTPエキスパート」と命名した。
DTPの教育をどうするのか
DTP が世界の本流となることを確信しても、1バイト言語の世界とは違い、漢字・ひらがな・カタカナ・数字・ローマ字を利用する日本語の世界では、コンピューターの処理能力の問題だけでなく、使えるフォントがほとんどなかった。1987(昭和62)年にモリサワがアドビと日本語PS フォントの開発契約をしたが、環境が整うまでには数年のタイムラグがあった。Illustrator 3.2J、QuarkXPress 3.1J、そしてヒラギノなどが出そろい始めてからやっと日本語DTPの本格稼働が始まった。
フォントの充実とともにDTPは急速に進歩し、実用レベルに達しつつあった。しかし、制作現場には様々なノウハウやTIPSが存在し、ハード・ソフトの未熟さや知識不足ゆえのトラブルに対応していたのが現状だった。DTPが印刷物制作の本流となるためには、標準化された知識の普及を急ぐ必要があった。そのためには、DTPというオープンシステムに相応しい、オープンな情報を基にした教育が必要であった。
そこで、1992(平成4)年から翌年にかけて日本のDTP先駆ユーザー30社ほどにヒアリングし、「どのような勉強をすればよいか」というアンケート調査を行った。そこから得られた結果は大変有用なもので、この調査結果を厳密に整理し、各種資料を精査し裏付けすることで、教育カリキュラムになると確信した。
教育カリキュラム開発のために、欧米のDTPに関する書籍を可能な限り集め、精査した情報から編集作業を行った。しかし、DTP技術の多くは欧文組版がベースになっているので、日本固有の組版技術に関しては役に立たなかった。製版(画像)の考え方も同様であった。当時のプリプレス技術は写植分野と製版分野の技術交流がほとんどなく、どちらにも詳しい人材が少なかった。関心はあっても簡単には取り組めなかったのが当時のDTP 技術であった。

1993(平成5)年に発行した第1 版の「DTPエキスパートになるためのカリキュラム」では、写植と製版の両方の知識をもち合わせる人、またはそれを必要とする立場の人を想定していた。この時点でカリキュラムをすべて理解できる人は極めて少数で、DTPエキスパートと呼べる人は、日本には200名程度しかいないとさえ考えられた。アメリカではデザイナーや編集者がDTPの主たるユーザーであり、日本での普及を考えるなら、従来の印刷業界の枠にとらわれた発想から転換していかなくてはならなかった。
時代の変遷とカリキュラム改訂

「DTPエキスパートカリキュラム」は、印刷物制作に関わる立場の異なる人々がスムーズに共同作業ができるように、共通の知識体系として発表したものである。理想は完全カラーDTPであったが、まだ現実はOPI(Open Prepress Interface)などCEPSの併用もあり、初版のカリキュラムでは従来製版も含め2つの道を示していた。
カリキュラムは2年ごとに改訂する方針で、進歩の速い技術に合わせていくこととした。カリキュラム改訂は、そのままDTP環境の変化の歴史に重なる。1996(平成8)年の第2版では従来の「写植」「製版」の分類をなくして「グラフィックアーツ」としてまとめるといった大きな改訂を行った。
1998(平成10)年第3版では「よいコミュニケーション、よい制作環境、よい印刷物」の3つのキーワードを基本に大きく改訂した。プリプレスに限定するのではなく、発注者側のデジタル化ともうまくつなげて、共に負担を減らして印刷物を作り、さらに電子媒体を活用してコミュニケーションを図ることをDTPエキスパートの務めとした。これはマルチメディア、Webやオンデマンド印刷への業務拡大範囲の動向を反映させたものであった。
電子メディアの制作パフォーマンスが向上するのに比して印刷物制作が効率化しないと、印刷需要そのものの低減につながる。2002(平成14)年の第5版では、DTPでもパフォーマンス向上のための制作管理能力と、個別知識でも科学的なアプローチができることを主眼に見直しを行い、3つのキーワードに「高いパフォーマンス」を新たに追加した。
デジタルカメラをイメージキャプチャーの中心に据え、RGB入稿、ICCプロファイルによる色変換、PDF/X、CTP、Japan Color という流れで安定的に制作ができる体制が固まったことを受け、2004(平成16)年発行の第6版では、これらに関する項目の変更、追加を行った。
第7版を発行した2006(平成18)年頃には、インターネットの普及による著作権問題や、コンプライアンスに対する関心が高まり、知的財産権や個人情報保護法の項目が加えられた。2010(平成22)年の第9版では、初めて「電子書籍」の基本的知識や照明光源知識としての「LED」が取り上げられた。
2014(平成26)年の第11版からは、試験の新カテゴリー「コミュニケーション」が加わった。多様なメディアを効率的、効果的に作り上げていくのに必要なコミュニケーション能力が、DTPエキスパートにも求められる時代になったということである。
2017(平成29)年時点で最新のカリキュラムは第12版(2016年)だが、この先もDTPエキスパートの役目と方向性を明確に示すためにもカリキュラムの改訂は続いていくことになる。
学ぶ風土を生んだ認証制度
アナログ時代の経験や知識を活かしながらも、DTPという従来とは大きく異なる技術を一から学ぶ印刷界の人、コスト削減に魅かれて学び始めた印刷周辺分野の人、Macintoshに憧れ、新たな技術に興味を抱く人など、これらすべての人々を巻き込む「魅力ある学びの環境」こそが「DTPエキスパート認証制度」である。
合格者の中から、本人の了解のもと資格登録リストを作成し広報活動にも力を入れた。色やデータ作りについて「相談できる人」として氏名・社名・プロフィールや講師・執筆など活動可能な範囲を広く公開することで、新しいリーダーとしての活躍を願った。
初期の頃は先駆的に取り組んできた一部の企業や個人、出力センター、メーカー、デザイナーの人たちが「混乱を終息させ、解決へ導く」先生役を果たしてくれた。まさに印刷技術を取り巻く新リーダーの出現であった。
また合格者同士のコミュニティとして、相互に交流、研鑚を進める主旨の任意組織「DTPエキスパートクラブ」も発足した。東日本と西日本の2つの組織に分かれ、定例会を開催した。
DTP人材の裾野が広がり始めたのがスタートから7~8年ほど経ってからである。少しずつ知名度が上がってくると印刷業界とは全く縁のない、若い未経験の受験者が増え、全体の半数近くを占める時期もあった。専門学校やDTP受験指定校で勉強して新たにDTPの世界へ入ってきたのである。
製版・印刷業界でも、直接DTP業務には関係のない経営幹部や社長が先頭に立って受験に挑むケースもあった。2000(平成12)年を過ぎた頃から、現場の技術者やオペレーターより営業担当者にこそこの知識を活かすべきだと経営者が気づき、営業も含め人事・教育システムとして社内に取り込む会社が増えていった。営業担当者が正しい知識を得て、顧客とコミュニケーションが取れるようになり、トラブルが減少したことも事実である。また、受験を通じて習得したデジタル関連知識により、新たなビジネスチャンスを獲得する可能性も広がった。
そして、資格が定着すると更新試験に合わせて社内学習会が開かれ、先輩が指導する学びの風土が生まれた。この学びの風土の醸成こそが、資格制度の大きな目標であった。DTPエキスパート認証制度は選抜試験ではない。学ぶための道具であり、学び続ける環境こそが企業を成長させ、産業を成長させる。JAGATではカリキュラムの改訂とともに時代に最もふさわしい資格であり続けることを目指してきた。今日までに5万2340人(2017 年2月現在)がチャレンジし、2万2297人が合格している(合格率42.6%)。男性が多い業界にあって、合格者の35%が女性である。また、20代に占める女性の割合は高く、女性の活躍を後押しする制度となった。
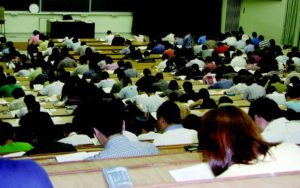

2カ月をかけて採点
出題範囲はDTPエキスパートカリキュラムに準拠し、印刷知識はもちろん、発注側知識、文字、画像、色、コンピューター、最近ではマーケティング分野に及ぶ知識を問う筆記試験と、実際の印刷物制作を提出する課題制作が課される。受験者にとっては合否は最大の関心事である。学びのプロセスこそが大切であるというのは簡単だが、その趣旨に見合った受験者へのフィードバックや課題採点の仕組み作りは楽ではなかった。
筆記試験は「DTP」「色」「印刷技術」「情報システム」「コミュニケーション」の5 つのカテゴリーで出題され、すべてのカテゴリーで80%以上の正解率で合格となる。1つのカテゴリーで1点でも及ばないと不合格となる。採点結果はカテゴリーごとの点数を結果通知で知らせるので、不得意分野の把握ができ、次回に向けての指針となる。
課題試験は、精緻な方法で採点を行うため最低でも2 カ月は要した。落とすための採点はしない方針で、2 人以上の採点官が合理的に不可とみなして初めて不合格と判断された。最終的に、提出物に不正がないか、また採点者の不備はないか判断が分かれ、迷う課題はDTPエキスパート認証委員会(初代委員長:猪股裕一)での判定とし、委員長が最終決裁をする公正な評価採点システムを構築した。
課題採点結果も、どの要素で落ちたかがわかるようにした。結果通知は資格の合否を知らせるものだけではなく、教育的見地から受験者のステップアップの礎となるべく、改良を重ねてきた。
人材育成こそが新しいビジネスを作る
カリキュラムを基準に共通の知識を得ることによって、地域、企業でバラバラであった現場用語や手順が次第に標準化された。印刷業界だけでなく、デザイン、出版編集、顧客といった分野にも広がり、互いのブラックボックスを解消していった。
2006(平成18)年にDTPに続き、メディア制作ディレクターとしての能力開発を目指して「クロスメディアエキスパート認証制度」をスタートさせた。
印刷業界にとって「印刷メディア+電子メディア」をどう扱うかが、これからのビジネスのキーになることは間違いない。かつての印刷業界は、同じ技術、同じ設備を持ち、同じサービスで競争して成長できた。しかし今日の印刷は同質技術、同質サービスからは強いビジネスは生まれない。自らの描いたビジョンに沿って技術と設備を選択し、それに見合った人材を育成することで企業は成長する。JAGATでは今後とも時代の変化に即した学び続ける環境作りに貢献していきたい。





