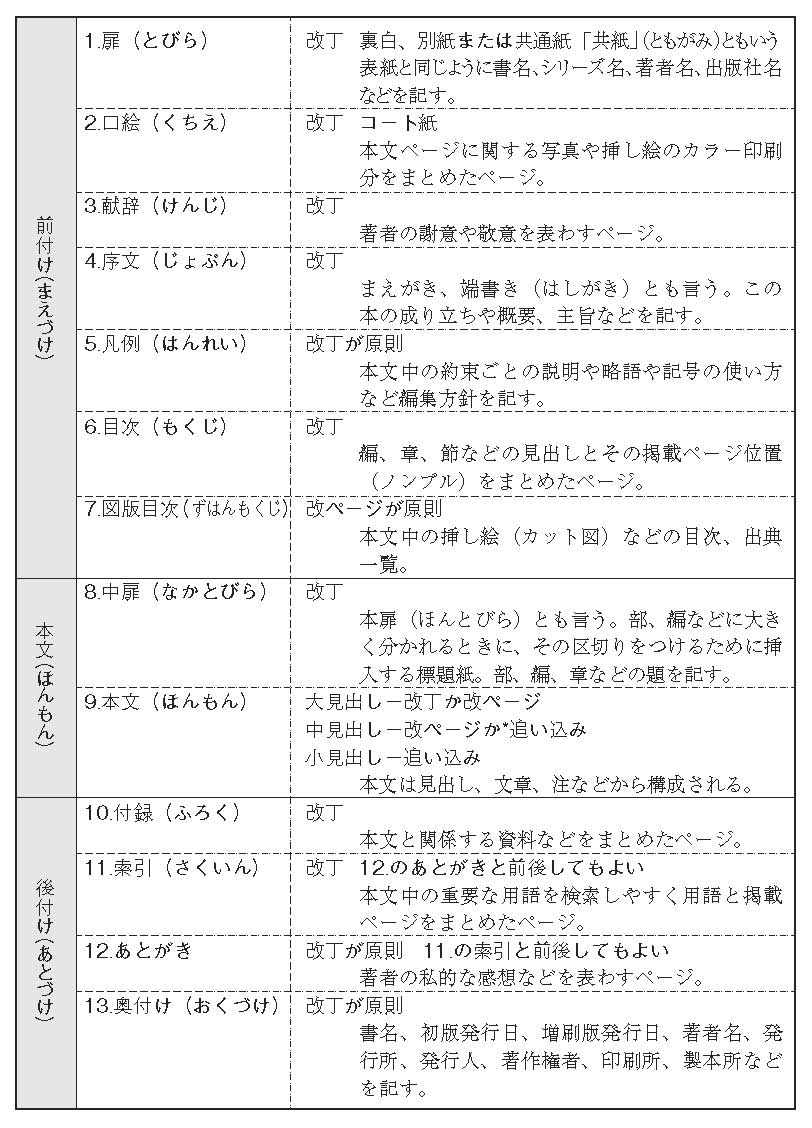1-3-1 企画
- 印刷物を制作するにあたっては必ず目的と用途がある。これらに基づいて制作のプロセスが進行する。
➢ 設計
- レイアウトの基本設計は企画コンセプトによって決定される。コンセプトに基づいて全体の構成や写真の配置、色使い、見出しや文字の大きさ、書体などを決めていく。また、組版の禁則処理や校正など、印刷物を製作するにあたって必要なルールを知っておく必要がある。
1-3-2 原稿
- 原稿には大きく分けて、写真などの階調原稿と、文字・図版などの原稿がある。
1-3-3 印刷物のサイズと用紙
- 印刷用紙のサイズには、「原紙寸法」と「紙加工仕上り寸法」の2つがある。
- 原紙は、印刷や製本を経た後に、仕上りサイズに加工される。
- JISの規格となっている「原紙寸法」には、
・四六判(788×1,091mm)
・B列本判(765×1,085mm)
・菊判(636×939mm)
・A列本判(625×880mm)
・ハトロン判(900×1,200mm)
の5つがあり、名称についてはJISにより規格化されている。 - 原紙サイズを1/2(半裁:はんさい)、または、1/4(四裁:よんさい)に裁ってから印刷することもあるため、元のサイズを便宜上「全判」と呼ぶのが一般的である。
・A列本判=A全判
・B列本判=B全判
・菊判=菊全判
・四六判=四六全判
また、JIS規格ではないが、A倍判やB倍判などといった、大きなサイズの原紙もある。 - 仕上り寸法がA列の場合は、「A列本判」や「菊判」の原紙を使用することが多い。B列の場合も同様に、「B列本判」や「四六判」の原紙を使用することが多い。原紙サイズで印刷した後に仕上げ段階で余分な部分を断裁して仕上げるのが一般的である。
- 印刷物のサイズは仕上り寸法であり、A1のサイズは841×594mm、B1のサイズは1,030×728mmである。一般的には印刷物の仕上りサイズは、倍判や全判の長辺を何度か2分割したものとするのが原則である。短辺と長辺の比率は、1:√2の関係である。A5は原紙を4回分割したもの(サイズは、210×148mm)であり、原紙から16枚とれる。
- 規格外の仕上り寸法が使用されることも多く、新書のサイズは182×103mmであり、B列本判から40枚とれる。AB判のサイズが257×210mmであるように、特殊な寸法は紙の無駄となる考えから、変形サイズであっても原紙や印刷を考慮して定められたサイズが使用されることが多い。このほか、148×100mmのハガキや、他の規格、慣例的に定められたサイズに則り、印刷物は設計される。
1-3-4 印刷用紙の選択
- 印刷物の品質は、印刷方式や用紙などの条件により、大きく左右される。
- 発色については、紙質の影響を受ける。印刷面に光沢をもたせるときは、塗工紙であるアート系やコート系の用紙を使用する。アート系やコート系の用紙は、カラー印刷物の場合、濃度が高くなり、彩度が高く感じられる。表面が粗く、乱反射を起こす用紙は、濃度が低くなる可能性が高い。また印刷物の発色には、紙の白色度が大きな影響を与える。
➢ 上質紙
- 上質紙は四六判で55~90kg程度のものが本文用紙として使用される。
- 紙質として淡いクリーム色の上質紙は、「裏ヌケ」が目立たず好まれる傾向がある。
- 色上質紙は、「扉」や「見返し」に使用されることが多く、名称が同一であっても製造元によって色合いが異なる。
- 色上質紙を分類する厚さの種類は、「特薄」や「特厚」といった名称で呼ばれ、連量表示とは異なる。
➢ ファンシーペーパー
- 表紙用として、装飾性のある「ファンシーペーパー」が使用されることがある。
- 「ファンシーペーパー」は、四六判のみが提供されているものが多く、連量も限定されている。
1-3-5 印刷用紙と光源
- 光源は種類により、含まれる波長とエネルギーが異なる。したがって、用紙上の色材の色の見え方に影響を与えることがある。印刷の色評価を行うためには標準光源の下で観察することが求められる。
- 用紙上の色材の色は、用紙自体の色、平滑性、吸油度、蛍光物質などの塗工材特性の影響を受ける。