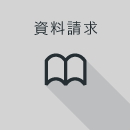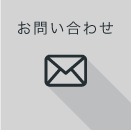第6期クロスメディアエキスパート認証第2部試験「与件:港アスレティッククラブ」
状況設定について
わが社
販売促進に使われる、印刷物やDVD、Webなどの制作をしている従業員25人の会社で、都市圏の中堅商業印刷会社の子会社である。別の子会社にデザイン会社がある。
プロジェクトについて
以前に印刷物を企画制作した顧客に、独立系中堅スポーツジムを運営している港アスレティッククラブ株式会社がある。同社のホームページの一部もわが社で手がけたことがある(参考資料1参照)。
営業担当者から、港アスレティッククラブが今までとは違う新たな方向性を出そうとしているという話を聞いて、何かこのクライアントを手伝えることはないかと相談をもちかけられた。
そこで、港アスレティッククラブのことを調べ直してみると、サービスの見直しを考えていることがわかったので、営業と制作の何人かで提案プロジェクトを作り、私がリーダーを務めることになった。
提案時期
社内のプロジェクトで港アスレティッククラブの状況についてまとめていた時点で、わが社のライバルがWebやケータイ販促での提案をしようとしているという情報が入った。そこで営業に様子を探らせた。
港アスレティッククラブは真剣にサービスの見直しを考えていて、そのヒントとして自由に社外からも優れたアイディアを多く得たいので、数社でコンペをして事業のプロモーションや業務改善、タイアップなど、かなり柔軟に検討したいようだという。桜木社長自身がこの件には意欲的で、来月半ばには社長宛にプレゼンをおこなうように各社に要請するようだ。
ということで、社内においてこの1週間のうちに自主的な提案書のラフを作成して、コンペに耐えられるよう一度揉んでおかなければならない。まず、このプロジェクトのリーダーをしてきた私が、プレゼンテーションに使用する提案の骨格を作成して、社内各所で検討してもらい、ふくらませていかなければならない。
<社外秘>プライムプロジェクトメモ 2008.7.27
港アスレティッククラブ 会社概要
<社名>
港アスレティッククラブ株式会社
<設立>
昭和43年(1968)年
<資本金>
221,276千円
<年商>
4,575,857千円(2007年)
<従業員>
165名(アルバイトを含む)
<所在地>
本社(横浜事業所) 神奈川県横浜市緑区
大阪事業所 大阪府大阪市
(川崎、大和、横須賀、大阪、泉大津)
<役員>
代表取締役 桜木 源一郎 専務取締役 白川 義男 田中 勇作 林 栄吉
常務取締役 桜木 マサヨ
<業種>
スポーツ/フィットネスジムの運営
<事業内容>
会員制総合スポーツクラブの運営
公共スポーツ施設の運営受託
企業フィットネスの受託
スポーツ用品の販売
スポーツ関連施設のプランニング・コンサルティング事業
スポーツ幼稚園の経営 等
<企業沿革>
1968年 横浜市に資本金500万円にて設立
1969年 資本金を2,000万円に増資(田中 勇作が出資)
スイミングスクール「港アスレティッククラブ」オープン
1972年 資本金を5,000万円に増資
フィットネスジム事業の開始
1974年 スポーツ専門幼稚園「チャイルドマック」オープン
新館落成
コンピュータを導入
1975年 コンピュータで体力度、栄養度、ストレス度を評価・処方するシステムを完成/販売開始
1978年 資本金を8,000万円に増資
1979年 関西地区に大阪事業所を開設
1985年 自然食品レストラン「H-CARE」を開店
1987年 アクアビックエクササイズ開始
スポーツ/フィットネス用品販売を本格化
1989年 資本金を1億2,000万円に増資
厚生大臣認定健康増進施設認定
1990年 「港北区健康増進センター」受託開始
1998年 Webサイト開設
2002年 資本金を2億円に増資
2007年 指定管理者8施設の受託開始
2008年 「横浜事業所」、「大阪事業所」にラウンジを設置
沿革
港アスレティッククラブは、会員制総合スポーツクラブの運営事業で、元水泳選手の桜木源一郎が1968年に関東地区の郊外でスポーツ用品メーカーの支援のもと、大学時代の先輩と創業した。その後、関東地区で事業を拡大し、関西地区も含め、全国で7事業所を持つようになった。桜木社長は、従業員教育にも力を入れており、正社員の多くは厚生労働省認定や文部科学省の公的資格を持っている他、従業員の態度やマナー、指導力、接客サービスの定期研修も取り入れている。創業時はスイミングスクールが主な事業であったが、1960年代に、郊外に大手企業の社宅が建設されたことから、福利厚生の一環で法人契約が伸び、1970年代は、フィットネスジムの運営やスポーツ専門幼稚園の設立、スポーツ/フィットネス関連商品の販売を開始するなど事業が拡大した。さらに、新規法人会員契約の伸びが鈍化したことから、法人向け営業の強化を図ったが、契約数が大きく伸びることはなかった。法人契約会員は、契約企業の業績に左右されることが多いため、長期的な契約がほとんどなかった。また、法人契約会員が退会すると、一社あたりの売上高に占める支払額の割合が高いため、売上減少の大きな要因となった。これにより、1980年代には個人契約会員の獲得に力を入れチラシ配布や地方局でのCMを行った結果、多くの個人契約会員獲得に繋がった。
1990年代になると、港アスレティッククラブは、主に個人契約会員の継続契約を重要視するようになり、会員にとって、生涯のパートナーとして認めてもらえる「地域に根ざした事業展開」を始めた。その施策は顧客満足度を高めることを目的とし、直接的には、社内勉強会をはじめ、専門家による外部研修を積極的に採用し、スタッフ、トレーナー、インストラクターの資格取得の奨励や、マナー、指導力、接客サービスなどの向上を目的とした従業員教育に力を入れることであった。さらに、インターナル・マーケティングにも力を入れ、表彰制度の導入や事業に貢献した従業員に休暇や旅行などのインセンティブを与えるなど、間接的に顧客満足度向上を図る施策も実施した。当時の業界では、バブル崩壊の影響で、法人会員企業の福利厚生の見直しによる退会が相次ぎ、経営不振に陥るクラブが続出した。さらに業界全体での事業再構築の一環として、中小クラブの営業権を大手クラブが買収・譲受するかたちでの整理統合が始まった。港アスレティッククラブも法人契約会員は減少したが、「地域に根ざした事業展開」が会員に受け入れられ、法人契約会員から個人契約会員に切り替える契約者が増えたことで事業が支えられた。2000年頃からは、ダイエットやアンチエイジングを始めとする健康ブーム、さらに、いわゆる「メタボリック症候群」が騒がれていることから、個人契約会員の契約者数の増加が目立っている。
港アスレティッククラブは、関東と関西に中心となる2つの事業所(横浜、大阪)があり、スイミングプールやトレーニングジム、ダンススタジオを備えている。残りの5つの事業所ではダンススタジオのみの運営を行っている。すべての事業所が最寄駅から徒歩15分程度の場所に立地している。会員のトレーニング内容の相談や経過診断については、各事業所内に診断室を設け、トレーナーによる診断が行なわれ、診断書を発行している。会員の構成比は、創業時からの会員が多く、40歳以上の占める割合が50%を超えている。幼少期に入会し社会人となっても通い続ける30歳代の会員も多い。また、「山歩き倶楽部」、「健康・旅クラブ」や「ゴルフコンペクラブ」など、会員によるいくつかの同好会があり、会員からの支持も高い。売上高の内訳は、年・月会費による収入が全体の70%を超えており、レストラン運営やスポーツ/フィットネス用品の販売、施設利用料などの収入が売上高に占める割合は、それぞれ5~7%である。
最近の動向
現在は、景気回復の兆しがあったことから法人契約会員の増加をはじめ、個人契約会員も増えてきている。港アスレティッククラブの会員特徴としては、10年以上継続契約をしている会員が多く、既存会員からの紹介で入会する会員の割合も高いことから、同業者の中ではシニア層の取り込みが、僅かではあるが成功している。今年4月には、コミュニケーションを重視する会員のために、横浜店と大阪店に広くてゆったりしたラウンジを増築した。
港アスレティッククラブは、入会金が他社に比べ高め(個人:30万円、法人:100万円)との指摘が会員からあり、会員種別による料金の見直しを行い、サラリーマンやOL向けに「ナイト会員」、シニア向けに「モーニング会員」、家族会員向けに「ホリデイ会員」を設け、気軽に会員登録をしやすい環境をつくった。しかしながら、新規会員の増加に比例するように退会する会員も増えてきており、特にサラリーマンやOLなど若年層会員の入れ替わりが目立っている。会員種別による施設の稼動状況は、「ナイト会員」の稼働率に波があり、混雑している日と空いている日があり一定ではない。また、「モーニング会員」や「ホリデイ会員」については、60%程度の稼働率で余力が残っている。
港アスレティッククラブの販促費の予算は前年の売上を基準に4%前後となっており、パンフレット作成の他、新聞折込チラシ、駅前でのチラシ配布、地域広報誌への広告出稿、フリーペーパーへの出稿、Webサイト運用費など、人件費も含まれている。以前は、新聞折込チラシを行なった際には、入会希望者などからの問い合せが多かったが、最近は、以前ほどの問い合せは無くなってきている。チラシは、健康情報やイベント情報を載せ配布している。販促を目的としたイベントは、「施設の無料開放」や、「無料体力測定の実施」など、主に町の祭りなどのイベントに合わせ実施するものであるが、あまり効果は出ていない。
最近、私鉄系列の大手スポーツジム「横鉄スポーツ」が横浜事業所の最寄り駅から5分程度の場所に進出してきており、その影響を桜木社長は気にしている。業界誌によるとスポーツ/フィットネスジム業界では、インターネットからの申込による新規会員が増えていると掲載されていた。横鉄スポーツは、インターネットからの申込による若年層会員の獲得を大きく伸ばしている。さらに若年層の新規会員は、好きなトレーニングには盛んに取り組みを行なうのに対し、関心の低いトレーニングに対する取り組みは控える傾向にあることから、横鉄スポーツは、人気のあるトレーニング器具を選別し20台程導入した。さらに、会員の施設利用履歴や体力測定記録を中央データセンターで管理し、事業所内に設置されている専用端末による、トレーニング診断サービスを提供している。横鉄スポーツの会員は、流行に左右されることが多く、会員定着率が低いとのことである。また、地域の特性に合わせたイベント等を行なっていない。シニア世代のスポーツ/フィットネス需要の高まりから、横鉄スポーツでは、シニア会員制度や高齢者向けのプログラムを導入し、中高年層の会員獲得について動いている。現在、横鉄スポーツには、港アスレティッククラブの元会員が新たに入会し、さらに従業員の転職が見受けられ、港アスレティッククラブ従業員の間では動揺がはしっている。
港アスレティッククラブでは1998年にWebサイトを開設し施設紹介やトレーニングコースの紹介を行なっている。インターネットでの情報公開により、入会希望者が事前にサービス種類や内容を調べてくるケースが多く見られる様になったが、サイトアクセス数については、開設以来横ばいである。さらに2003年から、インターネットによる若年層をターゲットとした会員の募集を行なっているが、インターネット経由での新規個人会員の獲得は少ない。また、インターネット経由で入会した会員は定着率が悪く、施設の利用頻度も少ない。以前は、メールマガジンで「フィットネス・ワンポイントメモ」や「食事ガイド」などの情報を配信していたが、配信希望者のメールアドレスが集まらなかった。その後、個人情報保護法施行のこともあり、2004年末をもってメールマガジンを廃止している。
スポーツ/フィットネス関連商品の販売は、事業所内に設置された店舗で行なわれており、売上の多くは、シニア層による高級商品の購入で賄われている。3年前にはスポーツ/フィットネス関連商品のECサイトを開設したが、購入者は若年層がほとんどで、型遅れのバーゲン品が多く売れるだけであり、利益への貢献は少ない。
ビジョン
最近、会員に対しアンケートを行った。結果は、「家族的な付き合いが良い」、「友人ができた」、「腰痛が治った」との良い意見の他、「施設が混雑している」、「施設の空き状況が解らない」、「欲しいフィットネスグッズが見つからない」、「トレーナーの出勤日がわからない」などの不満も見られた。桜木社長はアンケート結果から、特定の時間帯に特定の設備が混雑していることが問題と捉えており、会員退会の原因になりかねないことから対策を模索している。しかしながら、ラウンジの増築もあり新たな設備投資は控えたい意向を持っているが、経営効率をふまえ施設の稼働率の向上を図りたいと考えている。
桜木社長は、地域に根ざしたクラブ運営が重要であり、地域の発展と共に「港アスレティッククラブ」を成長させたい考えである。その為には、出来る限り会員に対し便宜を図り、また、地域クラブの枠を超えた関係作りに力を入れたいと考えている。さらに、港アスレティッククラブでの活動を通し、人の成長に合わせた人間形成を行うことが、会員にとって意味あるクラブの付加価値であるとの考えから、会員には「私のクラブ」という意識を持って欲しいとの思いが強い。
昨今では、医療費抑制の有効な手段として、「セルフメディケーション」が脚光を浴びつつあることから、社長が中心となり企画を行い、従業員の「健康運動指導士」や「管理栄養士」の資格を活かした「健康セミナー」など、新サービスの実施に向け準備をしている。
また、桜木社長を若い頃から支えている役員が、スポーツ用品メーカーの会長を兼任していることから、スポーツ/フィットネス関連商品の仕入れや品揃えには自信がある。桜木社長は今後、ECサイトを中心とした、商品販売事業に力を入れ大きな収益の源にしていきたいと考えている。
現在、「体の健康」「心の健康」「人間関係の育成」の3つの柱を軸とし、充実したサービスの提供を前提とした新たなビジョンを桜木社長はまとめようとしている。
ご注意
本試験時点では、上記文書のほか、「財務諸表」、「参考資料(Webページの抜粋、ニュース記事)」などが配布されます。