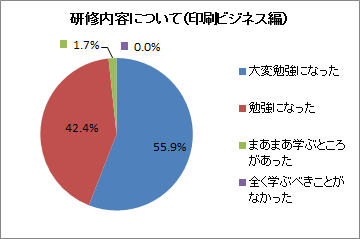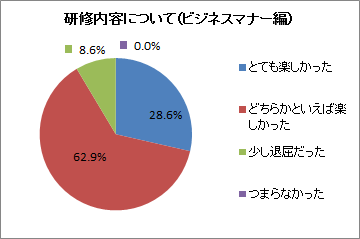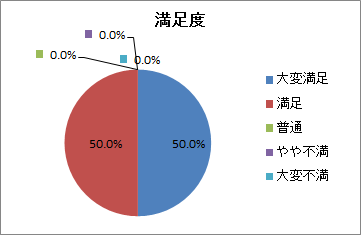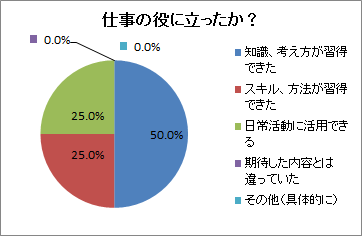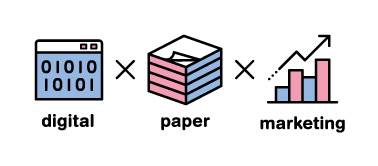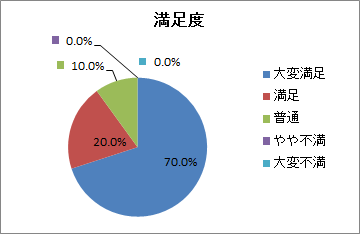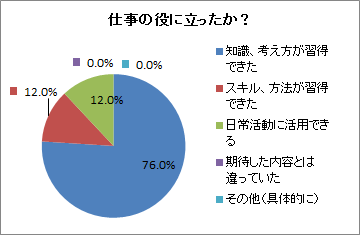インターネットの出現により、マーケティングにおいて革命ともいうべきデジタルシフトが起こっています。印刷業界はこうした現実にどのように向き合い、対応していくべきか。
JAGAT九州地区の集い
JUMP九州2019&ジョイントセミナー
2019年10月19日(土)開催
会場:福岡印刷会館
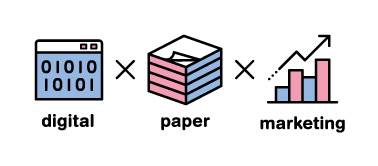

インターネットの出現により、マーケティングにおいて革命ともいうべきデジタルシフトが起こっています。
印刷業界はこうした現実にどのように向き合い、対応していくべきか。
JAGATは昨年来、世の中のデジタルシフトが進展する中で印刷のビジネスチャンスを切り拓くためには、デジタルVSアナログの二極対決路線ではなく、マーケティング情報と印刷の連携・融合が必要であるとし、“デジタル×紙×マーケティング”をスローガンとして掲げています。
今回のJUMP九州では、このテーマをさらに追及し、よりビジネスに直結させて“飯のタネ”となるよう、豊富な実践例を交えて情報提供するとともに、新たな印刷の成長戦略を考える場として展開いたします。
主催:公益社団法人 日本印刷技術協会 協力:九州地区印刷協議会
JUMP九州企画推進メンバー *五十音順・敬称略
池田 輝幸[南日本印刷材料(株)]/ 岩永 健[(有)正文社印刷所]/ 江口 正悟[(株)ディーエスエー]大迫 雅浩[(株)宮崎南印刷]/ 尾形 晴義[(有)文化プロセス]/ 笠木 信吾[極東印刷紙工(株)]木下 直哉[西部印刷企画(株)]/ 儀保 至[丸正印刷(株)]/ 藏原 宏行[(有)藏原印刷]
古賀 照也[アド印刷(株)]/ 貞末 宏治郎[(株)博巧印刷]/ 下地 義人[みなみ印刷]/ 森山 昴紀[(株)九大印刷]
————————————————————————————————————————————
JUMP九州2019ジョイントセミナー
“ デジタル×紙 ” を武器に経営戦略に新たな一手を!
「新たな売上構築に導くデジタル戦略と印刷会社の役割」
~印刷会社だからこそできる“デジタル×紙”の推進~
開催日時
10月19日(土)10:30~12:30
対象
経営者および経営幹部、各部門管理者・リーダーなど
講師
 後藤 佑紀 氏
後藤 佑紀 氏
(株)アイディーエイ
デザインコンサルティング部セクションリーダー/デザインコンサルタント
主旨
経産省と特許庁が昨年「デザイン経営」宣言を出して話題となりました。それは、デザインを活用した経営手法により、ブランド力向上とイノベーション力向上を通じて企業競争力の向上を図るものとされています。規模の大小を問わず、世界の有力企業がデザインを戦略の中心に据えており、実際に成果を上げていますが、日本ではまだ経営者がそれを有効な経営手段とは認識していないと問題提起しています。
本講座では、その重要性に注目が集まっているUXDESIGN(UX=User Experience・ユーザエクスペリエンス)、すなわち「ユーザー体験をどのように作るか」をO2Oで考える内容となっており、自社の競争力を高めると共に、顧客のブランド戦略に貢献するための武器を身につける機会としてご提供します。
紙以外の売上構築を“デジタル×紙”の活用で考えましょう。
主な内容
・印刷会社になぜデジタル戦略が必要なのか
・UXDESIGNとは ※UX=User Experience
・ブランド戦略型WEBデザインとは
・デジタルと印刷の融合 O2Oを可視化する
(戦略マップと顧客感動、ユーザー体験の可視化)
・デジタル戦略事例紹介
・ワークショップ:戦略マップの作成方法
JUMP九州2018ジョイントセミナー参加申込要項
■会場:福岡印刷会館
福岡市博多区築港本町6-1 TEL092-271-2700
■参加費:JAGAT会員、九州地区印刷協議会傘下組合員 7,700円(税込)
◆1社でセミナー、JUMP両方参加の場合(セット特別割引)
・ジョイントセミナー 6,160円(税込)/JUMP九州 7,040円(税込)
*両方お申込みの場合、参加者は別の方でも何名様でも割引価格を適応します
例)1社でセミナーに2人、JUMPに2人の場合6,160円×2+7,040円×2=26,400円
■お申込方法:
申込欄に必要事項をご記入の上、そのままFAXにてお申込みください。お申込みと同時に参加費をお振り込みください。お申込確認後に、参加票を送らせていただきます。
*お申込み後の取消はお受けできません。恐縮ですが代理の方の参加等でご対処ください。
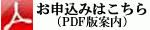
お申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。
● 振込先・・・・・・・・シャ)ニホンインサツギジュツキョウカイ
● 口座・・・・・・・・・みずほ銀行中野支店(普)202430
● お申込み締切・・・・・2019年10月16日(水)
● 内容問合せ先・・・・・日本印刷技術協会JUMP2019事務局 03-3384-3112
————————————————————————————————————————————
JUMP九州2019
“デジタル×紙×マーケティング for Business”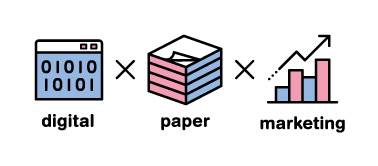
for Business
■開催日時:10月19日(土)14:00~19:10
■プログラム:
※記載内容は諸般の事情により変更される場合がございますので、予めご了承ください。
オープニング
14:00~14:15 |
【開会の辞】
大迫 雅浩 氏
JUMP企画推進メンバー代表/(株)宮崎南印刷 代表取締役社長
【ご挨拶】
塚田 司郎
JAGAT会長/錦明印刷(株) 代表取締役社長 |
|
JAGATからの報告
14:15~15:00
|
「印刷ビジネスの最新動向2019」
解説:藤井 建人 JAGAT研究調査部部長
最新動向を産業・市場・メディア・経営の4視点からデータで捉えるとともに、印刷ビジネス周辺のトレンドについても解説。業界と印刷経営の将来を考えます。
|
| 休憩 15:00~15:10 |
|
特別講演
15:10~16:30
|
「実践!デジタル×紙×マーケティング
~今こそ印刷ビジネスの新たな利益の源泉を発掘しよう」
解説:本間 充 氏
アビームコンサルティング/アウトブレインジャパン 顧問
デジタル×紙×マーケティングの必要性は、理解されました。では、この領域に展開する場合、どのような事業があるのでしょうか?また、広告主、事業主は、現在の印刷・紙で、できることをきちんと知っているのでしょうか?広告主、事業主と向き合うことで、「デジタル×紙×マーケティング」はどの印刷会社もできます。そのヒントとアイディアについて、豊富な事例を交えながらお話ししていただきます。
<主な内容>
(1)復習「デジタル×紙×マーケティング」
(2)デジタル×紙×マーケティング実践例
(3)問題は、印刷会社にも、お客様にも
(4)未知・未踏の領域「デジタル×紙×マーケティング」
|
| 休憩 16:30~16:40 |
|
総括
16:40~17:10
|
本間 充氏 × 郡司 秀明 for Business
JAGATが提唱する“デジタル×紙×マーケティング ”の本質とは何かをJAGAT専務理事の郡司が解説しつつ、本間氏との対話を通じて、今後の印刷業界が利益を生み出すために何をすべきか、進むべき方向性について展望します。
|
|
情報交換会
17:50~19:10
|
懇親パーティー
*懇親会会場:福岡サンパレス
|
■会場:
【JUMP九州2019】福岡印刷会館 福岡市博多区築港本町6-1 TEL092-271-2700
【懇親会】福岡サンパレス 福岡市博多区築港本町2-1
■参加費:
JAGAT会員、九州地区印刷協議会傘下組合員
【JUMP九州2019】 8,800円(税込)
◆1社でセミナー、JUMP両方参加の場合(セット特別割引)
・ジョイントセミナー 6,160円(税込)/JUMP九州 7,040円(税込)
*両方お申込みの場合、参加者は別の方でも何名様でも割引価格を適応します
例)1社でセミナーに2人、JUMPに2人の場合6,160円×2+7,040円×2=26,400円
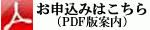
お申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。
● 振込先・・・・・・・・シャ)ニホンインサツギジュツキョウカイ
● 口座・・・・・・・・・みずほ銀行中野支店(普)202430
● お申込み締切・・・・・2019年10月16日(水)
● 内容問合せ先・・・・・日本印刷技術協会JUMP2019事務局03-3384-3112
 宮本 泰夫 (株)バリューマシーンインターナショナル 取締役副社長
宮本 泰夫 (株)バリューマシーンインターナショナル 取締役副社長