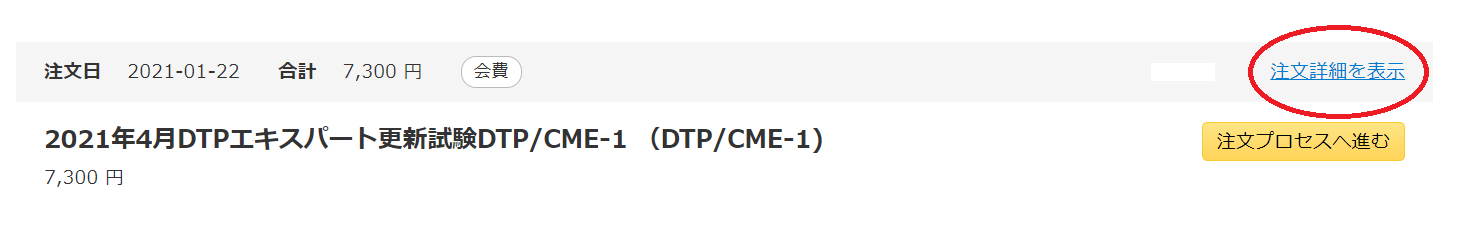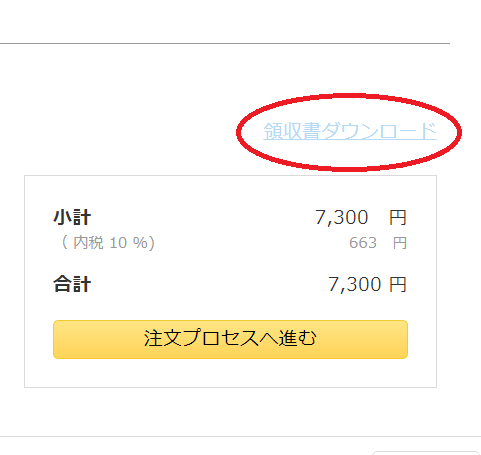コロナ禍による「緊急事態宣言」が初めて発出されたのは2020年4月であり、それから1年余が過ぎた。外出自粛や大規模イベントの中止など、生活者への影響は多大なものとなっている。一方、このような状況下で成長しているビジネスもある。
利用が急増したフードデリバリーサービス
例えば、フードデリバリーは、スマートフォンからメニューを選び、注文するだけで、自宅まで配送してもらうサービスである。複数店舗のメニューを一覧し、注文できる出前・宅配のWebサイトは、10年以上前から存在していた。しかし、2016年にUber EATSが日本に上陸したことで脚光を浴び、フードデリバリー市場全体の活性化につながった。
それまで「出前を頼む」となると、自宅や職場にあらかじめ保管された「メニュー表」の中から食べたいものを選び、直接、飲食店に電話で注文する必要があった。しかし、出前を受け付ける飲食店や対象地域はかなり限定されており、近所の中華料理店・蕎麦店などの一部である。それ以外では、ピザや寿司の宅配専門店程度であった。
現在のフードデリバリーサービスは、 飲食店にとって 追加投資なしに注文を受けることができ、売上を増やせる機会である。事前にメニューを印刷して、近所に配布することも必要ない。注文時の電話対応や配達、料金を受け取るために釣り銭を用意することも不要で、デリバリーサービスが代行してくれる。
スマートフォンのアプリでは、近隣でデリバリー可能な店舗とメニューが一覧表示され、利用者は幅広い中から好きなものを簡単に注文することができる。
そして、2020年より巣ごもり需要などで、利用者・登録店ともに急増し、フードデリバリー市場全体が拡大する状況となっている。当初は、スマートフォンやネットショッピングに馴染みのある若者が中心とされていたが、ファミリー・高齢者世帯など幅広い年齢層の利用が増えているようだ。
ネットスーパーと食材宅配ビジネス
同様に、2020年に市場が拡大したものに、ネットスーパーと食材宅配サービがある。
ネットスーパーは、自宅からスマートフォンのアプリで注文するだけで、買い物を済ませられるサービスである。宅配や店舗受け取りなど、配送方式も多様化している。外出自粛などの影響で、新規登録者数が2倍から3倍に伸長した事業者もあるという。
食材宅配サービスは、生活者のライフスタイルや年齢層に合わせたセットを用意し、さまざまなニーズに応えている。たとえば、栄養バランスや減塩などに配慮した健康サポート食品、子育て世帯に向けた離乳食・幼児食シリーズや忙しい主婦の手間を減らす簡単料理パッケージなどもあり、多くの支持を集めている。
コロナ禍によって、レストランなどで外食する機会が減少している。そのため、自宅で調理を行う内食(ないしょく・うちしょく)、惣菜や弁当などを購入して自宅で食べる中食(なかしょく)の需要が大きくなっている。
食材調達を担うネットスーパーや食品宅配サービスの進化によって、生活者の意識と行動スタイルは大きく変化していくだろう。一過性の現象と見る向きも多いが、多様な年齢層の利用者が増えており、今後も定着していく可能性が高いといえる。
変化に適応することの重要性
フードデリバリーサービスやネットスーパー・食材宅配サービスは、以前から存在はしていたが、それほど大きな潮流とまではいえないものであった。
しかし、生活者の行動様式が変化したことで浸透し、定着しつつある。イノベーター理論でいうアーリーアダプター(新製品や新技術、流行に敏感で自ら判断し購入する層)から、アーリーマジョリティ(新製品に慎重で価格・品質を重視する層)に進展したといえるのではないか。
このような行動様式は、コロナ禍が収束したとしても、定着すると考えられる。このような変化に常に注意を払い、適応していくことが必要といえるだろう。
(JAGAT 研究調査部 千葉 弘幸)