今回は「ひじわ」について取り上げる。 続きを読む
「協会情報」カテゴリーアーカイブ
経営に直結する戦略思考とは?
8月22日(木)、23日(金)に日本印刷技術協会本社で開催する「JAGAT Summer Fes 2019(夏フェス2019)」で実施いたします特別講演では、管理職及びマーケティング担当者様向けと、経営者の方々に聴いていただきたい講演タイトルをご用意しました。
マーケティング活動を通じて学ぶビジネスの原点を異なる2つの視点から
企業の管理職・マネジャー、またマーケティング担当者の方々に聞いていただきたい特別講演セッションのご紹介です。
「翼を授ける」のキャッチコピーでおなじみのエナジードリンク「レッドブル」。創業者のディートリッヒ・マテシッツは、「我々のための市場は存在しない。我々がこれから作るのだ。」と宣言しました。レッドブルのマーケティング戦略は、プロスポーツチームの買収や、新しいカテゴリのスポーツイベントの開催など、独創的なイメージが先行していますが、その原点はどの企業にも共通する「市場の創造」でした。そしてこれらの施策を通して、自社商品の販売だけでなく、よりよい顧客体験を提供することで、長期的なブランド価値向上につなげ、市場の創造を成し遂げたのでした。今まで語られることがほとんどなかった物語を、元レッドブル・ジャパンマーケティング本部長の長田新子氏に語っていただきます。
いつの時代も「優良顧客との良好な関係構築と維持」にマーケターは頭を悩ませてきました。現在、様々なデジタルマーケティングツールを活用して行われている施策の原点が、三越の「お帳場制度」にありました。三越における最上位顧客と呼ばれる「帳場前主」には、「扱者(あつかいしゃ)」と呼ばれる担当が付きます。扱者は、帳場前主の「タンスの中まで知っている」と言われるほど、顧客との関係は深いものでした。バブル崩壊とそれに伴う百貨店不況により、顧客との関係構築が見直され、帳場制度を現代風にアレンジして作られた三越日本橋本店お得意様営業部では、地道な施策を繰り返し、様々な試行錯誤を経て、既存顧客からの売上向上を成し遂げました。同組織のマネジャーとして、数々の実績を残した鈴木一正氏に、究極のONE TO ONEマーケティング施策についてお話しいただきます。
どちらのセッションも、ここでしか聞けない貴重なお話です。
【管理職・マネジャー・マーケティングご担当者様向け】特別講演>
「市場を創造するということ ~レッドブルが日本にもたらした変化とは」
(8/22(木)10:00~11:00 )
元 レッドブル・ジャパン マーケティング本部長 現 一般社団法人 渋谷未来デザイン 長田新子
「タンスの中まで知る」伝説のONE TO ONEマーケティング
(8/22(木)11:20~12:20 )
元 三越日本橋本店お得意様営業部マネジャー 現 お得意様育成事務所スズセイ 代表 鈴木一正
上記のセッションのご登録は、こちらからお願いいたします。
経営活動に直結する戦略思考と組織改革の実例を学ぶ
企業の経営者、役員の皆様に聴いていただきたい特別講演セッションのご紹介です。
「戦略」とは何か?ビジネスパーソンにとって魅力的な響きを持つこの「戦略」という言葉に対し、「なぜ『戦略』で差がつくのか。-戦略思考でマーケティングは強くなる」の著者である音部大輔氏は、「戦略とは、目的達成のために資源をどう利用するかの指針」と、明確に定義付けています。つまり、達成すべき目的があり、かつ資源が有限である時に必要となるのが戦略であり、売上を向上させるために実行するのが販売戦略、経営上の目的達成のために行うのが経営戦略となります。本講演では、戦略を正しく理解し、思考の道具として活用するための考え方を学びます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)によって顧客の購買行動の劇的な変化し、その傾向はBtoCだけではなくBtoBにおいても顕著になっています。3年前に半導体メーカーのインテルから横河電機に移籍した阿部剛士氏は、「DXに対応するため、マーケティングの力で会社を変えてほしい。」という経営陣からの依頼を受けて、組織の改革に着手しました。今、横河電機のマーケティング部には、営業部門だけでなく、工業デザインやR&Dセンター、さらには知財部門までも入っており、いわば1つの企業体に近い状態です。その結果、意思決定のスピードは劇的に早まりました。こうしたマーケティング活動を経営活動そのものと捉える考え方は、中小企業にこそ当てはまるものといえます。聴いたその日から、ビジネスのヒントが見つかる講演ですので、ぜひお聴きいただきたいと思います。
現代のスポーツ新聞を再発明する
今年9月のラグビー・ワールドカップ、そして来年には東京オリンピック・パラリンピックを控え、日本のスポーツ界が盛り上がってゆく大きなチャンスが到来しました。スポーツは「やる人」「見る人」「応援する人」など多くの人を一つにする力があり、健康寿命が延び、可処分時間が延びている中ますます多くの人がスポーツに関与することになります。
スポーツ新聞社は、自社の発行する新聞だけでなく、webサイトからの速報性の高い記事発信ゴルフやマラソンなどの各種スポーツ大会の主催、後援、協賛といった活動を行っています。これらの様々な資産をDXが進む現代に即した形で活用すべく、新たにスポーツニッポン新聞社のCDOに就任した江端浩人氏の考えるスポーツ新聞の再発明とは?デジタルマーケテイング界きっての実績と知見を持つ同氏の取り組みを語っていただきます。
<【経営者・役員向け】特別講演>
「戦略思考で考えるジャイアントキリング」
8月23日(金)10:00~11:00
クー・マーケティング・カンパニー 代表 音部大輔
「デジタル×スポーツ×マーケティング」
8月23日(金)11:20~12:20
江端浩人事務所 代表 スポーツニッポン新聞社 特任執行役員 CDO 江端 浩人
「デジタル・トランスフォーメーションとマーケティング ~デジタル時代におけるB2Bマーケティングの戦略と組織」
8月23日(金)14:10~15:10
横河電機株式会社 常務執行役員 兼 マーケティング本部長 阿部剛士
これらのセッションのご登録は、こちらからお願いいたします。
ご参加お待ちしております。
(JAGAT Summer Fes 2019事務局)
印刷業定点調査 各地の声(2019年3月度)
3月の売上高は△0.6%。2月のプラス(+0.3%)からマイナスに転じたが、微小な変化であって実質的には2カ月連続で±0の前年同水準であったと見て良いのではないか。 続きを読む
第30回 国際 文具・紙製品展 ISOTに見る2019年の文具トレンド
第30回 国際 文具・紙製品展 ISOTと第28回 日本文具大賞の結果から、印刷業界に関わりのあるトピックを紹介する。
ライフスタイルに生きる、紙ものたち
2019年7月17日(水)から19日(金)に開催されたインテリア・デザイン市場のための国際見本市「インテリア ライフスタイル」では、紙素材や印刷・製本加工技術を応用した製品も多数発表された。
印刷会社の持続的な成長のための経営幹部育成
10年後にどれだけの企業と仕事が今と同じ形で残っているだろうか。以前、話題になった2013年発表のオックスフォード大学のカールフレイ氏らの論文「The Future of Employment(雇用の未来)」よれば、コンピューター・AIによる技術革新によって必要とされる職業が大きく変わる。無くなる職業のトップ5が<1位>テレマーケター(電話を使った販売活動)、<2位>不動産の権原検査員、権原抄録者、権原調査員 <3位>手縫いの裁縫師<4位>数理技術者、<5位>保険事務員となっている。例えば、従来、私は、単純労働が無くなるようなイメージを持っていたが、これらの技術革新が出現後の変化の有り様はまったく違う。現在はどうであろうか。
経済産業省の企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン(2017年3月)では、近年、IoTやAI・ビッグデータが圧倒的なスピードで進化し、あらゆる分野で実用化され始めている。経営環境の変化の中で企業の競争力を強化し、成長を実現することは大きな課題となっている。次世代の経営に携わる人材育成は急務とされている。
また、同省の調査・研究の一環として実施したアンケート調査によれば、経営リーダー人材候補の育成を目的とした何らかの取り組みをしている企業は、52.6%と過半数を占める。対象者の現在の役職は、「部長クラス」が 88.2%ともっとも多く、「課長クラス」が 58.8%となっている。また、経営リーダー人材の育成状況については、順調に確保・育成できていると認識している企業は 37.6%にとどまり、経営リーダー人材育成の取組みをしている企業においても、52.9%が不安であると回答している。候補者はいるという企業は 36.6%あるものの、5 年後の候補者が不足しているとする企業も29.7%存在している。経営リーダー人材育成の確保・育成は、多くの企業において課題となっている。
企業の支えるのは「人」である。印刷会社においても次世代で中心的な役割を果たす経営幹部の多くは、ビジネスの現場で原動力になっているミドルマネージャーである。日々の営業活動や製造業務などに追われていることが現状のようだ。経営判断で戦略的に経営幹部育成に取り組む必要がある。企業の持続的成長に決定的な影響を与え、競争力を継続的に向上させるためにはミドルマネージャーの経営幹部としての成長が鍵を握る。
CS部 古谷芸文
<関連講座>
●第36期印刷経営幹部ゼミナール(2019年9月リニューアル開講)
https://www.jagat.or.jp/archives/61871
印刷経営幹部ゼミナール受講者の感想
これまで36期に渡り開催して参りました「印刷経営幹部ゼミナール」。34期受講者の株式会社きかんしの宿利秀海氏、35期受講者の昭和情報プロセス株式会社の中野正巨氏に、本ゼミナールの感想を伺った。
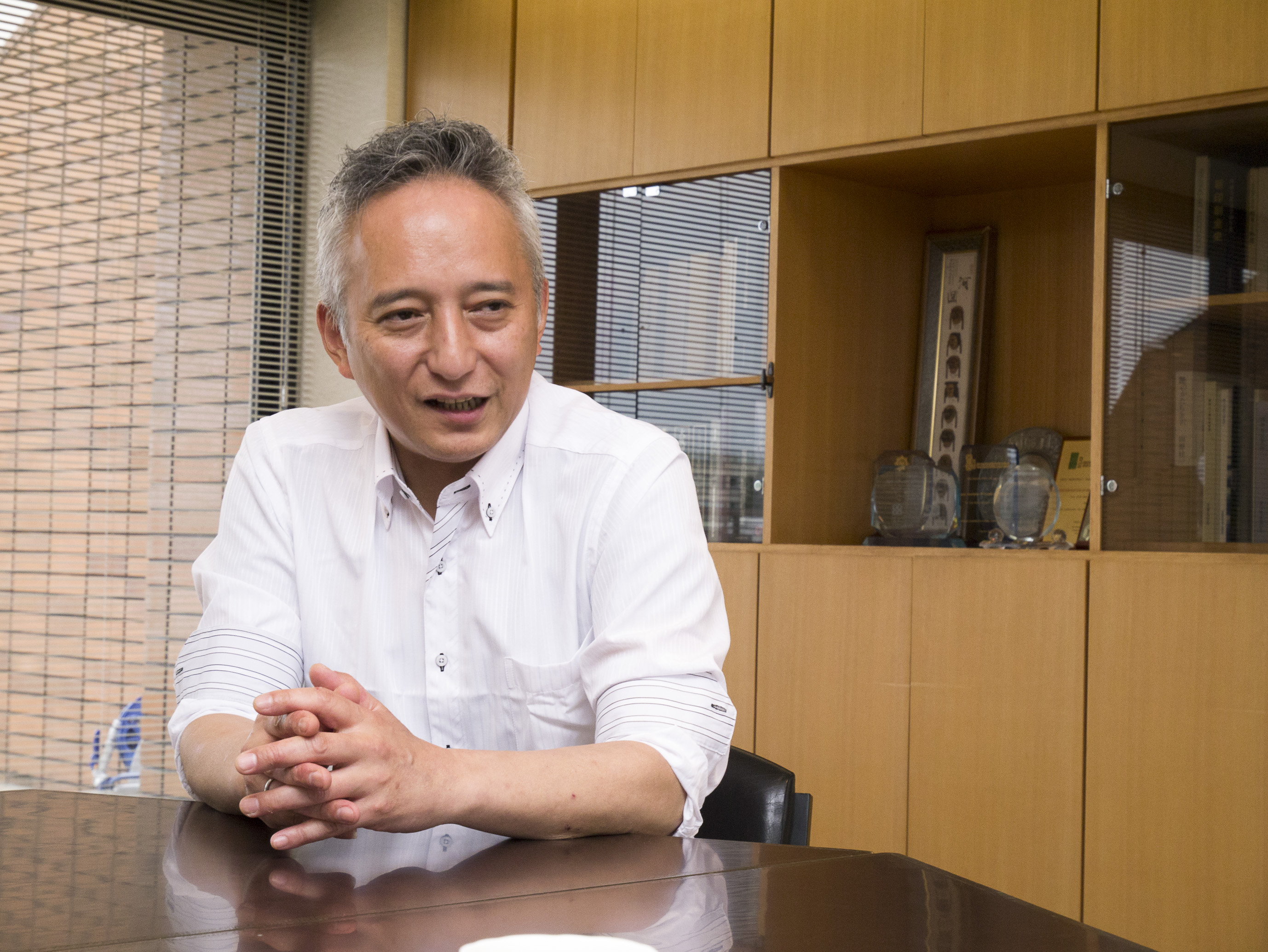
●第34期受講者 宿利秀海 氏 株式会社きかんし 取締役制作担当・制作部長
Q.1受講の動機は?
社長からの薦めです。ゼミが始まる1 カ月程前に、社長から直接声をかけてもらい受講を薦められた。当時から制作部門の取締役の任に就いており、経営幹部として、それなりに経験年数を重ねていたため、最初は今さら幹部育成講座を受ける意味を模索していた。しかし、経営幹部としてのキャリアを積み、問題意識を持った上で参加したからこそ、ゼミの内容と自社の経営をリンクして考えることができたため、結果として受講のタイミングは良かった。
Q.2学べたことは?
営業、製造、財務会計、法務、人事等、経営全般の必須知識全般を学べたことはもちろん、自社とは異なる事業やビジネス展開を知る中で、他社にない自社の強みを再認識し整理することができたのは大きい。特に、製造原価の管理手法や人事評価制度等、本来なら見せてもらえない他社の取り組みについて知れたことや、ダイレクトマーケティングやクロスメディアの事例等、トレンドをつかめたことも参考になった。
Q.3学んだことを実務にどう活かしたか?
講義内容や事例をそのまま真似するのでなく、自社の特長や強みを考慮して、アレンジして取り入れることを意識した。当社の強みでもあるプロモーションツールの制作力に企画提案力をプラスアルファすることで、請負受注型のスタイルから、課題解決策の相談に対応する提案型のスタイルに移行しつつある。今後はより提案型の顧客対応や組織体制づくりの構築を図っていく。
Q.4 自社と自分自身の成長に向けての抱負は?
立場と年齢的にもゼミで学んだことを同僚や部下と共有することを意識している。例えば人材評価制度については、その手法よりも人材育成における考え方や価値観として参考になった。社員の働き方や能力を適切に評価する上で、部下との関わり合いや見る目が重要だと再認識した。社員の特徴を見極め、その才能を仕事を通じて引き出していく。部下、自分、自社の相互成長の課題に取り組んでいきたい。これからの重要な経営課題として捉えている。

●第35期受講生 中野正巨 氏 昭和情報プロセス株式会社 営業部課長
Q.1受講の動機は?
上司からの推薦これからの経営幹部として経営や財務知識を学ぶと共に、他社との交流を通じて視野を広げるためにと、社長からの勧めもあった。
Q.2学べたことは?
現役経営者の実践的な話が聴けて良かった。特に印象に残っていることは「他社がしていないことをやる、やり続ける、やり続ければ認知される」という言葉が刺さった。自社の特徴を活かし、チャレンジし、やり続けることの価値を知った。
Q.3学んだことを実務にどう活かしたか?
原価計算と“ 見える化” は、特に意識するようになった。自社の営業目標のひとつとして加工高比率を重要視している。財務の視点を部下に浸透させる上でも知識は役に立つ。自社の強みを活かした「勝者の営業・弱者の営業」について意識し顧客対応に心がけている。
Q.4 自社と自分自身の成長に向けての抱負は?
日常業務に追われる中、ゼミで取り組む課題と業務の両立は厳しいものもあっが、今後の営業展開を考える良い機会になった。視野が広がることによって、面白みも見出した。今後に向けては、第一に、自社の強みを広い視野で捉え、魅力を顧客に伝える力を向上させる。第二に、営業として、顧客との関係を強化し、顧客に喜ばれるサービスを提供する中、ビジネスチャンスを広げていくことに取り組んでいきたい。
以 上
【関連講座】
「オンライン印刷経営幹部ゼミナール」2020年10月開講
出版流通の構造再編が迫っている
出版流通が変化の時を迎えている。取次大手と出版社との間では書籍出荷価格や運賃協力金についての交渉も始まった。背景となっているのは、出版インフラの収益源だった雑誌の売上減である。書籍中心の物流を再構築できるのか。また、電子書籍と印刷書籍との連動をいかに最適化するか。業界構造の再編は印刷会社にどのような影響を与えるだろうか。
再編される出版流通業界
書籍流通を改善する方策の一つにデジタル印刷を利用した適時生産が挙げられる。書店からの追加注文をデジタル印刷機で生産し納品、または出版社が小ロット重版を自ら生産するなど、様々な形で試験的な導入が始まっている。
定期的に大部数が印刷される雑誌に合わせて流通網を作り、そこに書籍を載せていくというのが、これまでの出版流通の考え方だった。しかし、今後は必要なものを必要なだけ作り、欲しい人が欲しい時に手に入れられる、タイムリーな生産・流通の構図を作り上げていくことが望まれている。
出版産業全体を見渡す視点が必要
こういった流れから言えることは分担されていた出版産業がその垣根を超えて連動する一体的なサプライチェーンの必要性が高まっているということである。これまではコンテンツを作る出版社、書籍・雑誌を製造する印刷会社、流通を担う取次、販売する書店と各段階が個別に業務を遂行してきた。しかし、今後は流通各段階の部分最適化に留まらず、各領域が横断され、業界全体で最適化していくことが求められてくる。
こういった包括的な変革が近い時は全工程を網羅するような視点を持つ企業の方が有利になる。そのためには、今まで以上に取引先との連携を深め、全体の動向に注視する必要があるだろう。印刷工程での負担と作業を少し増やすことで、出版売上が大きく改善される場合もある。そういったニーズを掘り起し、提案していくことも求められる。
今後の出版流通を占う
7月30日の研究会では、海外の出版流通の最新事業にも詳しいデジタルタグボードの辻本氏が今後日本にも導入されうる出版流通の仕組みについて解説する。その後、文化通信社の星野氏が出版流通が現在抱える課題と見通しについて語る。また、竹書房の竹村氏からは電子出版に強みを持つ中堅出版社の立場と全国の書店を視察した経験から、流通の現場が抱える課題と最適化のための提言、そして印刷会社に対する期待について語る。出版流通全体を考察する研究会になるだろう。
(JAGAT 研究調査部 松永寛和)
■関連イベント
出版ビジネスの最新動向2019~デジタルとの関係からみた出版流通の今後~
既存の出版流通が限界に近づいている。収益を雑誌に依存することで成り立ってきた出版流通インフラは、その前提を失った。取次と出版社との間で書籍出荷価格と運賃協力金についての交渉が始まるなど、取引慣行の見直しも含めた構造改革の動きも表れ始めている。本研究会ではデジタルタグボートの辻本氏に海外の出版事業をご講演頂き、今後の出版業界を考えるヒントをいただく。次に文化通信社の星野氏に現在の取次と出版社、書店の置かれた状況を解説していただく。
また、日本では電子コミックが出版社の収益を支え始めている事情もある。紙と電子の同時出版に強みを持ち、書店にも配慮しながら独自の存在感を強める竹書房の竹村氏に中堅出版社の立場からも出版流通の今後と出版社の再生について語っていただき、業界構造の再編を多角的に考察する。
2019/8/7 印刷物の品質基本セオリーを学ぶ お申込み
セミナー名:印刷物の品質基本セオリーを学ぶ
開催日:2019年8月7日(水)10:00~17:00
参加費:JAGAT会員:18,900円 一般:25,200円(税込)
→詳細案内ページ
・申込みは、下記のフォームに必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。
・申込フォームにメールアドレスを入力した後「Enter」ボタンを押すと、フォームの内容が送信されてしまいます。恐れ入りますが、「Tab」ボタンを使う、マウスを使うなどの方法で移動お願いします。
※ご注意ください※
本 メールにご登録いただくと、申込完了メールが送信されます。登録後、数分経ってもメールが受領できない場合は、迷惑メールフィルタ等の要因が考えられま す。その場合は、お手数ですが、メール(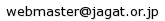 )またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。
)またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。
印刷ビジネスの本質が変わりつつある
今年で3回目になるJAGAT Summer Fesが、~デジタル×紙×マーケティングfor Business~というテーマで8月22日と23日に開催する。
印刷会社は、デジタルと紙を融合させたマーケティング施策を提供することでビジネスを創り出そうというものである。
印刷会社のビジネスを取り巻く環境はデジタル化社会になって大きく変わった。それはインターネットの普及、多メディア化の進展ということだけではなく、それに伴って生活者であるエンドユーザーの意識と行動が変化しているからであり、それに対応して印刷会社のクライント側の意識やニーズも変わっているからである。
当然、印刷会社の提供するサービスに対するクライアントの期待も変わるわけで、印刷物を提供することが第一義だった印刷ビジネスの本質が変わりつつあるのを感じる。
そのような状況で、印刷メディアで企業の情報伝達を支援してきた印刷会社が、これからはデジタル×紙×マーケティングを駆使することによって顧客の期待に応えるサービスをビジネスにしていくことが一つの解となるだろうというのがJAGATの思いである。
デジタル×紙×マーケティングでビジネスをする場合に最も重要になるのが、プロデュース、ディレクション、オペレーションしていく一連の人材だろう。
このような人材は印刷物を受注、制作することを主とする場合と比較して、求められる知識は幅広く、その能力も高い水準が必要にある。
そういった人材を育成していく一助となり得るのが、JAGAT認証クロスメディアエキスパート資格である。会員誌『JAGAT info 』では、この資格試験を受験する時に役立つものとして、JAGATエキスパート資格講座インストラクターの影山史枝氏による課題解決入門を連載している。
連載ではAIDMA・AISASのような購買行動モデルの解説から、ネットを活用したビジネスモデルの解説、AIやIoTとメディアビジネスの関係、ネットビジネストレンド、次々登場する新しいネットメディア等の紹介など、ネット戦略と印刷メディアの融合を意識した記事を掲載している。
この連載記事はクロスメディアエキスパート試験に役立つだけではなく、もちろん実際にデジタル×紙×マーケティングのビジネスを実行しようとする人たちにとっても、現在、これからのメディア活用を実践していくうえで参考になる。
『 JAGAT info 』では、これからも会員の皆さんに少しでも役立つことができる記事を提供していきたいと考えているので、本誌記事に対するご意見や感想をいただければ幸いである。
JAGAT info7月号の目次はこちら




