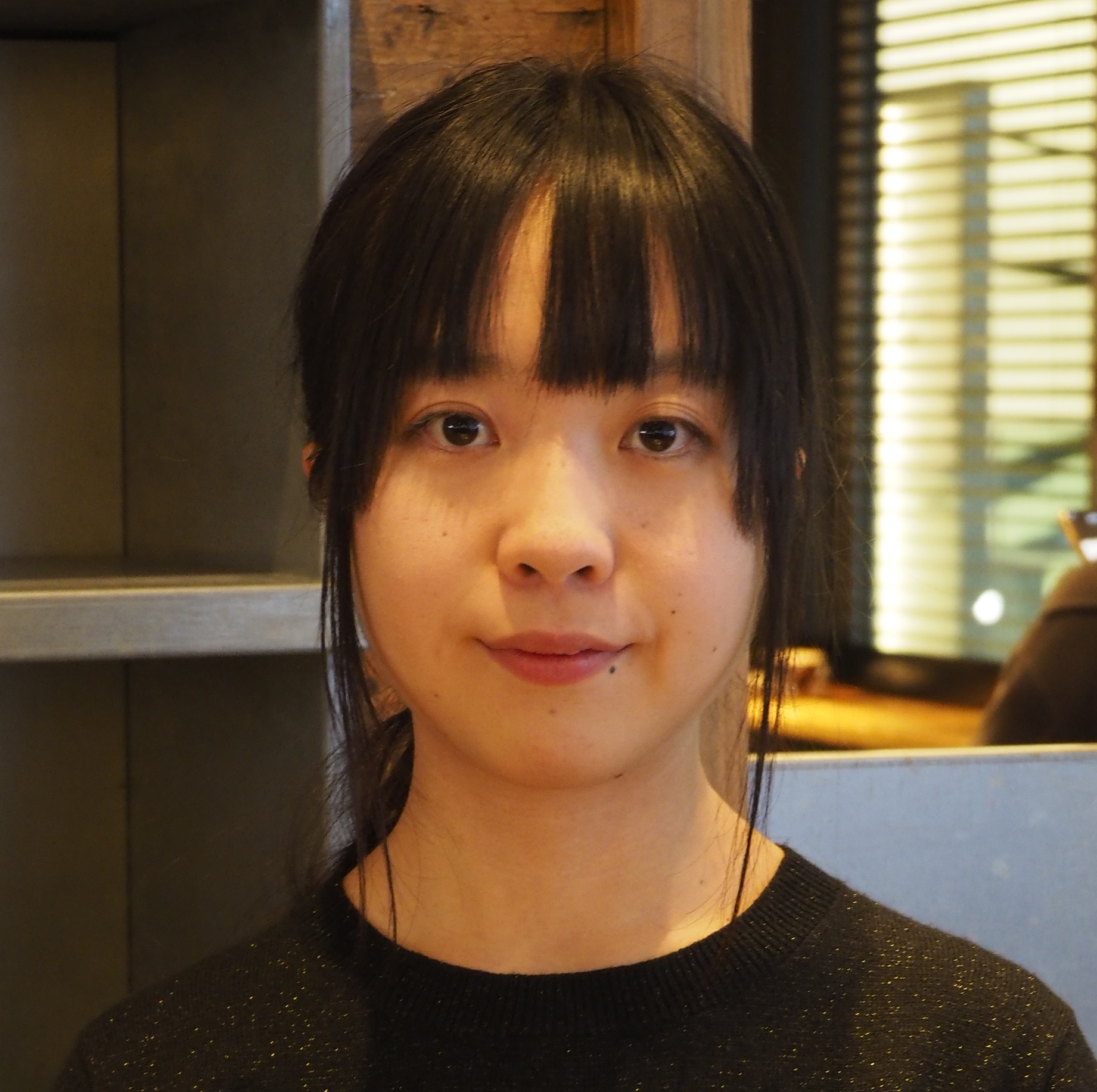デジタルメディアが台頭するなかで、印刷物には「早い」「安い」だけでなく価値を高めることが求められている。マーケティングの活用もその要素のひとつであるが、五感に訴えるという紙(印刷物)の魅力を増幅するのが各種表面加工や特殊印刷である。
本研究会では、新技術を活用した光沢加工や箔押しの紹介、機能性インクや特殊印刷による新たな用途提案、またデジタル印刷機における特殊・特色トナーの活用を取り上げる。
構成と内容
【1】 多種多様な特殊加工による印刷物の高付加価値化
株式会社太陽堂成晃社 代表取締役 宮本 武紀 氏
光沢加工の専業者として創業。2008年にオフセット印刷機(UV)を導入し、印刷と加工を組み合わせた新たなビジネス分野に挑戦。
オフセット印刷+コールドフォイル、オフセット印刷+疑似エンボス、あるいはアルミ蒸着紙やホログラム紙、不織布紙などの特殊原反への印刷など多様な表現を実現。
さらに、KRUZ社のDM-LINER(金型を必要としないオンデマンド箔印刷)を導入し、液体トナーや紛体トナーを使った電子写真方式デジタル印刷との組み合わせも積極的に取り組んでいる。
———————————————————-
【2】機能性インクと特殊印刷によるTRICK PRINTの技術と事例
株式会社SO-KEN 代表取締役 浅尾 孝司 氏
TRICK PRINTは、同社が提供する特殊印刷サービスの総称である。
以下の5つの製品群からなる。
1.ブラックライトプリント
ブラックライトで画像が光るプリント
2.ソーラープリント
太陽の光(紫外線)に当たることで画像が浮き出るプリント
3.エディブルプリント
可食性色素技術でフルカラーで鮮明な可食印刷が可能に
4.フラッシュプリント
フラッシュ撮影をする事で初めて写るプリント
5.リライトプリント
まったく異なる2つの広告を1つの電飾サインで表現
バックライトのON-OFFが切り替わることで昼と夜で違う訴求が可能となる
それぞれの特殊印刷の特長、用途、事例を紹介する
———————————————————-
【3】特殊トナー・特色トナーによる印刷物の価値向上
(1)1パス6色の印刷によりメタリックカラーなど多彩な特殊色を表現
(2)不可視トナー(インビジブルレッド)による用途提案
~セキュリティ、トレーサビリティ、加飾(ブラックライト印刷)
———————————————————-
※講演者・講演内容は一部変更になることがあります。
開催情報
【日時】
2019年7月2日(火) 14:00-17:00 (終了時間は延長する場合があります)
【会場】
日本印刷技術協会 3Fセミナールーム(〒166-8539 東京都杉並区和田1-29-11)
【参加費】
15,120円(税込)、JAGAT会員:10,800円(税込)
印刷総合研究会メンバー: 無料 [一般]2名まで [上級]3名まで [特別]5名まで
→自社が研究会メンバーか確認したい場合は、お手数ですがこちらのフォームからお問合せください。
申込み
WEBから
・Web申込フォーム に必要事項をご記入のうえ、ご登録ください。
登録後は完了メールが入力したメールアドレス宛に届きます。
FAXから
・申込書に必要事項をご記入の上、 FAX(03-3384-3216)にてお申し込みください。
(印刷総合研究会メンバーの方は、別途送付の専用申込み用紙をご利用ください)
問い合わせ先
内容に関して
研究調査部 印刷総合研究会担当 電話:03-3384-3113(直通)
お申し込み及びお支払に関して
管理部 電話:03-5385-7185(直通)