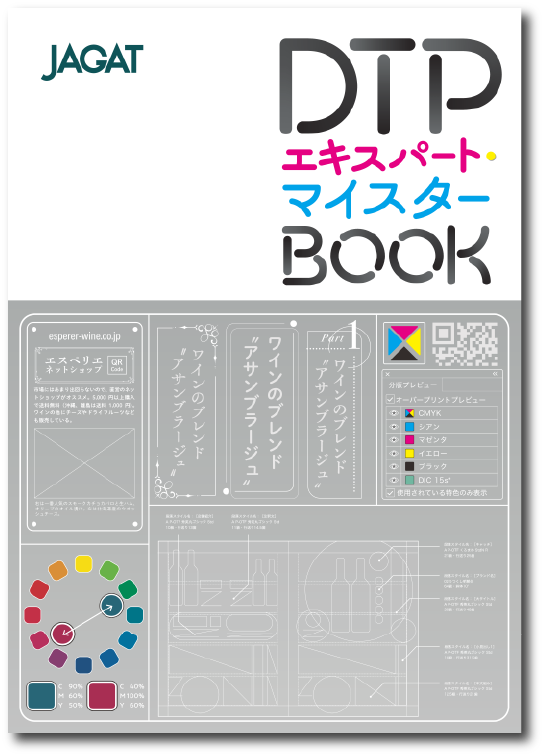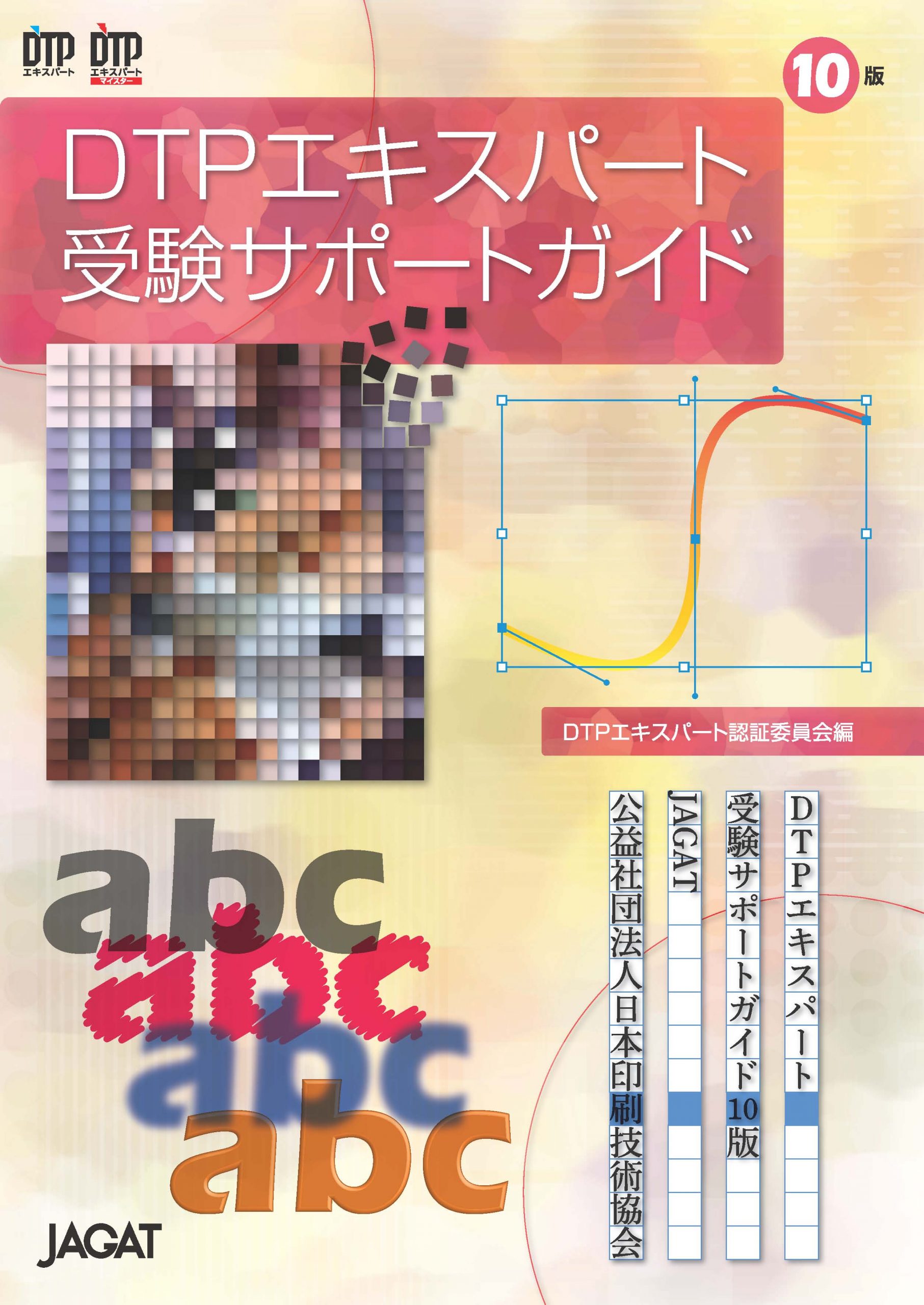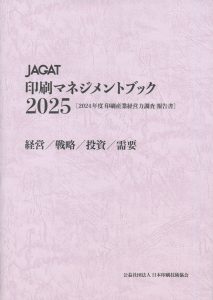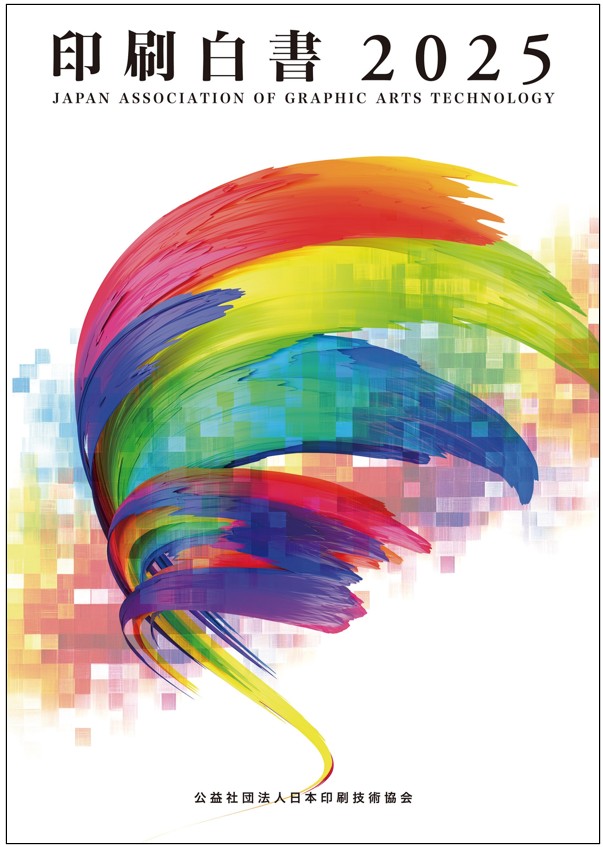「令和2年(2020年)東京都産業連関表」によれば、東京都の印刷産業生産額は6293億円、全国の印刷産業生産額に占める割合は15.4%。(数字で読み解く印刷産業2025その10)
全国産業連関表と東京都産業連関表
JAGAT『印刷白書2025』では、日本全国を対象とした全国産業連関表の最新版「令和2年(2020年)産業連関表」を使って、印刷産業の取引を見ています。
国内全体の経済構造を表す「全国産業連関表」に対して、都道府県や一部の市が作成している産業連関表は、その地域内の財・サービスの取引を明示し、地域経済の構造を可視化するものです。
「東京都産業連関表」は、こうした都道府県産業連関表の持つ特徴に加えて、東京都の経済の実態をより的確に表すため、①地域間表の作成、②本社部門の設定、③移動消費部門の設定が行われています。東京都の経済は、他道府県との相互依存、本社機能の集積、通勤・通学・観光など都外からの昼間流入という影響が大きいからです。
東京都の生産額は全国の約5分の1
「令和2年(2020年)東京都産業連関表」が11月27日に公表されました。都内の産業が1年間に行ったモノやサービスの取引を示した統計表で、5年ごとに作成されています。
東京都における2020年の財・サービスおよび本社の生産額は209兆8080億円で、全国の生産額(1097兆5247億円)に占める都の割合は19.1%を占めています。
東京都の印刷産業(印刷・製版・製本)生産額は6293億円で、全国の印刷産業生産額(4兆875億円)に占める都の割合は15.4%です。
なお、東京都産業連関表の全国の生産額(1097兆5247億円)は、全国産業連関表の生産額(1026兆1540億円)および東京都産業連関表(地域間表)の本社部門の生産額(71兆3707億円)の合計を指すものです。
東京都の生産額とその構成比を見ると、サービス(対事業所サービス、医療・福祉、教育・研究など)56兆4730億円(26.9%)、情報通信34兆1912億円(16.3%)、本社32兆4273億円(15.5%)、不動産21兆9094億円(10.4%)、商業21兆8531億円(10.4%)となり、これら5部門で都内生産額の79.5%を占めます。印刷産業(印刷・製版・製本)は6293億円(0.3%)です。
東京都に集積している産業は、産業別特化係数(=東京都の産業別構成比÷全国の産業別構成比)が高い産業で、1を超えればその産業のウェイトが全国水準を上回ることになります。特化係数が高い部門は、情報通信2.75、本社2.38、金融・保険1.60、不動産1.27、商業1.23となっています。逆に低い部門は、農林漁業0.02、鉱業0.02、製造業0.14、電気・ガス・水道0.37、建設0.64となっています。印刷産業(印刷・製版・製本)は0.81となりました。
東京都と他道府県との取引を見ると、東京都は本社、情報通信、サービス、商業などで他道府県へサービスを提供(移出)し、他道府県の経済を下支えしています。一方、東京都は製造業で他道府県から多くの製品を購入(移入)し、他道府県の産業の顧客や消費者となっています。
東京都の移出計73兆5539億円に対し、移入計は33兆1871億円と、差し引き40兆3668億円の移出超過となっています。この移出超過のうちの50.0%(20兆1805億円)は本社部門の移出超過です。印刷産業(印刷・製版・製本)の移出は2590億円、移入は9644億円で、7054億円の移入超過となっています。
『印刷白書2025』(2025年10月31日発刊)の第2章 印刷産業の動向「産業連関表」では、「令和2年(2020年)産業連関表」(2025年7月再推計)と「平成23-27-令和2年接続産業連関表」を使って、印刷産業と取引先やクライアント産業の動きを見ています。
また、限られた誌面で伝え切れないことや、今後の大きな変更点は「数字で読み解く印刷産業」で順次発信していきます。ご意見、ご要望などもぜひお寄せください。
(JAGAT 研究・教育部 吉村マチ子)