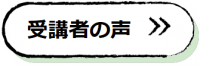[コンペに勝つ3つの重要なポイント]
情報戦で6割、企画で1割、プレゼンで3割
印刷物やWeb制作のコンペの勝敗は、実は企画そのもの以上に重要なポイントがあります。それは営業パーソンの情報収集力です。その精度を高めることで、勝てる可能性はぐっと上がります。
収集した情報を的確に反映した企画やプレゼンテーションを行うことができれば、勝率はさらに大きく高まります。
印刷会社の営業パーソンがコンペに勝つための情報収集、企画、プレゼンテーションの方法について、経験豊富な現役プレゼンターが解説します。
●コンペに参加する際、貴社は以下のような状況になっていませんか?
![]()
・企画書の制作は制作担当者にお任せ
・当日のプレゼンテーションも制作担当者にお任せ
・営業のクライアントから得ている情報が少なく企画設計に困る
![]()
・どのような情報を収集するべきかわからない
・企画書の設計方法がわからない
・プレゼンテーションは苦手で、上手に話すこともできないし緊張する

営業パーソンを戦力化しコンペへ積極的に関与させることで
貴社のコンペ勝率は高まります!
本講座は、コンペで勝てる営業パーソンの育成を目的としたカリキュラムを編成しています。
[カリキュラム]
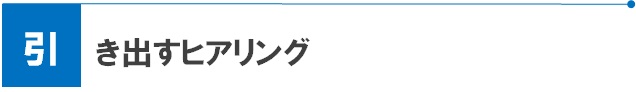
企画を強みとする会社でも軽視されがちなヒアリングは、単に情報を引き出すだけでなく、自社を売り込む機会でもある。そこから勝負が始まっていることを理解し、コンペで勝てるための営業力を学ぶ。
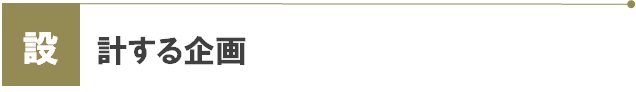
引き出した情報から相手のニーズや心理を的確に捉え、それを解決できる企画力を身につけることで、クライアントや制作物の読み手の心に刺さる企画の考え方や設計の仕方を学ぶ。
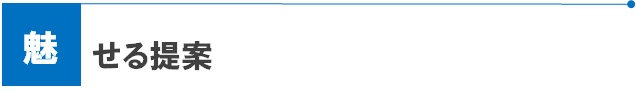
コンペにおいて重要となる提案書。美しいデザインは勿論、企画のポイントを抑えた表現や章立てにより、競合より優位に立ちクライアントを魅了する提案書の作成手法を学ぶ。
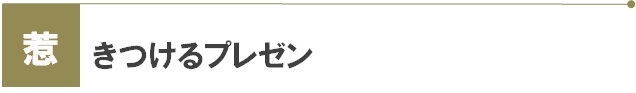
提案において重要なウエイトを占めるのがプレゼンテーション。話すのが苦手、緊張してしまう等、苦手意識を持つ人でも、簡単に成功するための秘訣を学ぶ。

株式会社BLY PROJECT 代表取締役
布施 貴規
コピーライターとして大手家電メーカーや楽器メーカーの広告を手がける。その後、マーケティング・プランナーとして、新規メディアの立ち上げやWeb事業のスタートアップを牽引する。
2014年 (株)BLY PROJECTを立ち上げ、企業のマーケティング活動を、マス媒体、プリントメディア、Webメディアなど、全方位においてクリエイティブでサポートする一方、セミナー講師や研修講師としても精力的に活動している。
開催日時
2025年9月4日(木)14:00~17:00
対象
印刷、Web制作の企画、営業の方
参加費(税込)/1名
JAGAT会員 15,400円 /一 般 20,900円
最少催行人数
6名
研究会・セミナーのZoomウェビナー参加方法のご案内
セミナーお申し込み後の流れについて
お申込み
●Webからのお申込み
必要事項をご入力のうえ、お申込みください。
●FAXでのお申し込み
![]()
お申込書に必要事項をご記入のうえ、
03-3384- 3216までFAXにてお送りください。
■参加費振込先
参加費は、下記口座に開催日の2日前までに振り込 み願います。
なお、お申し込み後の取り消しはお受けできません。代理の方のご出席をお願いします。
口座名:シャ)ニホンインサツギジュツキョウカイ
口座番号:みずほ銀行中野支店(普)202430
■内容に関して問い合わせ先
内容に関するお問い合わせはお気軽に 下記までお寄せください。
CS部 セミナー担当 電話:03-3384-3411
■お申し込み及びお支払に関して
管理部(販売管理担当) 電話:03-5385-7185(直通)
公益社団法人 日本印刷技術協会