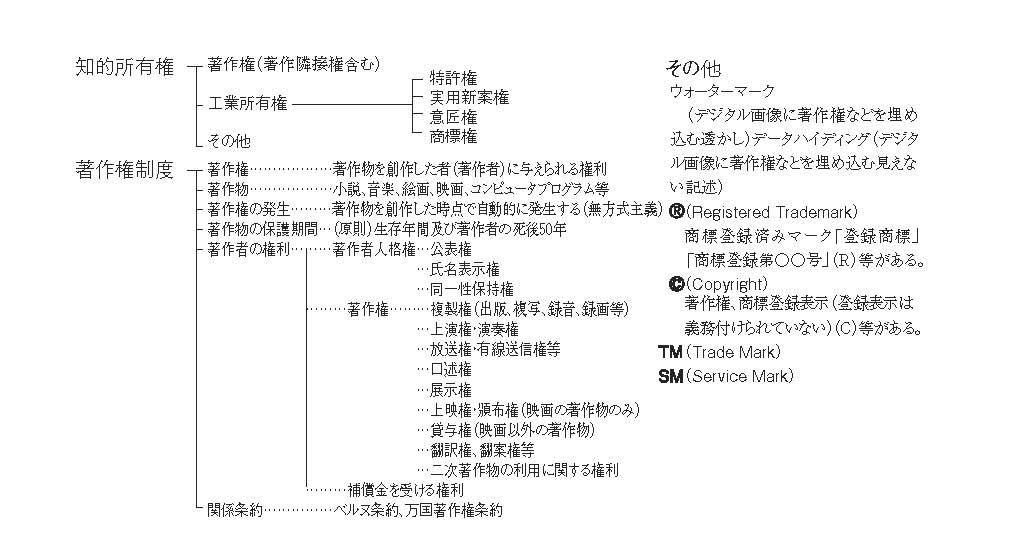メディアはインターネットが普及する以前、広告を目的としたものと、SP(Sales Promotion:販売促進)を目的としたものとして位置付け、メディアプランニングを実施するのが一般的であった。
ATL とBTL
広告メディアはマスコミ4 媒体(新聞、雑誌、ラジオ放送、テレビ放送)が主な役割を担い、ATL(AboveThe Line)と呼ばれ、「認知度」を高めることを目的で利用されている。
一方、プロモーションメディアについてはBTL(Below The Line)と呼ばれ、OOH(Out Of Home:交通広告、屋外広告など)、折込広告、DM(Direct Mail)、フリーペーパー、フリーマガジン、POP 広告(Point Of Purchase advertising)などといったさまざまなメディアが含まれており、生活者の「興味」を高めたり、「購入」を促進する目的で利用されている。
ここで「Line」が示す意味は「境界線」を指し、メディア特性に応じてそれぞれを位置付ける考え方とされている。したがって、ATL は主に「ブランディング」を目的としたメディアであり、BTL は主に「プロモーション(販売促進)」を目的としたメディアと位置付けることができる。
インターネットメディア
インターネットの普及と技術の進化に伴い、インターネットメディアはATL とBTL をシームレスに担う第3のメディアとして、地位を確立した。
インターネットメディア(ミドルメディア)は、パソコンのほか、ケータイ、スマートフォン、タブレットなどといったさまざまな端末を通じ、コーポレートサイト、EC(Electronic Commerce)サイト、ネット広告、ブログ、SNS(Social Networking Service)などが展開されている。インターネットメディアでは、電子決済システムとの連携により、告知から販売に至る処理をワンストップで提供することが可能になった。昨今では物流にも影響を与え、生活者の購買行動に変化も及ぼしている。さらに、スマホやタブレットといったモバイル端末が普及することで、インターネットメディアはさまざまな市場に影響を与えることが予想される。また、インターネットメディアには、生活者の購買行動に関する詳細なデータを蓄積できる特性がある。この特性により、行動変数による精度の高いターゲティングや、マーケットバスケット分析による傾向値を踏まえた商品のレコメンド(推薦)などをはじめとするマーケティングを実現している。
さらに、インタラクティブ性と購買行動データを生かし、電子メールやBBS(Bulletin Board System:電子掲示板)をはじめ、「LINE」や「Skype」などのソーシャルメディアによる対話形式のコミュニケーションを行うことも可能になった。「Facebook」や「twitter」などによる口コミ手段の発達により、生活者間の情報交換が盛んに行われることに起因する「バイラルマーケティング」や「バズマーケティング」が手法化された。企業にとって口コミは、広告やプロモーション、人的販売、パブリシティに並ぶ生活者とのコミュニケーション手段として活用されている。
メディア特性
従来の広告メディアやプロモーションメディアに加え、インターネットメディアが普及した昨今では、生活者にとって適切な時間や場所を意識したメディアを選定し、情報の受発信を行うことにより、設定した目的や目標を果たす効果を期待できる。そのためには、さまざまなメディアの特性を理解する必要がある。
【ATL】
<マスコミ4 媒体>
マスコミ4 媒体は、ほかのメディアと比べ「情報伝達の範囲が広い」「注目度が高い」などのメリットがある。しかしながら「多くの費用を要する」といったデメリットもある。
対象については、ある程度のセグメントを意識しすることができるが、不特定多数に対する情報発信となる。企業と生活者のコミュニケーションでは、マーケティングやPR(Public Relations)、IR(Investor Relations)の手段として利用される。また、従来の「ながら聴取および視聴」は、ラジオ放送が主だったものと考えられていたが、モバイル端末の普及により「テレビ放送を視聴しながらスマホでインターネット検索」や「雑誌を閲読しながらタブレットでECサイトから商品を購入」などの行動をとる生活者も増えてきた。
【BTL】
BTL にはさまざまな種類のメディアあり、プロモーションに対し直接的に関与するため、高い到達率が期待できる。例としてOOH とDM を取り上げる。
<OOH>
OOH は、ほかのメディアと比べ広い範囲に設置および掲示できることから「表現に柔軟性を持たせることができる」などのメリットがある。しかし、「多くの費用を要する」「一定期間は変更することができない」などのデメリットもある。対象は設置場所に訪れる生活者となるが、企業と生活者のコミュニケーションではマーケティングやPR の手段として利用される。
<DM>
顧客リストにより対象者に直接送付する紙広告であり、工夫により高いレスポンスが期待できるメディアである。他社との違い(オファー[特典]提供)により、生活者の購買意欲を高めることも重要視される。セグメンテーションを的確に行えば、費用対効果も期待でき、キャンペーンなどでは有効に利用されている。的確に大量な情報を提供することも可能であり、視覚に訴求することができるなどのメリットがある。しかし、「1 件当たりの費用が高い」「送付先の収集が必要となる」「発送までに時間がかかる」「封書の場合、開封率が低い」などのデメリットもある。
企業のメディア戦略
プロモーションメディアは、本稿で取り上げたOOHやDM のほか、チラシやPOP 広告、フリーペーパー、フリーマガジンなどさまざまなメディアが存在する。また、新たなマスメディアが登場する可能性もある。さらにインターネットメディアは、際限なく新たなサービスが登場するほか、モバイル端末の進化も予想され、眼鏡型や腕時計型などのウェアラブルデバイスが普及することが予想される。そのような中、企業が継続的な発展を遂げるには、さまざまなメディアを駆使し、ステークホルダーとの適切なコミュニケーションを図る必要がある。経営戦略に則ったメディア戦略を実現するために、本稿で取り上げたメディアだけでなく、さまざまなメディアの特性を理解した上で、活用を計画的に行うことが求められる。
JAGAT CS部
Jagat info 2014年7月号より転載