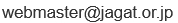JAGATは豊富な図版とわかりやすい解説で、DTPの基本知識とDTPエキスパート受験のための基礎が学習できる「DTPベーシックガイダンス」を発刊した。
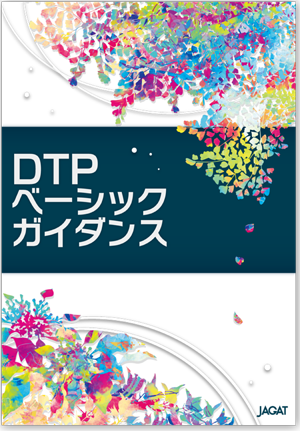
「DTPベーシックガイダンス」まえがき
DTPの基礎を学ぶための参考書は多々ありますが、本書はJAGATのDTPエキスパート認証試験対策セミナーのレジュメをもとに誕生しました。
早いものでDTPエキスパート認証試験も2016年8月の試験で46回目を迎えます。初期のDTP環境は、知識も、ワークフローも、オペレーションも、人によってバラバラで、信頼できる指針がなかった混沌としたものでした。そのような中、標準的な指針を示す必要性から生まれた「DTPエキスパート認証試験」が、日本の印刷物製作のデジタル化、DTP化へ貢献してきた点は決して少なくないと自負しています。
スタート時の混沌としたDTP環境も、瞬く間に進化しました。今や「DTPエキスパート認証試験」の解説書は、膨大な量の情報が網羅されており、効率よく勉強するには少々骨が折れます。しかし、本書「DTPベーシックガイダンス」は、セミナーで講義の理解をより深めるためのレジュメをもとにしているため、図版が豊富で分かりやすく、効率よく学習することができます。
現代のDTPエキスパートは、DTPオペレーションだけではなく幅広い知識が必要です。DTP以外の新しい情報も常に仕入れて行く必要があり、時間との勝負でもあります。そこで、スピーディにDTPの基礎を学べ、DTPエキスパートを目指す方にとってもベーシックな知識を学べる本書は、最適な教科書と言えます。
DTP経験者にとっても、知識の再整理に役立つとともに最新知識を勉強する良い参考書になることでしょう。
本書をフル活用し、最新DTP知識を学び、考え、実践し、ぜひ「DTPエキスパート認証試験」の合格を目指してください。
JAGAT専務理事 郡司秀明
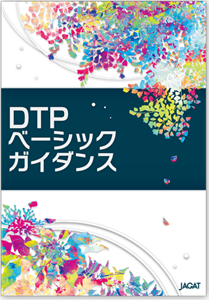 |
JAGAT BOOK STORE 『DTPベーシックガイダンス』のページへ
発行日:2016年6月23日 ※ご注文受付を開始しました |