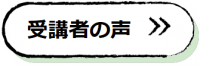JAGATセミナーは人材育成の観点で印刷業界を支援し、人材のボトムアップから業界活性化を図ることが目的である。基本方針は、「印刷会社の“今”の課題を解決」「明日から仕事で使える」とし、印刷現場、営業、マーケティング、デザイン制作、法務、会計と多岐に渡るテーマを取り扱っている。今回は、2022年上期に開催したセミナーについて報告する。
続きを読む
「営業・企画系」カテゴリーアーカイブ
新卒採用活動の次はフォローアップが重要!
会社の痛手となる新入社員の離職
人事採用と入社後人材育成は、印刷会社の成長においても重要な取り組みだ。中小企業の新卒採用担当者の中には、「会社を知名度で決める」「採用競争力」など大企業に比較しての悩みを抱えてことを聞くことがある。リクルートワークス研究所によれば、過去10年5,000人以上の大手企業の求人倍率は1倍以下と採用がしやすい状況があるが、一方、300人未満の有効求人倍率は、常に3倍以上を推移している。コロナ禍により超売り手市場であった2021年卒の3.40倍よりも上がり、22年卒採用においても「5.28倍」と依然として採用難であることが分かる。
一方、苦労して採用に結びつけても、昨年令和3年10月の厚生労働省のプレスリリースによれば、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者36.9%、新規大卒就職者31.2%ということである。新卒者本人だけでなく企業側にとっても大きな痛手だ。更に、毎年1割近くが1年以内で離職している。新卒者が1年以内に離職することは珍しくない状況だ。
理想と現実とのギャップを埋めるフォローアップ
離職の理由のひとつに「理想と現実とのギャップ」が挙げられるがことが多い。入社3カ月~半年が過ぎたあたりから、現実との壁が生じる。そのギャップを埋めることが重要だ。現実的な仕事に対するやりがいや働き方に起因する事柄を共に解決していくことが必要になる。採用活動の次の課題はフォローアップである。教育をはじめとする社員が成長するための計画的な施策と環境は不可欠だ。フォローアップは、新入社員研修からある程度時間が経ってから繰り返し行うことを意味する。「会社での帰属意識を高め、生産性を向上させる」「研修効果の定着や離職率を低下させる」などの狙いがある。手段としては、フォローアップ教育研修などもあるが目的が重要だ。仕事に直面した新入社員の不安や疑問を解決することが目的だ。単に専門知識を詰め込むことでないことを認識し、寄り添うことが肝心なところだ。一般的に用いられる方法では、「人事面談で意見を聴く」「上司によるフォローアップ」、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度「メンターをつける」「フォローアップ研修」などがあるが、会社全体として取り組むことが必要になる。
(CS部 古谷芸文)
2022年度秋期
【オンライン】フォローアップ総合研修
「まるまる学ぶサービス」
【オンライン】印刷技術の基礎知識
【オンライン】印刷営業の基本
事故にみる工場のヒューマンエラー対策
交通事故にみるヒューマンエラー
工場管理でやっかいな課題に人為的過誤やミスであるヒューマンエラーがある。ヒューマンエラーに起因するトラブルや事故は、工場に限ったことではない。警察庁によれば、交通事故におけるアクセルとブレーキの踏み間違いによる人身事故は過去5年(2016~20年)で2万1103件発生し、248件が死亡事故につながっているという。よく高齢者による事案が話題になるが年齢に限らずヒューマンエラーの視点で捉えることも重要だ。国土交通省自動車局が2018年9月に公表した「自動車の安全確保に係る制度及び自動運転技術等の動向について」では、2016年のヒューマンエラーによる法令違反に起因する交通死亡事故は全死亡事故の97%に上るという。また、内閣府が同年発表した「平成28年中の道路交通事故の状況」での死亡事故原因は「わき見」や「漫然運転」「安全不確認」といった安全運転義務違反が55%を占めている。「一時停止違反」や「速度違反」なども多いようだ。こうしたヒューマンエラーへの対応策は、自動運転システムの普及と人間の心理的、生理的特徴への対応だともいわれている。
犯人捜しでは解決できないヒューマンエラー対策
人が活動する限りヒューマンエラーは無くすことはできない。なくならいことを前提に考える必要がある。トラブル対応では、事故を起こした当人を探し責める場面があるが、犯人捜だけでは解決できない。孔子の教えに「罪を憎んで人を憎まず」とあるが、同様にトラブル自体に目を向けなければならい。原因を把握したうえで適切な対策を講じて発生しにくい環境を整えることが大切だ。コンサルソーシング株式会社のサイト記事(2018年7月28日)では、事務ミス・作業ミスの多い人の傾向的特徴と対策の方法・事例について解説してある。人それぞれに傾向と特徴があり、それに合わせた対策を行うことで効果的にヒューマンエラーやミスを軽減することができるというものだ。例えば、人の行動特性を7つタイプに分ければ下記のようになる。
- 細部が気になる人
- 場当たり的に仕事をする人
- 言われたことしかしない人
- 認識が他の人とずれる人
- 何でも抱え込んでしまう人
- 仕事が中途半端な人
- すぐ忘れる人
タイプ別に対応は異なる。ヒューマンエラーは、人の特性を理解し、それぞれに応じた対策が求められる。対応策としては、人に仕事の中に潜むミスを気づかせる見える化改善に繋げることが必要になるという。ミスの検出力を高めるミーティングや見える化の改善策が有効になるとうことだ。工場管理においては、改善活動とヒューマンエラー対策はセットで考える必要があるのだ。
CS部 古谷芸文
印刷工場の競争力を高めるための「工場改善活動の進め方」
工場のトラブル対応!「ヒューマンエラー対策」
【オンライン】印刷ビジネスで利益を出すための会社数字の見方、捉え方
印刷業の財務・会計視点を学ぶ
会社で利益を出すためのお金の流れを学ぶ講座です。財務・会計、いわゆる会社の数字において、仕事で貢献する視点を学び、生産性や働き方を向上させることが利益にも繋がります。
印刷業界の事例を交えて、数字に対する意識を高め、社員ひとり一人のパフォーマンスが会社の利益に大きく関係していくことを理解し、定量的に物事を判断するためのビジネス数字を学びます。
開催日時
2022年9月14日(水) 13:00~17:00
対象
印刷会社数字の基礎を学びたい方、若手社員、再確認したい社員、実践的な数字知りたい方、他
プログラム
<会社数字のアウトライン>2時間
・会社数字とは何か
・会社の数字と財務諸表の見方
・仕事とお金の動き
・変動費と固定費(管理会計)
・会社の利益(黒字)を知る
・求められる生産性と働き方
<実務・実践編>2時間
・大まかな会社の収益構造の解説
・「得する仕事と損する仕事」
・仕事の仕方と会社数字との結びつき
・数字にみる会社数字に貢献する仕事
※講師やプログラムはやむを得ず一部変更する場合があります。
講師
 寶積 昌彦 (ほうづみ まさひこ)
寶積 昌彦 (ほうづみ まさひこ)
株式会社GIMS コンサルタント・中小企業診断士
【プロフィール】
立命館大学卒業後、ハマダ印刷機械株式会社入社。各種印刷機、CTP等関連機器等多岐にわたる機械の営業担当を経て、営業管理・推進業務を担当。市場調査や製品開発企画とプロモーション、仕入商品・部材の調達管理や販売・製造台数の予測などの業務に従事。その後、グラビア印刷会社朋和産業株式会社に入社し、大手コンビニエンスチェーン、大手カフェチェーンの軟包材の営業を担当後、中小企業診断士として独立し、現在に至る。
中島 章裕(なかじまあきひろ)
大東印刷工業株式会社 第一営業部 営業三課課長 兼 業務課課長
定員
50名(最少催行人数5名)
参加費(税込)/1名
JAGAT会員 15,400円/ 一 般 20,900円
●研究会・セミナーのZoomウェビナー参加方法のご案内
●セミナーお申し込み後の流れについて
お申込み
●Webからのお申込み
●FAXでのお申込み
お申込書に必要事項をご記入のうえ、
03-3384-3216までFAXにてお送りください。
■参加費振込先
参加費は、下記口座に開催日の2日前までに振り込み願います。
なお、お申し込み後の取り消しはお受けできません。代理の方のご出席をお願いします。
口座名:シャ)ニホンインサツギジュツキョウカイ
口座番号:みずほ銀行中野支店(普)202430
■内容に関して問い合わせ先
内容に関するお問い合わせはお気軽に下記までお寄せください。
CS部 セミナー担当 電話:03-3384-3411
■お申し込み及びお支払に関して
管理部(販売管理担当) 電話:03-5385-7185(直通)
公益社団法人 日本印刷技術協会
工場の日常管理、維持管理、叱ると怒るの境界線
パワハラが社会問題とされる中、悩む管理者
工場をマネジメントする管理者は、人を育てる意識が重要だ。2021年6月に大手運送会社では、上司2人からの度重なる叱責(しっせき)によるパワーハラスメント(パワハラ)などを理由に、営業所で自殺していたことが明らかになった。同社では内部通報があったが生かせなかったという(東京新聞2021年11月5日)。2020年4月にパワハラ対策を大企業に義務付けた法律施行後も、働く人の自殺は後を絶たない。2022年4月より中小企業にも義務付けられた。一方、昨今の工場の管理者は、生産性の向上や部下への指導と関わり方で「厳しく接すること」がうまく実践できずに悩んでいることを耳にする。パワハラが社会問題とされる中、過剰に気を遣うことは容易に理解できる。
「叱る」と「怒る」の違いを学ぶ
5S活動をベースに工場改善に取り組む上では、日常管理、維持管理が第一歩となる。維持管理は至ってシンプルで部下に決まったことやルールを守らせることである。維持管理ができなければ、工場づくりは進まない。時には守らない部下を厳しく躾ける必要が出てくる。指導するコツのひとつが「叱る」と「怒る」の境界線を知ることだ。「叱る」は、人を育てるための教育であり理性である。一方、「怒る」は、個人的でコントロールができない感情であり暴力にあたる。叱ることを学ぶ必要がある。
ルールを守れない場合は、原因を探求することが肝心
2022年6月9日(木)に開講した「第2期印刷工場養成講座」(JAGAT主催、全6回)での初回「経営と印刷工場のマネジメント」では、石川秀人氏(コンサルソーシング株式会社、コンサルタント)を招き、部下の指導についても触れられた。叱るときのポイントは、熱くなりすぎず要点を絞り込んで指摘することだという。部下に問題の重大性を認識させ、同じ失敗を繰り返さないように考えさせることだ。根本的には、部下に反省や気付きを促すという目的を意識して指導できるかどうかである。ルールを守れない場合は、原因を探求することが肝心だ。原因は、いくつかのパターンに整理できる。
①決まったことを知らない、忘れてしまった。
②内容を理解していない
③管理者が根気強く教えていない
④守れない者に叱り方が分からない
⑤守っていないことに当事者が気づかない
⑥守っていない犯人捜しで終わっている
⑦作業の指示が曖昧で、報連相が無い
⑧維持管理のサイクル(PDCA)が回っていない
守れない原因は何故かということを繰り返し考えることが重要だ。そして、原因に合わせて対処するのだ。考えることによって理性的に対応することへも繋がる。考えさせることを学ぶのだ。指導の仕方を身に着けることで人材が育ち工場の競争力に繋がる。
(CS部 古谷芸文)
先行予約案受付中!第3期【オンライン】印刷工場長養成講座
最新版!DTPアプリケーションの徹底活用
PDF入稿の運用方法とトラブル対策
情報の活かし方とアイデア発想法
DTP制作のための組版の基礎知識
スマートフォンと縦型動画のトレンド
誰もがカメラマン、誰でもできる動画編集
動画の需要は、益々高まりコンテンツや使い方も様々だ。多くの印刷会社でもビジネスチャンスとしての関心度が高いようだ。ただし、動画制作の受注案件も単純に収録や編集の作業を請け負うのであれば、印刷ビジネスと同様に価格破壊が起きている。スマートフォンに代表される技術やネットワーク環境は、誰もがカメラマンで、誰でも動画編集をすることを可能にしている。受注においては、クラウドワークスやランサーズに代表されるクラウドソーシングにより誰もが競合と成り得る時代だ。ビジネスでは、ユーザーのニーズとトレンドをいち早く掴み、独自のサービスを提供するしくみが求められる。
スマートフォンで様相が変わった 動画
縦型動画が増えている。大きなトレンドだ。スチール写真のフレームは、横や縦に活用されてきたが、動画は、従来のテレビやパソコンで見ることを前提に作られてきたので横型にフレームが決まっていた。最近では、スマートフォンでの需要が増えて様相が変わった。Webコンテンツは、スマートフォンのフレームに合わせていち早く変わったが、動画コンテンツ多くは未だに横型だ。通常、横型で作られたコンテンツをスマートフォンでフレームいっぱいに見る場合は、縦から横に持ち方を変える必要がある。そのままだと天地を余した小さなフレームで見ることになる。最近、YouTubeやFacebookといった動画配信プラットフォームでもスマートフォン向けのタテ型動画への対応が始まっている。
動画コンテンツの縦型への移行は意外と大きな出来事のようだ。考えてみれば、収録するビデオカメラは横型フレーム向けに設計されているし、編集するPCやアプリケーションも横型がベースになっている。更に、大きな変化はコンテンツづくりだ。人間の視野に近い横型に比べ縦型はメッセージとしての質が異なり、企画立案やクリエイティブのアプローチが変わってくる。
存在感を増す縦型
「動画は横長」という常識が変わりつつある。英語で縦型の意味を持つ単語をバーティカルと言い、それをスマートフォンで再生するアプリを「バーティカルシアターアプリ」という。2020年10月にスタートしたバーティカルシアターアプリ「smash.(スマッシュ)」は、2022年3月に200万ダウンロードを超えた。サービスを提供するSHOWROOM株式会社の前田裕二氏(代表取締役社長)のインタビュー記事(日経新聞オンライン2022年4月5日)によれば、縦型ドラマの事業で頓挫した米国クイビー社を分析するなど「刺さるコンテンツ」の配信を目指すという。smash.は、プロクオリティーであることを売りにしている。誰でも投稿できるYouTube(ユーチューブ)やTikTok(ティックトック)と一線を画し、プロのクリエーターが制作し、プロのアーティストやタレントが出演する。「スマホでも、映画と同じぐらい人を感動させられる動画を作れることを証明したい」(前田氏)という思いからだという。徹底しているのは、画面を目いっぱいに使った「1対1」の没入感。縦型動画ならではの強みは1人称、つまり、自分があたかもその世界の中にいる感覚に浸れる主観映像が作りやすい点にあるという。100万ダウンロードの大台突破し、普及の後押には、韓国発7人組アーティストBTSのオリジナルコンテンツが大きな起点になったということだ。(日経ビジネス記事2021年7月29日)
コンテンツの力が大きい。縦型動画コンテンツの価値は、有名アーティストやクオリティーの高いドラマ、映画に限って発揮されることではない。ビジネスで必要とされる様々な用途がある。商品・サービス紹介や広告、採用者向け会社PR、研修資料などの顧客ニーズは多岐に渡る。また、すべての動画が縦型に移行するわけではない。動画受注ビジネスとしては、表現手段の選択肢が増えたと捉えるべきだ。企画立案や制作に当たっては、キーワードに「刺さる」コンテンツがある。刺さるとは、比喩的に刺されたような強い衝撃を受けるなどの感情や心の動きを表す言葉だ。つまり、前出にあった視聴者の没入感である。視聴者である顧客を知ることが鍵を握る。マーケティング視点でペルソナのような手法も必要になってくるようだ。
(CS部 古谷芸文)
印刷会社が ”ゼロから始める” 動画受注の基礎知識
【オンライン】DM企画制作実践講座
2022/6/8 【オンライン】発注者の活用事例から学ぶDMの可能性~DM企画制作ワンポイントセミナー~ お申込み
セミナー名:発注者の活用事例から学ぶDMの可能性~DM企画制作ワンポイントセミナー~
開催日:2022年6月8日(水) 16:00-17:00
参加費:JAGAT会員:無料 /一般:5,000円(税込)
→詳細案内ページ
・申込みは、下記のフォームに必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。
・申込フォームにメールアドレスを入力した後「Enter」ボタンを押すと、フォームの内容が送信されてしまいます。恐れ入りますが、「Tab」ボタンを使う、マウスを使うなどの方法でカーソル移動をお願いします。
※ご注意ください※
本 メールにご登録いただくと、申込完了メールが送信されます。登録後、数分経ってもメールが受領できない場合は、迷惑メールフィルタ等の要因が考えられま す。その場合は、お手数ですが、メール(![]() )またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。
)またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。
【ご入力いただいた個人情報に関する内容は厳正に取り扱います】
増える中小企業の副業・兼業人材の活用
新しい事業の成功には、優秀な人材の有無が成否を分けると言っても過言ではない。そのためには育成、採用が主たる人事施策であるが、今、注目を集めているのが副業・兼業の外部人材の活用である。 続きを読む
人が主体の標準化改善とマニュアル化
働き方の転換のために取り組むべき2つ のこと
サステナブルな社会やそれを具体化するSDGsへの企業の取り組みを良く見聞きするようになった。多くの印刷会社でも意識にはあるはずだ。SDGsを構成する17の目標は印刷工場にも関係する。人材確保の難しさもあり、中でも関係する持続的に社員を大切にする環境整備や働き方の質の向上への対応は急務である。
働き方の転換のために取り組むべきことは2つあるという。株式会社コンサルソーシング(2018年7月16日blog)によれば、1つは、長時間労働・残業などを助長する「仕事のブラックボックス化=属人化」を無くし、一人ひとりの仕事を適切に管理し、協業力を高めることと言われている。もう1つは、「価値で仕事を選り好みするスタイル」へ転換し、価値のない仕事をやめて生産性を高めることという。改善活動から多能化へ繋げ、標準化改善を行うことにより社員の仕事量と質をマネジメントすることが可能になる。
人が主体のマニュアル化
標準化と言えば、マニュアルが思いつく。かつてマニュアルは、“マニュアル通りの対応”というような負のイメージがあった。今は違うようだ。作業服の株式会社ワークマンのマニュアル書の捉え方が面白い。頑張らなくていいマニュアル書らしい。ダイヤモンドオンライン記事、GW限定講義(2022年5月8日)では、急成長を遂げるワークマンの仕掛け人、同社専務取締役の土屋哲雄氏の「『社員は頑張ってはいけない』と言い切っている、たった1つの理由」で、マネジメントについて語ってある。同社は、能力の高さではなく 「親切心」と「人柄」で広がる善意の連鎖を重要視しているとある。採用でも能力より人柄重視だという。行動規範では、自発性だ。フランチャイズの運営では、社員の自発性を重視する一方、小売業で最も標準化とマニュアル化が進んでいる企業でもある。加盟店の募集においても人柄重視である。店舗は100坪の標準店舗のみ、品揃えは全国で97%が共通、販売価格は変えない。小売未経験の加盟店がマニュアルどおりに運営すると、誰でも高収入が得られる仕組みができているという。ビジネスの仕組みと手順が決まっていれば安心感と気持ちに余裕ができる。頑張っている雰囲気ではなく、顧客に良い人柄を伝えることもできるというのだ。
マニュアル化は、捉え方で価値や運用が変わる。トヨタ生産方式の自働化にも人偏がついているように、上位にくるのは人間である。機械やシステムが作業をしても操るのは人間だ。標準化改善の本質も仕事をこなすことだけが目的ではなく、社員の能力を引き出し、働きがいを大切にするための活動だということを忘れてはいけない。
(CS部 古谷芸文)
【オンライン】印刷工場長養成講座
Web事業できちんと利益を上げるために必要な正しい知識とノウハウを身につける
印刷で培った強みを活かし、Webを受注する。そしてきちんと利益を上げていくためには印刷営業とはちがった勘所を押さえる必要がある。そして顧客満足を得るためには正しい知識とミッションを理解しているWebディレクターの育成が欠かせない。 続きを読む