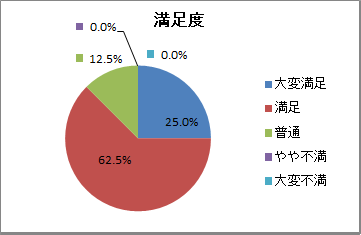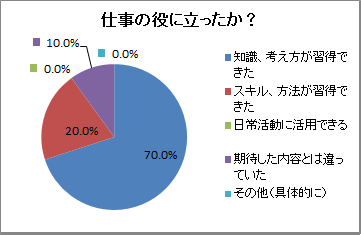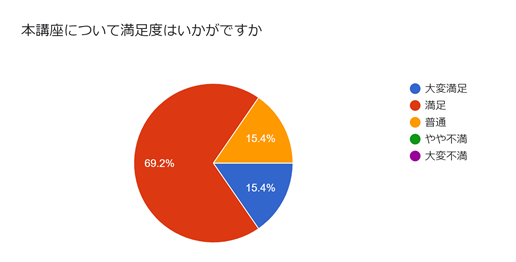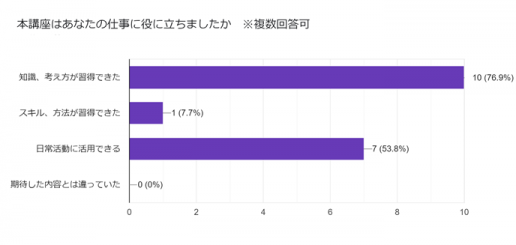長い労働時間は、日本の産業界の体質
生産性向上は、印刷産業界に限らず日本の産業界全体で解決すべき課題だ。日本の労働生産性が先進諸外国と比較して著しく低いことは、周知の通りだ。日本生産性本部がまとめた2017年における日本の労働生産性(時間あたり)は47.5ドルで、主要先進国では最下位だ。この数字は、1位の米国は72ドル、2位のドイツ69.8ドルに対して3分の2の生産性ということになる。生産性を決める要素は、付加価値、労働者数、労働時間の3つである。生産性は、「付加価値」を「労働者数」×「労働時間」で割ったものだ。つまり、先進国の中で、一番長く働いていても儲からない仕事の仕方をしていることになる。苦労しても報われない、貧乏暇なしの状態かもしれない。一方、印刷業での労働力不足、人材不足も深刻な課題だ。政府が掲げる働き方改革では、「長時間労働の是正」、「同一労働同一賃金」、「柔軟な働き方」があるが、印刷会社がこれらの課題に取り組むためには、企業の業績や環境が共に改善されなければ元も子もない。印刷会社が利益を生み出すことは、経営者に限らず社員全員で意識を高め取り組まなければならない。印刷会社は、効率よく利益を生み出すことが重要だ。ビジネスのしくみにより利益を生み出すことがマーケティングであるならば、印刷工場の利益の源泉は、生産効率である。これらの改題解決のひとつに多能工化がある。
多能工化への壁は、品質管理における作業の標準化と見える化
多能工とは、生産・施工の現場において、1人が一つの職務だけを受け持つ単能工に対し、1人で複数の異なる作業や工程を遂行する技能を身につけた作業者のことだ。多くの印刷工場の課題である多品種少量生産や品種・数量の変動に対して生産体制を柔軟に維持し、生産性の向上に効果的に取り組むことができる。一方、組織的に多能工化を進めるには、教育・訓練するしくみをつくる必要がある。多能工化へのボトルネックは、教育への手間暇と評価制度が上げられる。従来の勘や経験、徒弟制度的な教育では困難だ。標準化や見える化への取り組みは必須なのだ。
一概に印刷工場の多能化といっても、印刷会社の規模や事業領域によって、取り組み方も様々なようだ。page2020セミナー「印刷工場の生産性向上実践 ①~多能工化編~」では、二つの違った多能工化への取り組みを紹介し、生産性、働き改革の視点からも検証する。水上印刷株式会社の事例では、「きれいな工場でしか良い印刷物は作れない」をスローガンに最先端の設備と環境を備えた工場で「4S」「機械設備の保全」「品質」「多能化」のー連の活動の中、多能工化を位置づけしている。工場内の整理整頓はもとより、セキュリティや安全管理がゆきとどいた環境で社員の働きやすさにも繋がっている。「スピード」「フレキシビリティ」「クオリティ」の3つの要素を達成する道筋になっている。職場環境が人材育成と製品の品質にも結びついていることがポイントだ。
また、大東印刷工業株式会社の事例では、徹底した「見える化」への取り組みがポイントだ。同社では「印刷タクシーメーター」と呼ばれるその仕事の原価が、今どのくらいかかっているのかがリアルタイムに「見える」ことでコスト意識を高め、目標管理を行い、効率的に仕事を進めるしくみづくりに特徴がある。その業務管理システムの構築を通じ、生産性向上の中での複数の工程をカバーした多能工化について紹介する。
一概に多能工化といってもそれぞれのビズネス形態や規模によっても様々であることが分かる。重要なことは、単なる真似や知識だけでは、多能化や改善活動は上手くいかないことだ。如何に考え、葛藤し、モチベーションを高めたかを学ぶことが重要になる。
CS部 古谷芸文